お役立ちコラム 2025.08.26
家庭用蓄電池で売電収入を増やす方法と注意点

家庭用蓄電池の導入を検討しているかたのなかには、「蓄電池をつかって効率的に売電したい」「蓄電池があると売電単価はどうなるの?」といった疑問をおもちのかたも多いのではないでしょうか。 太陽光発電システムと蓄電池を上手に組み合わせることで、電気代の節約だけでなく、売電収入を最適化することも可能です。 ただし、蓄電池の導入時期や運転モードの設定によっては、かえって経済的なメリットが減ってしまうケースもあるため、正しい知識をもって判断することが重要です。
この記事では、家庭用蓄電池と売電の関係について、基本的な仕組みから最新のサービスまで詳しく解説します。 とくに、2019年度を境に大きく変わったFIT制度のルールや、蓄電池から直接売電できる革新的なサービス「わけトク」についても紹介します。 家庭用蓄電池の導入を検討しているかたはもちろん、すでに導入済みで運用方法に悩んでいるかたにも役立つ情報をお届けします。

目次
家庭用蓄電池と売電の基本知識

太陽光発電と蓄電池の仕組み
太陽光発電システムは、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する設備です。 屋根に設置した太陽光パネルで発電した直流電力を、パワーコンディショナーで交流電力に変換して家庭内で使用します。 晴れた日の昼間は発電量が多くなり、曇りや雨の日、夜間は発電できないという特徴があります。
一方、家庭用蓄電池は、電気を貯めておくことができる大型の充電池です。 リチウムイオン電池が主流で、容量は4kWhから16kWh程度まで幅広いラインナップがあります。 蓄電池があれば、昼間に太陽光発電で作った電気を貯めておき、夜間や停電時に使用することができます。
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで得られるメリットは以下のとおりです。
• 発電した電気を無駄なく活用できる • 電気料金の削減効果が高まる • 停電時でも電気が使える安心感 • 環境にやさしいエネルギー利用が可能 • 電力の地産地消に貢献できる
とくに近年は、電気料金の高騰により、売電するよりも自家消費したほうが経済的メリットが大きくなっています。 2023年10月時点で、電力会社から購入する電気料金は1kWhあたり約30円ですが、FIT制度での売電価格は16円程度です。 このような状況下で、蓄電池は重要な役割を果たしています。
電気の流れと売電の優先順位
太陽光発電システムと蓄電池を導入した場合、電気の流れには明確な優先順位があります。 基本的な流れは「発電→自家消費→蓄電→売電」の順番で、システムが自動的に判断して制御します。 この優先順位を理解することで、より効率的な運用が可能になります。
まず、太陽光発電で作られた電気は、その時点で家庭内で使用している電力(自家消費)に優先的に充てられます。 たとえば、エアコンや冷蔵庫、照明などで使用する電力は、太陽光発電の電気でまかなわれます。 次に、自家消費しきれなかった余剰電力は、蓄電池に充電されます。
蓄電池の容量が満杯になると、それ以上充電できない余剰電力が売電に回されます。 夜間や発電できない時間帯は、蓄電池に貯めた電気を優先的に使用し、蓄電池が空になったら電力会社から電気を購入します。 この一連の流れは、以下の表のようにまとめることができます。
| 時間帯 | 太陽光発電 | 電気の使い道 | 優先順位 |
|---|---|---|---|
| 昼間(晴天時) | 発電あり | 自家消費→蓄電→売電 | 高い順 |
| 昼間(曇天時) | 発電少量 | 自家消費→蓄電 | 高い順 |
| 夜間 | 発電なし | 蓄電池から放電→買電 | 高い順 |
このような電気の流れを最適化することで、電気料金の削減と売電収入の最大化を図ることができます。 ただし、運転モードの設定によっては、この優先順位を変更することも可能です。 次の項目で、蓄電池導入による売電への具体的な影響について詳しく見ていきましょう。
蓄電池導入による売電への影響
蓄電池を導入すると、売電量や売電収入にさまざまな影響があります。 最も大きな変化は、売電量が減少する一方で、自家消費率が大幅に向上することです。 この変化は、必ずしもデメリットではなく、むしろ経済的なメリットにつながることが多いのが現状です。
具体的な数値でみると、太陽光発電のみの場合の自家消費率は約30%程度ですが、蓄電池を導入すると50%以上に向上します。 これは、昼間に発電した電気を蓄電池に貯めて、夜間に使用できるようになるためです。 結果として、電力会社から購入する電気量が大幅に削減され、月々の電気代を抑えることができます。
蓄電池導入による影響を整理すると、以下のようになります。
• 売電量の減少:蓄電池への充電分だけ売電量が減る • 自家消費率の向上:30%→50%以上に増加 • 電気料金の削減:買電量が減少し、月々の支払いが軽減 • 売電単価への影響:導入時期により異なる(後述) • 災害対策の強化:停電時でも電気が使える
とくに注目すべきは、売電価格と電気料金の逆転現象です。 2023年度のFIT価格16円/kWhに対して、電気料金は30円/kWh以上となっており、売電するよりも自家消費したほうが約2倍お得な計算になります。 このため、蓄電池導入により売電量が減っても、トータルでの経済メリットは大きくなるケースがほとんどです。
ダブル発電による売電単価の変化
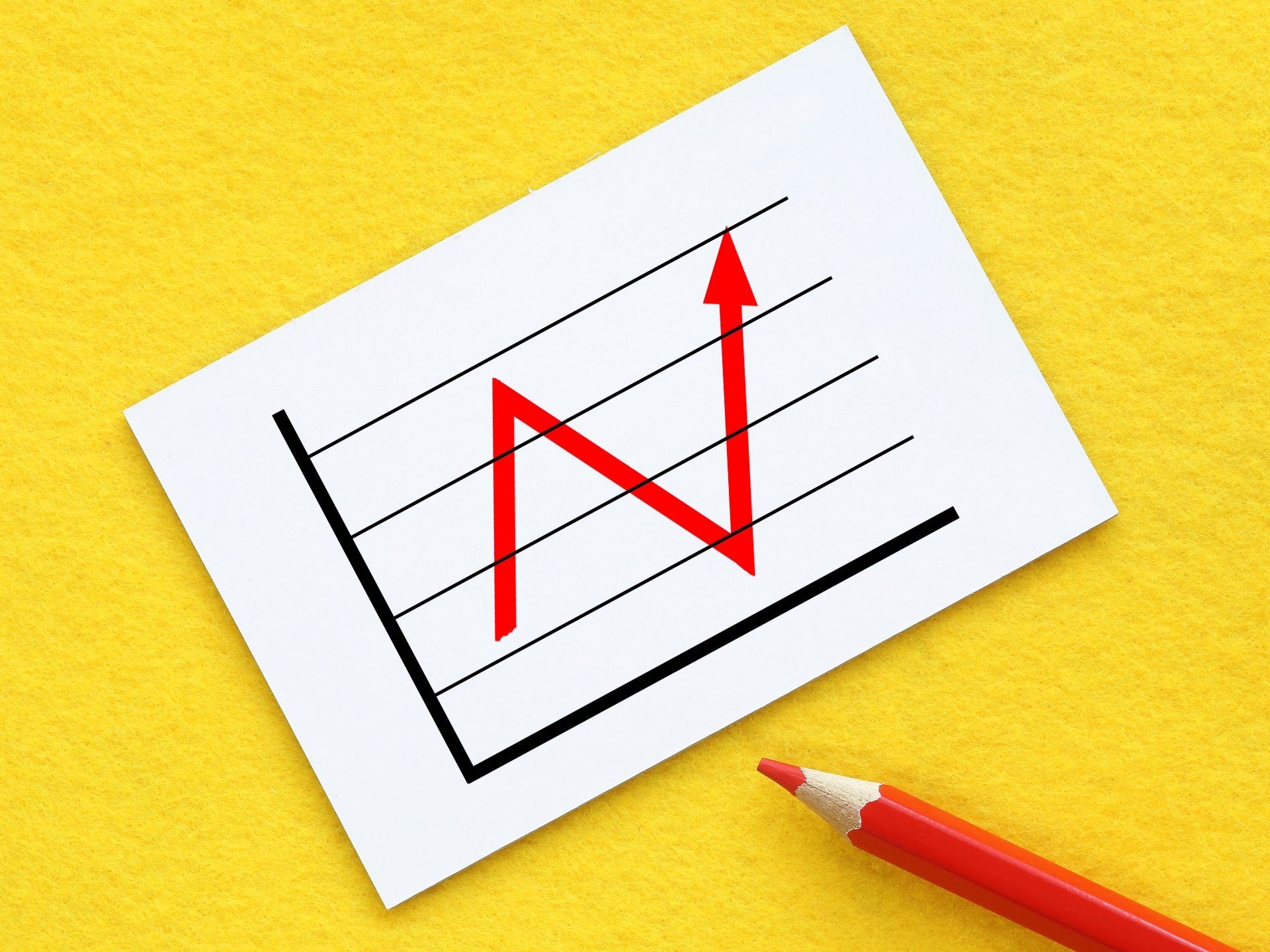
ダブル発電とは何か
ダブル発電とは、太陽光発電システムと他の発電・蓄電設備を併用することで、売電量を増やす仕組みのことです。 具体的には、太陽光発電と蓄電池、エネファーム、エコウィルなどの創エネ機器を同時に運用する方法を指します。 この名称は、複数の電源を使用することで、太陽光発電の余剰電力を「押し上げる」効果があることに由来しています。
押し上げ効果とは、蓄電池などから放電した電気で自家消費をまかなうことで、太陽光発電の電気をより多く売電に回せる現象です。 たとえば、昼間の電力使用を蓄電池からの放電でカバーすれば、太陽光発電の電気はすべて売電できることになります。 この仕組みにより、シングル発電(太陽光発電のみ)と比較して、売電量を増やすことが可能になります。
ダブル発電に該当する主な機器は以下のとおりです。
| 機器名 | 特徴 | 押し上げ効果 |
|---|---|---|
| 家庭用蓄電池 | 電気を貯めて必要時に放電 | あり |
| エネファーム | ガスで発電・給湯 | あり |
| エコウィル | ガスエンジンで発電・給湯 | あり |
| V2H(一部) | 電気自動車の電池を活用 | 機種による |
ただし、すべての蓄電池がダブル発電になるわけではありません。 シングル発電用の蓄電池は、売電時に放電を停止する機能があり、押し上げ効果が発生しないよう設計されています。 このような機器の違いを理解することで、自分の目的に合った設備選びが可能になります。
FIT制度における売電単価の違い
FIT制度(固定価格買取制度)では、ダブル発電とシングル発電で売電単価に差を設けていた時期があります。 この制度設計の背景には、ダブル発電による押し上げ効果で売電量が増えることへの配慮がありました。 しかし、2019年度を境に、この取り扱いが大きく変更されています。
FIT制度の変遷を理解することで、蓄電池導入のタイミングによる影響を正確に把握できます。 とくに、すでに太陽光発電を設置している方が蓄電池を後付けする場合は、認定年度によって売電単価への影響が異なるため注意が必要です。 以下、年度別の詳細について見ていきましょう。
2019年度以降は単価差なし
2019年度以降にFIT認定を受けた太陽光発電システムでは、ダブル発電でもシングル発電でも売電単価は同じです。 これは、売電価格が電気料金に近づいたことで、押し上げ効果による不公平感が小さくなったためです。 つまり、2019年度以降に太陽光発電を設置した方は、蓄電池を導入しても売電単価が下がる心配はありません。
具体的な売電単価は以下のとおりです。
• 2019年度:24円~26円/kWh(出力制御対応機器の有無により異なる) • 2020年度:21円/kWh • 2021年度:19円/kWh • 2022年度:17円/kWh • 2023年度:16円/kWh
この変更により、蓄電池導入のハードルが大きく下がりました。 売電単価を気にすることなく、純粋に自家消費のメリットや災害対策の観点から蓄電池を選べるようになったのです。 とくに、電気料金が30円/kWhを超える現在では、売電よりも自家消費を優先することが経済的に有利になっています。
2018年度以前は単価が下がる
2018年度以前にFIT認定を受けた太陽光発電システムの場合、ダブル発電にすると売電単価が下がります。 この差額は年度によって異なり、古い認定ほど差が大きくなる傾向があります。 たとえば、2015年度認定の場合、シングル発電33円~35円/kWhに対して、ダブル発電では27円~29円/kWhと、6円/kWhもの差があります。
年度別の売電単価の差を表にまとめると以下のようになります。
| 認定年度 | シングル発電 | ダブル発電 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 2015年度 | 33~35円/kWh | 27~29円/kWh | 6円/kWh |
| 2016年度 | 31~33円/kWh | 25~27円/kWh | 6円/kWh |
| 2017年度 | 28~30円/kWh | 25~27円/kWh | 3円/kWh |
| 2018年度 | 26~28円/kWh | 25~27円/kWh | 1円/kWh |
この売電単価の差は、10年間のFIT期間中ずっと継続します。 そのため、年間の売電量が多い家庭では、累計で数十万円の差になることもあります。 ただし、自家消費による電気料金削減効果を考慮すると、それでも蓄電池導入のメリットが上回るケースも多いため、総合的な判断が必要です。
ダブル発電でも単価が下がらないケース
2018年度以前の認定でも、ダブル発電による売電単価の低下を避ける方法があります。 主な方法は、10kW以上の太陽光発電システムを設置している場合と、シングル発電用の蓄電池を選ぶ場合です。 これらの方法を知っておくことで、より柔軟な設備選択が可能になります。
まず、10kW以上の太陽光発電システムは、もともとダブル発電でも売電単価が変わりません。 これは、10kW以上のシステムが産業用として扱われ、全量売電が基本となるためです。 ただし、10kW以上のシステムは住宅用としては大規模で、設置には広い屋根面積が必要になります。
シングル発電用の蓄電池を選ぶ方法もあります。 これらの蓄電池には、以下のような特徴があります。
• 売電時は自動的に放電を停止 • 押し上げ効果が発生しない設計 • FIT制度上はシングル発電として認定 • 通常の蓄電池と同様に災害対策として機能 • 価格は通常の蓄電池とほぼ同等
代表的なシングル発電対応蓄電池メーカーには、パナソニック、シャープ、京セラなどがあります。 これらのメーカーの蓄電池は、運転モードの切り替えでシングル発電とダブル発電を選択できる機種も多く、将来的な運用変更にも対応可能です。 ただし、シングル発電モードでは押し上げ効果による売電量増加は期待できないため、純粋に自家消費のメリットで判断することになります。
蓄電池の運転モードと最適な売電戦略

主要な運転モードの特徴
家庭用蓄電池には、さまざまな運転モードが搭載されており、生活スタイルや電気の使用目的に応じて切り替えることができます。 各メーカーによって名称は異なりますが、基本的な機能は共通しています。 適切な運転モードを選択することで、電気料金の削減効果を最大化し、売電収入も最適化できます。
主な運転モードとその特徴は以下のとおりです。
| 運転モード | 主な動作 | 適した場面 |
|---|---|---|
| 自家消費優先モード | 余剰電力を蓄電池に充電し、売電を最小限に | 電気料金が売電価格より高い場合 |
| 売電優先モード | 余剰電力を優先的に売電し、蓄電池充電は最小限に | 売電価格が高いFIT期間中 |
| おまかせモード | AIが最適な充放電を自動判断 | 初心者や設定が面倒な方 |
| 強制充電モード | 系統電力で蓄電池を満充電 | 台風接近時など停電に備える場合 |
| 非常時モード | 停電時に蓄電池から給電 | 実際の停電発生時 |
とくに重要なのは、自家消費優先モードと売電優先モードの使い分けです。 自家消費優先モードでは、昼間の余剰電力をできるだけ蓄電池に貯めて、夜間に使用します。 一方、売電優先モードでは、余剰電力を積極的に売電し、蓄電池への充電は最小限に抑えます。
最近の蓄電池には、AI機能が搭載されているものも増えています。 天気予報や過去の電力使用パターンを学習し、翌日の発電量や消費量を予測して最適な充放電を行います。 これにより、ユーザーが細かい設定をしなくても、自動的に経済効果の高い運用が可能になっています。
電気代と売電単価で選ぶ最適モード
運転モードの選択で最も重要なのは、電気料金と売電単価の比較です。 基本的な考え方はシンプルで、「電気料金>売電単価」なら自家消費優先、「電気料金<売電単価」なら売電優先を選びます。 2023年現在の状況では、ほとんどの家庭で自家消費優先が有利になっています。
具体的な数値で比較してみましょう。 2023年度の新規FIT認定での売電価格は16円/kWhですが、電気料金は以下のような水準です。
• 従量電灯B(東京電力):約30円/kWh • オール電化プラン(昼間):約35円/kWh • オール電化プラン(夜間):約25円/kWh
この価格差を活用した場合の経済効果を計算すると、1,000kWh分の電力で以下のような差が生まれます。
• 売電した場合:16円×1,000kWh=16,000円の収入 • 自家消費した場合:30円×1,000kWh=30,000円の電気代削減 • 差額:14,000円(自家消費の方が有利)
このように、現在の価格体系では自家消費を優先することで、売電の約2倍の経済効果が得られます。 ただし、2018年度以前の高いFIT価格が適用されている場合は、状況が異なることもあるため、個別の計算が必要です。
FIT期間中と卒FIT後の運用方法
太陽光発電を導入してからの期間によって、最適な運用方法は変化します。 とくに重要なのは、FIT期間中(10年間)と卒FIT後の運用戦略の違いです。 それぞれの期間に応じた適切な運用を行うことで、長期的な経済メリットを最大化できます。
FIT期間中の運用方法は、認定年度によって異なります。
【2019年度以降の認定】 • 最初から自家消費優先モードを推奨 • 売電価格が電気料金を下回るため • 蓄電池導入による売電単価への影響なし
【2018年度以前の認定】 • 売電価格が高い場合は売電優先モードも検討 • ただし、ダブル発電による単価低下に注意 • シングル発電用蓄電池なら影響なし
卒FIT後は、売電価格が大幅に下がるため、運用方法の見直しが必須です。 一般的な卒FIT後の売電価格は8円~11円/kWh程度で、電気料金の3分の1以下になります。 この時期の運用ポイントは以下のとおりです。
• 自家消費優先モードに切り替え • 蓄電池未導入なら導入を検討 • 電気の使用時間を昼間にシフト • オール電化への切り替えも選択肢 • 新電力の高価買取プランも検討
とくに卒FIT後の蓄電池導入は、経済効果が高くなります。 売電収入の減少分を、自家消費による電気代削減でカバーできるためです。 実際のシミュレーションでは、卒FIT後に蓄電池を導入することで、年間10万円以上の電気代削減効果が得られるケースも珍しくありません。
蓄電池から直接売電できる新サービス
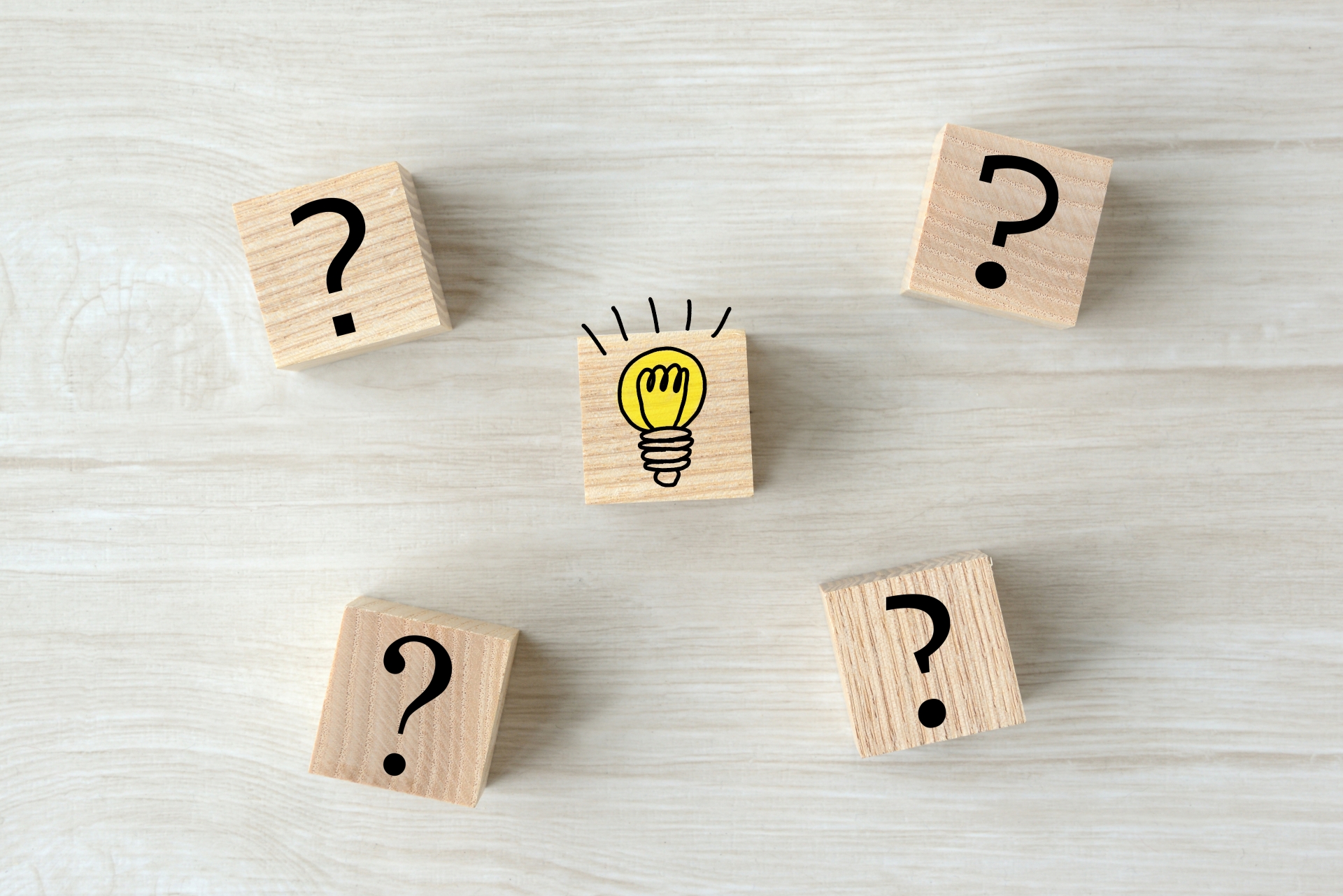
従来の蓄電池売電の制限
これまで、家庭用蓄電池に貯めた電気を売電することは、技術的にも制度的にも困難でした。 最大の理由は、蓄電池からの逆潮流(電力会社の系統への電力供給)に対応した機器が限られていたことです。 また、仮に技術的に可能でも、それを買い取る電力会社や制度が存在しませんでした。
従来の制限事項を整理すると、以下のようになります。
• 逆潮流防止機能により蓄電池からの売電は不可 • FIT制度では太陽光発電の電力のみが対象 • 蓄電池の電力源が不明確(系統充電か太陽光充電か) • 電力品質の管理が困難 • 買取事業者が存在しない
このような制限により、蓄電池はあくまで自家消費用の設備として位置づけられていました。 太陽光発電の余剰電力を貯めて夜間に使用することはできても、その電力を再び売電することはできなかったのです。 しかし、この状況は新たなサービスの登場により、大きく変わろうとしています。
電力システムの進化により、VPP(バーチャルパワープラント)という概念が注目されています。 これは、分散した小規模な電源や蓄電池を、あたかも一つの発電所のように統合制御する仕組みです。 この技術により、家庭用蓄電池も電力供給の一翼を担える可能性が開けてきました。
東邦ガス「わけトク」の仕組みと特徴
2024年、東邦ガスが提供を開始した「わけトク」は、家庭用蓄電池からの売電を可能にする画期的なサービスです。 このサービスは、地域の電力需給がひっ迫したタイミングで、蓄電池に貯めた電力を高値で買い取るという仕組みです。 従来の常識を覆すこのサービスは、新エネルギー財団会長賞も受賞し、注目を集めています。
わけトクの主な特徴は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 買取価格 | 32円~35円/kWh(2024年11月~2025年1月実績) |
| 買取タイミング | 電力需給ひっ迫時(事前通知あり) |
| 対象エリア | 東邦ガスサービスエリア |
| 初期費用 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 必要条件 | 東邦ガスとの電気契約・卒FIT契約 |
とくに注目すべきは、買取価格の高さです。 通常のFIT売電価格16円/kWhと比較して、2倍以上の価格で買い取られます。 これは、電力需給がひっ迫する時間帯の電力に高い価値があるためです。
わけトクの動作イメージは次のようになります。
- 東邦ガスから需給ひっ迫の予告通知
- 指定時間に蓄電池から自動放電
- 放電した電力量に応じて高値買取
- 翌月の電気料金から買取額を相殺
このサービスにより、蓄電池は単なる自家消費用設備から、収益を生み出す設備へと進化しました。 地域の電力安定供給にも貢献できるため、社会的意義も大きいサービスといえます。
対応機種と導入メリット
わけトクを利用するには、対応した蓄電池システムが必要です。 2024年時点で対応している機種は限られていますが、今後拡大が期待されています。 対応機種を選ぶことで、通常の蓄電池のメリットに加えて、新たな収益機会を得ることができます。
現在の対応機種は以下のとおりです。
• オムロンソーシアルソリューションズ「マルチ蓄電プラットフォーム」シリーズ • 長州産業「スマートPVマルチ」シリーズ
これらの蓄電池システムは、以下のような特徴を持っています。
【技術的特徴】 • 遠隔制御機能搭載 • 高精度な充放電管理 • 系統連系時の安定性 • リアルタイム通信機能
【導入メリット】 • 通常時は自家消費で電気代削減 • 需給ひっ迫時は高値売電で収益 • 地域の電力安定化に貢献 • 将来的なサービス拡大の可能性
わけトクによる年間収益シミュレーションをしてみましょう。 仮に月2回、各3時間の買取要請があり、1回あたり10kWhを売電した場合:
• 月間売電量:20kWh • 月間収益:20kWh×34円=680円 • 年間収益:680円×12ヶ月=8,160円
これは最小限の試算ですが、需給ひっ迫の頻度が高まれば、さらに大きな収益が期待できます。 また、通常の自家消費による電気代削減効果と合わせると、蓄電池の投資回収期間を大幅に短縮できる可能性があります。
蓄電池導入の経済効果と最適なタイミング

自家消費vs売電の収支比較
蓄電池導入の経済効果を正確に把握するには、自家消費優先と売電優先の収支を具体的に比較することが重要です。 実際のシミュレーション結果を見ることで、どちらの運用方法が有利かが明確になります。 ここでは、一般的な4人家族の住宅を例に、15年間の累計経済効果を検証してみましょう。
シミュレーション条件は以下のとおりです。
• 太陽光発電:4kW(南向き、傾斜角23度) • 蓄電池:6.5kWh • 月間電気使用量:600kWh • 電気料金:従量電灯B(50A) • FIT買取単価:16円/kWh(10年間) • 卒FIT後買取単価:8.5円/kWh • 電気料金上昇率:年2%
この条件での15年間の経済効果は次のようになります。
| 運用方法 | 電気代削減額 | 売電収入 | 合計経済効果 |
|---|---|---|---|
| 自家消費優先 | 約213万円 | 約60万円 | 約273万円 |
| 売電優先 | 約95万円 | 約65万円 | 約160万円 |
| 差額 | +118万円 | -5万円 | +113万円 |
このシミュレーション結果から、自家消費優先の方が15年間で113万円も有利なことがわかります。 売電収入は若干減少しますが、電気代削減効果が大幅に上回るため、トータルでの経済メリットは自家消費優先が圧倒的です。 とくに電気料金が今後も上昇すると予想される中、この差はさらに拡大する可能性があります。
蓄電池導入のベストタイミング
蓄電池導入のタイミングは、経済効果を大きく左右する重要な要素です。 最適なタイミングを見極めることで、投資効率を最大化し、早期の投資回収が可能になります。 主な導入タイミングとそれぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。
蓄電池導入の主なタイミングは以下の3つです。
【1. 太陽光発電と同時導入】 • メリット:工事が1回で済み、工事費を抑えられる • メリット:最初から最適なシステム設計が可能 • メリット:ハイブリッド型パワコンで効率向上 • デメリット:初期投資額が大きくなる
【2. FIT期間中の後付け】 • メリット:太陽光発電の投資回収後で資金に余裕 • メリット:蓄電池の価格下落を待てる • デメリット:2018年度以前はダブル発電に注意 • デメリット:追加工事費用が発生
【3. 卒FIT時の導入】 • メリット:売電価格下落のタイミングで最大効果 • メリット:10年間の実績データを活用した最適設計 • メリット:補助金制度が充実している場合が多い • デメリット:それまでの自家消費メリットを逃す
多くの専門家が推奨するのは、卒FIT時の導入です。 この時期は売電価格が8円~11円/kWhに下落するため、自家消費のメリットが最大化します。 また、10年間の発電実績と電力使用パターンのデータが蓄積されているため、最適な容量の蓄電池を選択できます。
投資回収期間の目安
蓄電池導入の投資判断で重要なのは、投資回収期間の把握です。 一般的に、家庭用蓄電池の投資回収期間は10年~15年といわれていますが、運用方法や電気料金の変動により大きく変わります。 具体的な計算方法と、回収期間を短縮するポイントを見ていきましょう。
投資回収期間の計算に必要な要素は以下のとおりです。
• 蓄電池システムの導入費用(工事費込み) • 年間の電気代削減額 • 売電収入の変化額 • メンテナンス費用 • 補助金の有無
一般的な6.5kWh蓄電池システムの例で計算してみます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 導入費用 | 150万円 |
| 補助金 | -30万円 |
| 実質負担額 | 120万円 |
| 年間削減効果 | 10万円 |
| 投資回収期間 | 12年 |
投資回収期間を短縮する方法として、以下のポイントがあります。
• 補助金制度の活用(国・自治体) • 適切な容量選択(過大な容量は避ける) • 効率的な運用モード設定 • 電気使用の時間シフト • わけトクなど新サービスの活用
とくに補助金の活用は重要で、国の補助金に加えて自治体独自の補助金を併用できる場合もあります。 これらを最大限活用することで、実質負担額を大幅に削減し、投資回収期間を10年以下に短縮することも可能です。
よくある質問と注意点
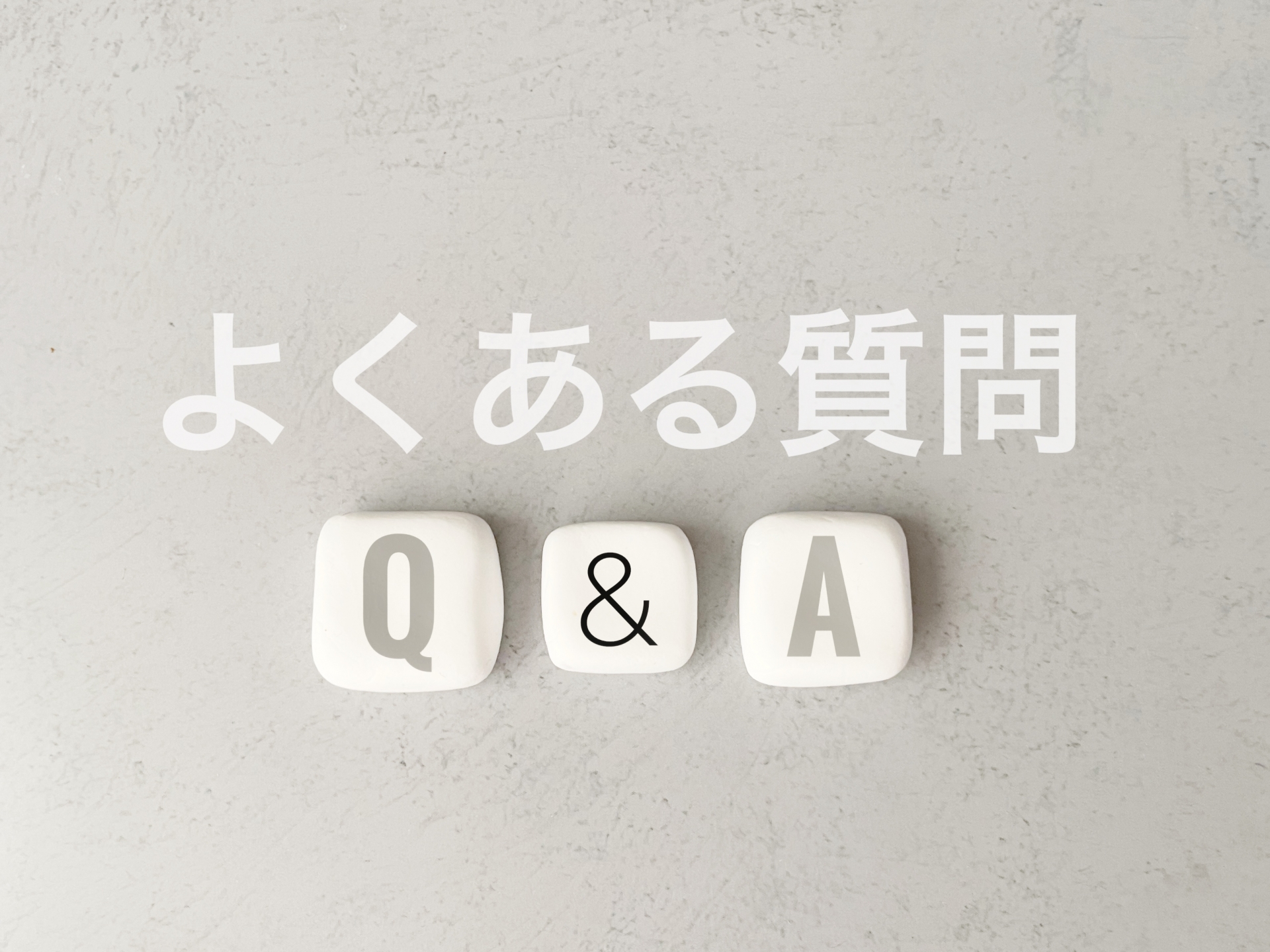
FIT制度への影響について
蓄電池導入を検討する際、多くの方が心配するのがFIT制度への影響です。 「蓄電池を設置するとFIT認定が取り消される?」「買取期間が短くなる?」といった誤解も少なくありません。 ここでは、FIT制度に関する正確な情報を整理してお伝えします。
まず、基本的な事実として、蓄電池の設置によってFIT認定が取り消されることはありません。 また、買取期間(10年間)が短縮されることもありません。 ただし、2018年度以前の認定では、ダブル発電により買取単価が変更される可能性があることは、すでに説明したとおりです。
FIT制度に関する重要なポイントをまとめると:
• FIT認定の取り消し:なし • 買取期間の変更:なし(10年間で変わらず) • 買取単価の変更:2018年度以前は要注意 • 変更申請:必要な場合あり • シングル発電用蓄電池:影響なし
変更申請が必要なケースは、以下のような場合です。
- パワーコンディショナーの変更を伴う場合
- 太陽光発電の出力が変わる場合
- ダブル発電への変更となる場合
これらの変更申請は、設置業者が代行してくれることがほとんどです。 ただし、申請漏れがあるとFIT認定に影響する可能性があるため、信頼できる業者選びが重要です。
V2Hシステム併用時の注意点
電気自動車(EV)の普及に伴い、V2H(Vehicle to Home)システムへの関心も高まっています。 V2Hは電気自動車のバッテリーを家庭用蓄電池として活用するシステムで、大容量かつ移動可能な蓄電池として注目されています。 しかし、太陽光発電との併用では、いくつかの注意点があります。
V2Hシステムの基本的な特徴は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 蓄電容量 | 40~60kWh(一般的なEV) |
| 出力 | 3~6kW |
| 価格 | 50~100万円(V2H機器のみ) |
| ダブル発電 | 機種により異なる |
V2Hシステム導入時の注意点として、最も重要なのがダブル発電への該当有無です。 一般的なV2Hシステムは押し上げ効果があるため、2018年度以前のFIT認定ではダブル発電となり、売電単価が下がる可能性があります。 ただし、「SMART V2H」と呼ばれる機種では、売電時の放電停止機能によりシングル発電として扱われます。
V2H導入のメリットとデメリットを整理すると:
【メリット】 • 大容量で長時間の停電対応が可能 • 移動可能な蓄電池として活用 • 車と家の両方で電気を活用 • 将来的な電力取引への参加可能性
【デメリット】 • 車の使用中は蓄電池として使えない • 初期投資が高額(車両+V2H機器) • ダブル発電による売電単価への影響 • 充放電による車載バッテリーの劣化
V2Hシステムは、ライフスタイルに合わせた選択が重要です。 毎日車を使用する方には不向きですが、週末のみの使用や、複数台所有している家庭では有効な選択肢となります。
災害時の運用方法
近年、自然災害の増加により、蓄電池の災害対策機能への注目が高まっています。 停電時でも電気が使える安心感は、蓄電池導入の大きなメリットの一つです。 しかし、災害時の運用には事前の準備と正しい知識が必要です。
災害時の蓄電池運用で重要なポイントは以下のとおりです。
• 平常時からの備え(残量設定) • 停電時の自動切り替え機能 • 使用可能な家電の把握 • 効率的な電力使用計画 • 復旧後の運用再開方法
まず、平常時の設定として、災害用の残量確保が重要です。 多くの蓄電池では、「非常時用残量」を設定でき、通常は20~30%程度を確保することが推奨されています。 これにより、急な停電でも最低限の電力を確保できます。
停電時に使用できる電力と時間の目安は次のとおりです。
| 蓄電池容量 | 使用可能な家電例 | 連続使用時間 |
|---|---|---|
| 5kWh | 冷蔵庫+LED照明+スマホ充電 | 約15時間 |
| 10kWh | 上記+エアコン(1台) | 約10時間 |
| 15kWh | 上記+IH調理器(短時間) | 約12時間 |
効率的な災害時運用のコツとして、以下の点が挙げられます。
• 優先順位を決めて家電を使用 • 昼間は太陽光発電で充電 • 夜間は最小限の電力使用 • 情報収集機器を優先 • 冷暖房は最小限に
また、長期停電に備えて、ポータブル電源や発電機との併用も検討する価値があります。 蓄電池はベース電源として使用し、補助的な電源を組み合わせることで、より長期間の停電にも対応可能です。
まとめ

家庭用蓄電池と売電の関係について、基本的な仕組みから最新のサービスまで詳しく解説してきました。 2023年現在、電気料金が売電価格を大きく上回る状況では、蓄電池を活用した自家消費優先の運用が最も経済的メリットが大きいことがわかりました。 とくに、15年間の累計で100万円以上の差が生まれることは、多くの方にとって驚きの結果だったのではないでしょうか。
また、従来は不可能だった蓄電池からの売電を実現する「わけトク」のような新サービスの登場により、蓄電池の価値はさらに高まっています。 単なる自家消費用の設備から、収益を生み出し、地域の電力安定供給にも貢献できる設備へと進化しているのです。 今後もこのような革新的なサービスが増えることで、蓄電池の可能性はますます広がっていくでしょう。
蓄電池導入を検討されている方は、まず自分の太陽光発電の認定年度と現在の電気使用状況を確認することから始めてください。 そのうえで、シミュレーションを行い、最適な容量と運用方法を選択することが成功への近道です。 補助金制度も積極的に活用し、賢い蓄電池ライフを実現していただければ幸いです。
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。






