お役立ちコラム 2025.10.13
蓄電池後付けの費用相場・補助金・工事完全ガイド徹底解説版
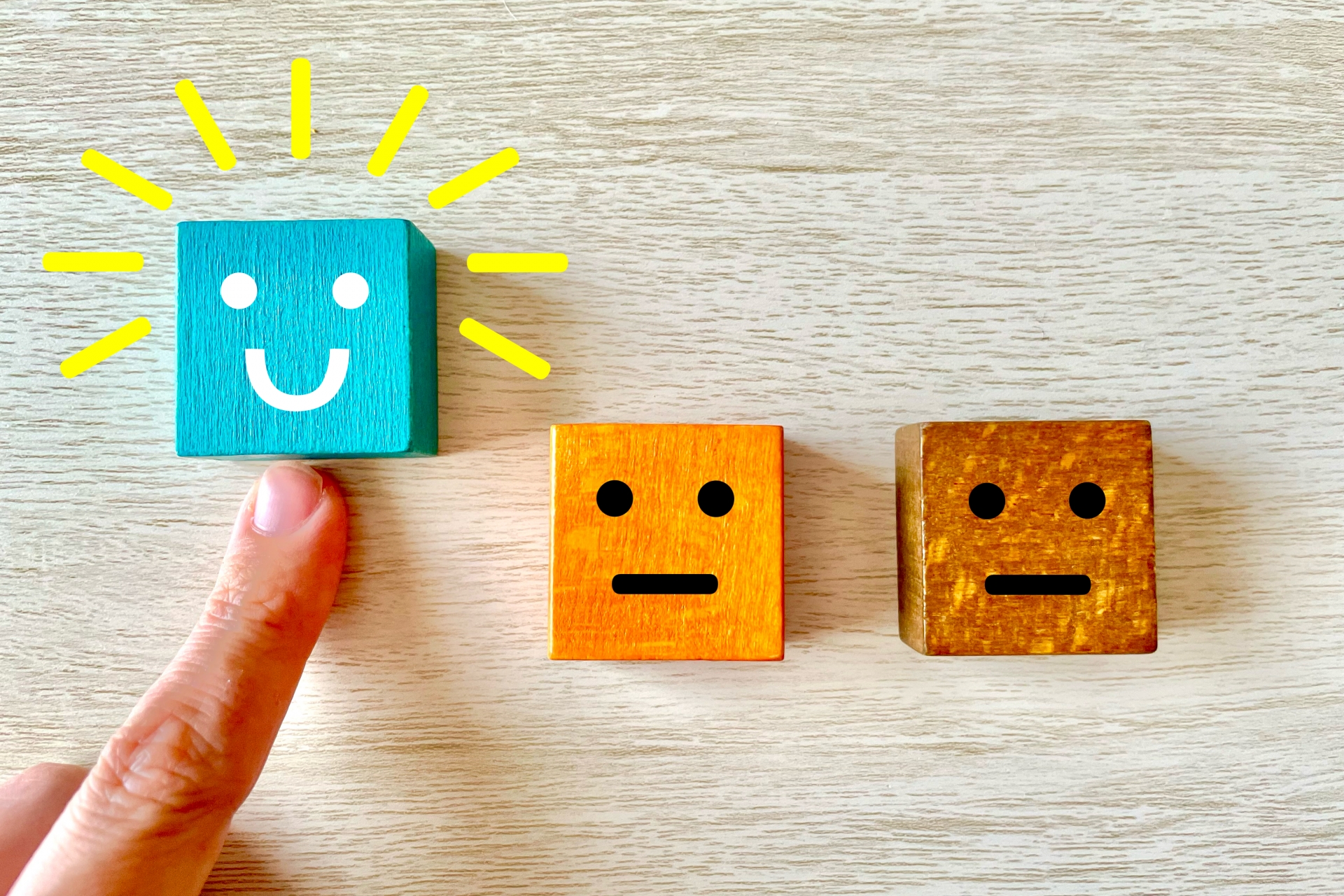
「すでに設置している太陽光発電に、後から蓄電池を追加できるの?」「費用はどのくらいかかるの?」
太陽光発電を導入済みの方の多くが、蓄電池の後付けを検討する際にこうした疑問を抱きます。
実は、太陽光発電と蓄電池を同時に設置するよりも、後付けの方が費用が高くなったり、工事が複雑になったりするケースがあります。
しかし一方で、卒FITを迎えた家庭では、後付けによる経済的メリットが大きいという側面もあるのです。
近年、FIT(固定価格買取制度)の売電単価が大幅に下がり、余剰電力を売るよりも自家消費する方が有利な時代になりました。
2019年以降、10年間のFIT期間を終えた「卒FIT」の家庭が増え続けており、蓄電池を後付けして自家消費率を高める動きが加速しています。
本記事では、太陽光発電に蓄電池を後付けする際の費用相場、補助金の活用方法、工事の注意点を徹底的に解説します。
単機能型とハイブリッド型の違い、既設パワーコンディショナーとの互換性、FIT制度との関係、補助金申請の手順など、後付け特有の複雑なポイントを分かりやすく整理してお伝えします。
すでに太陽光発電を設置している方、卒FITを迎えた方、これから蓄電池の後付けを検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
後付けの基礎理解―方式の違いと太陽光との相性をまず押さえる
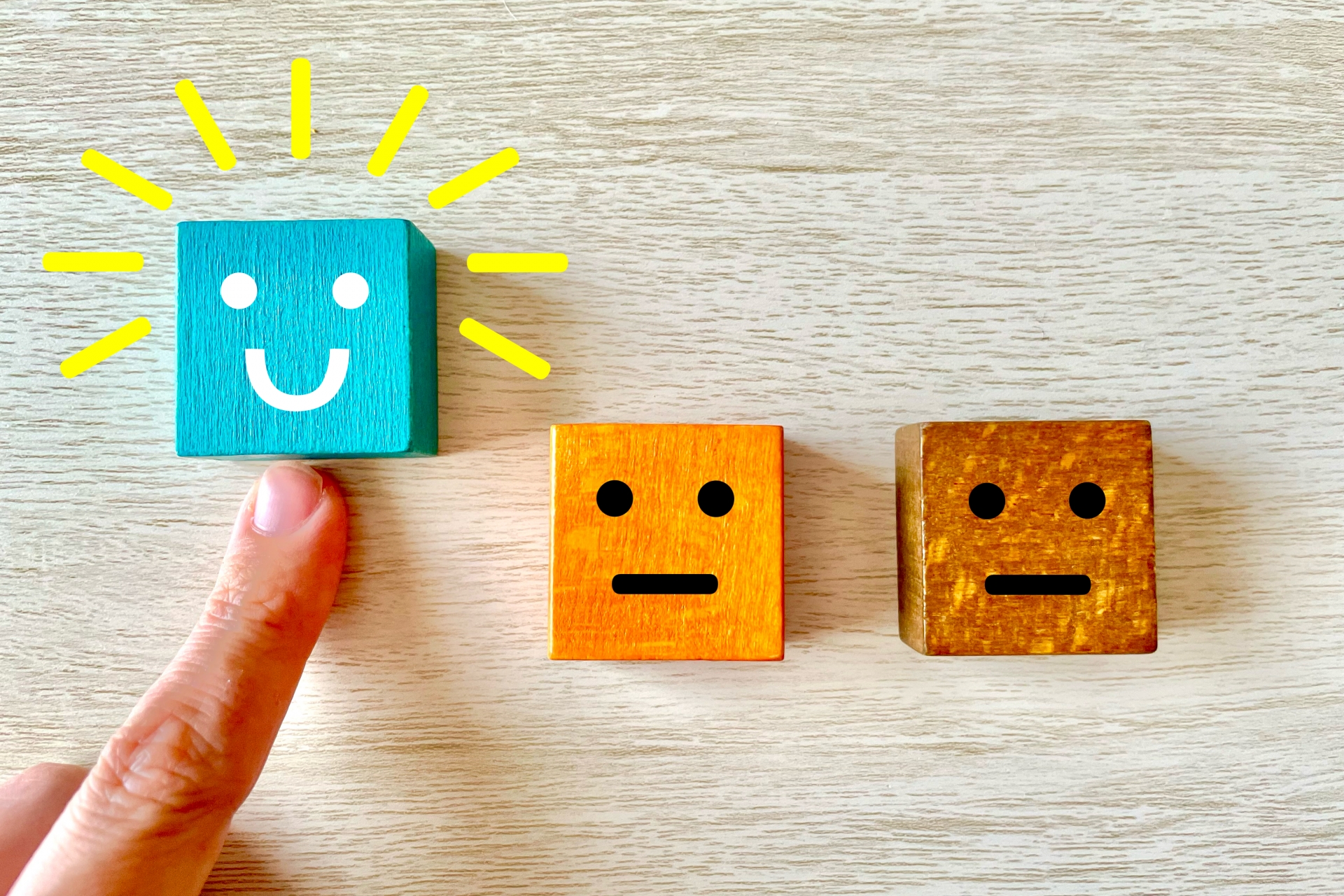
単機能・ハイブリッド・ポータブルの特徴と選び分け
太陽光発電に蓄電池を後付けする際、まず理解すべきは蓄電池のタイプによる違いです。
後付けに適した蓄電池は、大きく分けて単機能型、ハイブリッド型、ポータブル型の3種類があり、それぞれ特徴が大きく異なります。
**単機能型(蓄電池専用型)**は、蓄電池の機能のみを持つタイプです。
既設の太陽光発電システムはそのまま残し、蓄電池とその専用パワーコンディショナーを追加設置します。
つまり、太陽光用のパワーコンディショナーと、蓄電池用のパワーコンディショナーの2台が並存する構成になります。
単機能型の最大のメリットは、既設の太陽光発電システムに手を加えずに済むことです。
太陽光のパワーコンディショナーを交換する必要がないため、FIT認定への影響が最小限で、設置済みの保証もそのまま継続できます。
また、工事が比較的シンプルで、設置期間も短く済む(通常1~2日)という利点があります。
デメリットは、パワーコンディショナーが2台になるため、変換ロスが増えることです。
太陽光発電→太陽光用パワコン→蓄電池→蓄電池用パワコン→家庭という経路をたどるため、各段階でエネルギーロスが発生し、総合効率が低下します。
また、設置スペースも2台分必要になり、狭小住宅では設置場所の確保が課題となる場合があります。
|
単機能型の特徴 |
内容 |
評価 |
|
既設太陽光への影響 |
ほぼなし、そのまま使用可能 |
◎ |
|
パワコン台数 |
2台(太陽光用+蓄電池用) |
△ |
|
変換効率 |
やや低い(ロスが多い) |
△ |
|
初期費用 |
比較的安価 |
○ |
|
工事の複雑さ |
シンプル |
◎ |
|
設置スペース |
2台分必要 |
△ |
ハイブリッド型は、太陽光発電と蓄電池を一つのパワーコンディショナーで統合制御するタイプです。
後付けする場合は、既設の太陽光用パワーコンディショナーを撤去し、ハイブリッド型パワーコンディショナーに交換する必要があります。
ハイブリッド型の最大のメリットは、変換効率が高いことです。
太陽光発電の直流電力を、交流に変換せずにそのまま蓄電池に充電できるため、変換ロスが最小限に抑えられます。
総合的なシステム効率は、単機能型より5~10%程度高いとされています。
また、パワーコンディショナーが1台で済むため、設置スペースがコンパクトになり、メンテナンスも一元管理できます。
デメリットは、既設パワーコンディショナーの交換費用が追加でかかることです。
パワコン本体と交換工事費で、20万円~30万円程度の追加コストが発生します。
また、パワコンを交換すると、FIT認定の変更届出が必要になり、手続きが煩雑になります。
さらに、既設の太陽光パネルが古い場合、新しいハイブリッドパワコンと互換性がない可能性もあります。
|
ハイブリッド型の特徴 |
内容 |
評価 |
|
既設太陽光への影響 |
パワコン交換が必要 |
△ |
|
パワコン台数 |
1台(統合制御) |
◎ |
|
変換効率 |
高い(ロスが少ない) |
◎ |
|
初期費用 |
高い(パワコン交換費含む) |
△ |
|
工事の複雑さ |
やや複雑 |
△ |
|
設置スペース |
コンパクト |
◎ |
ポータブル型は、持ち運び可能な小型蓄電池です。
工事不要で、コンセントに差すだけで使える手軽さが特徴です。
容量は通常0.5kWh~3kWh程度と小さく、停電時の緊急用電源やアウトドア用途に適しています。
ポータブル型のメリットは、工事不要で即日使用開始できること、初期費用が安い(5万円~20万円程度)こと、引っ越しの際も持っていけることです。
デメリットは、容量が小さすぎて家全体の電力をまかなえないこと、太陽光発電との連携機能が限定的なこと、長期的な経済効果は薄いことです。
本格的な蓄電池システムというよりは、補助的なバックアップ電源として位置づけられます。
後付けでどのタイプを選ぶべきかの判断基準をまとめます。
単機能型を選ぶべきケース:
- 既設太陽光のパワコンが新しい(5年以内)
- FIT認定に影響を与えたくない
- 初期費用を抑えたい
- 工事を簡単に済ませたい
- 設置スペースに余裕がある
ハイブリッド型を選ぶべきケース:
- 既設太陽光のパワコンが古い(10年前後)
- 変換効率を最大化したい
- 将来的なメンテナンスを一元化したい
- 設置スペースが限られている
- パワコン交換費用を許容できる
ポータブル型を選ぶべきケース:
- 本格的な蓄電池は不要
- 停電時の最低限のバックアップがあれば十分
- 初期費用を極力抑えたい
- 賃貸住宅で工事ができない
- 将来の引っ越しを予定している
後付けの場合、最も一般的な選択肢は単機能型です。
既設システムへの影響が少なく、コストと効果のバランスが取れているためです。
ただし、パワコンの更新時期と重なる場合は、ハイブリッド型も有力な選択肢となります。
既設太陽光との適合性(パワコン構成・変換ロス・設置スペース)
蓄電池を後付けする際に最も重要なのが、既設の太陽光発電システムとの適合性です。
単に蓄電池を買って設置すれば良いわけではなく、既存設備との相性や連携方法を慎重に検討する必要があります。
まず、既設パワーコンディショナーの仕様確認が必須です。
太陽光発電のパワコンには、メーカー、型番、出力容量、設置年などの情報があり、これらが蓄電池と互換性があるかをチェックする必要があります。
特に、10年以上前の古いパワコンの場合、現在の蓄電池との通信プロトコルが対応していない可能性があります。
この場合、単機能型の蓄電池であっても、太陽光との連携が制限されることがあります。
例えば、太陽光の余剰電力を自動的に蓄電池に充電する機能が使えず、手動で充電タイミングを設定しなければならないといった不便が生じます。
パワコンの出力容量とのバランスも重要です。
太陽光パネルの発電容量が5kWで、パワコンの定格出力が4.5kWの場合、蓄電池への充電可能量も最大4.5kWに制限されます。
もし10kWhの大容量蓄電池を設置しても、充電に時間がかかり、日中の数時間では満充電にならない可能性があります。
逆に、蓄電池の出力が大きすぎると、パワコンの容量を超えてしまい、システムが停止するリスクもあります。
したがって、太陽光の発電容量、パワコンの出力、蓄電池の容量・出力のバランスを取ることが重要です。
|
設備 |
容量・出力 |
バランスの考え方 |
|
太陽光パネル |
5kW |
発電の上限 |
|
太陽光パワコン |
4.5kW |
実際の出力上限 |
|
蓄電池容量 |
8~10kWh |
パワコン出力で2~3時間で満充電可能 |
|
蓄電池出力 |
3~5kW |
家庭の電力需要に対応 |
変換ロスの理解も後付けには重要です。
単機能型で後付けする場合、電力の流れは以下のようになります。
太陽光パネル(直流)→太陽光パワコン(交流に変換)→家庭内消費 or 蓄電池
蓄電池(直流)→蓄電池パワコン(交流に変換)→家庭内消費
各変換段階で5~10%程度のエネルギーロスが発生するため、太陽光で発電した10kWhの電力のうち、実際に蓄電池から取り出せるのは8~8.5kWh程度になります。
一方、ハイブリッド型では、太陽光の直流電力を直接蓄電池に充電できるため、変換ロスが少なく、9~9.5kWh程度を取り出せます。
この差は、年間で見ると数百kWh、電気代に換算して数千円~1万円以上の差になる可能性があります。
設置スペースの確保も後付けの課題です。
単機能型の場合、蓄電池本体(幅60~100cm、奥行30~60cm、高さ100~150cm程度)と、蓄電池用パワコン(幅40~60cm、奥行20~30cm、高さ50~70cm程度)の両方を設置するスペースが必要です。
既に太陽光のパワコンが設置されている場所の近くに、追加で約1畳分のスペースを確保しなければなりません。
屋外設置の場合、直射日光を避け、風通しが良く、メンテナンスしやすい場所という条件を満たす必要があります。
狭小住宅や、外壁沿いのスペースが限られている場合、設置場所の確保が最大のハードルになることもあります。
配線の引き回しも考慮が必要です。
蓄電池は、分電盤、既設の太陽光パワコン、蓄電池用パワコンの間を配線で接続する必要があります。
これらの機器が離れた場所にある場合、長い配線が必要になり、工事費用が増加します。
また、外壁に配線を這わせる場合、美観を損なう可能性もあります。
既設太陽光との適合性を確認するチェックリストをまとめます。
- 既設パワコンのメーカー・型番・設置年を確認する
- 蓄電池メーカーの互換性リストで対応機種か確認する
- 太陽光の発電容量と蓄電池の容量・出力のバランスを確認する
- 設置スペース(蓄電池本体+パワコン)を確保できるか確認する
- 分電盤からの距離と配線ルートを確認する
- 施工業者に現地調査を依頼し、適合性を判定してもらう
後付けの場合、事前の互換性確認を怠ると、購入後に「設置できない」「期待した性能が出ない」といったトラブルにつながります。
必ず専門業者に相談し、現地調査と互換性チェックを行ってから契約することが重要です。
いくらかかる?相場・同時導入比較・補助金で総コストを最小化

後付け価格相場と同時導入との費用・施工・補助金の違い
蓄電池を後付けする際に最も気になるのが、「いくらかかるのか」という費用面でしょう。
後付けの費用相場と、太陽光と蓄電池を同時設置した場合との違いを詳しく見ていきます。
**後付けの費用相場(単機能型・10kWhの場合)**は、以下のような内訳になります。
- 蓄電池本体:120万円~160万円
- 蓄電池用パワーコンディショナー:(本体価格に含まれる場合が多い)
- 設置工事費:25万円~40万円
- 電気工事費:15万円~25万円
- 既設太陽光との連系工事費:5万円~15万円
- 合計:180万円~220万円
同時設置の場合と比較すると、後付けの方が20万円~40万円程度高くなる傾向があります。
|
導入方法 |
費用目安(10kWh) |
差額 |
理由 |
|
太陽光と同時設置 |
150~180万円 |
– |
工事を一度で済ませられる |
|
後付け(単機能型) |
180~220万円 |
+20~40万円 |
連系工事費が追加、工事が2回 |
|
後付け(ハイブリッド型) |
220~280万円 |
+50~100万円 |
パワコン交換費が追加 |
後付けが高くなる理由は、主に以下の3点です。
理由1:連系工事の複雑さ
既設の太陽光システムと蓄電池を連携させるための配線工事が追加で必要になります。
分電盤の改修、配線の引き直し、制御装置の追加など、同時設置ではかからない作業が発生します。
理由2:工事の非効率性
同時設置であれば、足場設置、配線工事、電気工事を一度に行えますが、後付けでは既に完成したシステムに手を加えるため、工事の手間が増加します。
また、既設設備を傷つけないよう慎重に作業する必要があり、工期も長くなりがちです。
理由3:部材の追加
既設システムとの接続に必要な特殊な部材(接続箱、保護装置、通信ケーブルなど)が追加で必要になります。
ハイブリッド型で後付けする場合は、さらに費用が増加します。
既設パワコンの撤去費(3万円~5万円)、新規ハイブリッドパワコンの購入費(15万円~25万円)、交換工事費(5万円~10万円)が追加され、単機能型より30万円~60万円程度高くなります。
施工面での違いも理解しておきましょう。
同時設置の場合、太陽光パネル設置と蓄電池設置を同じ業者が一貫して行うため、責任の所在が明確です。
後付けの場合、太陽光は別の業者が設置済みであるため、万が一トラブルが発生した際に、太陽光側の問題か蓄電池側の問題か切り分けが難しいことがあります。
また、既設太陽光の保証内容によっては、後付けの蓄電池設置により保証が無効になるリスクもあります。
事前に、既設太陽光の施工業者またはメーカーに、蓄電池後付けが保証に影響しないか確認することが重要です。
補助金の違いも重要なポイントです。
国の蓄電池補助金(DR補助金)は、太陽光の有無に関わらず蓄電池単体で申請可能です。
したがって、後付けでも同時設置でも、受けられる補助金額に大きな差はありません。
ただし、一部の自治体補助金では、太陽光と蓄電池の同時設置を条件としている場合があります。
この場合、後付けではその自治体補助金が受けられない可能性があるため、事前確認が必要です。
逆に、卒FIT向けの特別な補助金を設けている自治体もあります。
例えば、東京都では卒FIT世帯が蓄電池を後付けする場合、通常より上乗せした補助金を受けられる制度があります(年度により変動)。
後付けのコストを抑えるポイントをまとめます。
- 複数業者(最低3社)から相見積もりを取る
- 単機能型で十分な場合は、ハイブリッド型を避ける
- パワコンの更新時期と重なるなら、ハイブリッド型も検討
- 国と自治体の補助金を必ず確認し、併用する
- 卒FIT向け特別補助金の有無を調べる
- 既設太陽光の保証への影響を事前確認する
後付けは同時設置より高額になりがちですが、補助金を最大限活用し、適切な方式を選ぶことで、総コストを抑えることが可能です。
補助金・DR・自治体活用+一括見積・ローンで初期負担を圧縮
蓄電池後付けの初期費用を抑えるための具体的な方法とテクニックを詳しく解説します。
**国の補助金(DR補助金)**は、後付けでも利用可能です。
2025年度のDR補助金は、1kWhあたり4万円~7万円、上限60万円~80万円程度が見込まれます。
10kWhの蓄電池であれば、40万円~70万円の補助が受けられる計算です。
ただし、DR補助金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- SII(環境共創イニシアチブ)登録製品であること
- DR事業者との契約(5~10年間)を結ぶこと
- 電力需給逼迫時に遠隔制御による放電に協力すること
- 工事着工前に申請すること
DR契約により、電力需給が逼迫した際に蓄電池が遠隔制御されて放電することがありますが、日常生活への影響は最小限で、協力の対価として補助金が受けられます。
自治体補助金は、地域によって大きく異なります。
東京都、神奈川県、埼玉県、大阪府などの主要都市部では、10万円~50万円規模の補助を行っています。
|
自治体例 |
補助金額の目安 |
特徴 |
|
東京都 |
30~50万円 |
卒FIT向け上乗せあり |
|
神奈川県 |
15~30万円 |
太陽光併設が条件 |
|
埼玉県 |
10~20万円 |
市町村補助との併用可 |
|
大阪府 |
10~25万円 |
早期締切の傾向 |
自治体補助金の注意点は、予算枠が小さく、先着順で締め切られることです。
年度初め(4~5月)に公募が始まり、早ければ夏頃には予算消化で終了してしまうこともあります。
また、市区町村レベルでも独自補助金を設けている場合があり、都道府県補助金と市区町村補助金を併用できるケースもあります。
例えば、東京都の補助金40万円+世田谷区の補助金10万円=合計50万円といった具合です。
補助金を最大限活用するステップをまとめます。
- 自分の自治体の補助金情報を検索する(「○○市 蓄電池 補助金」で検索)
- 国の補助金(DR補助金)の公募時期を確認する(通常4~5月頃)
- 併用可能かどうかを確認する(多くは併用可)
- 申請書類を早めに準備する
- 公募開始と同時に申請する(先着順の場合)
一括見積サービスの活用も、コスト削減に有効です。
複数の施工業者に一度に見積もり依頼ができるサービスを利用することで、価格競争により相場より安い見積もりを引き出せる可能性があります。
一括見積のメリットは以下の通りです。
- 1回の入力で複数業者(3~5社)に見積もり依頼できる
- 業者間の競争により価格が下がりやすい
- 悪質業者を排除した優良業者のみが登録されている
- 見積もり比較が容易
ただし、最安値だけで選ぶのは危険です。
工事品質、保証内容、アフターサポート、施工実績なども総合的に判断しましょう。
ソーラーローンや蓄電池ローンの活用も、初期負担を軽減する手段です。
多くの金融機関や信販会社が、蓄電池専用の低金利ローンを提供しています。
金利は通常1~3%程度で、返済期間は5年~15年が一般的です。
例えば、180万円を金利2%、10年返済で借りた場合、月々の返済額は約1.6万円となります。
蓄電池による電気代削減効果が月1万円程度あれば、実質的な負担は月6,000円程度に抑えられます。
ローン活用のポイントは以下の通りです。
- 複数の金融機関の金利を比較する
- 繰上げ返済手数料の有無を確認する
- 返済シミュレーションを作成し、無理のない返済計画を立てる
- 蓄電池による削減効果とローン返済額のバランスを検証する
**PPAモデル(初期費用ゼロ)**も後付けで利用可能な場合があります。
PPA事業者が蓄電池を無償設置し、利用者は月額料金を支払って電力を使用する仕組みです。
契約期間(10~15年)終了後は、設備が無償または格安で譲渡されます。
PPAモデルのメリットは、初期費用ゼロで導入できること、メンテナンスはPPA事業者が負担することです。
デメリットは、月額料金の長期支払い、契約期間中の解約制限、補助金はPPA事業者が受け取ることです。
初期負担を最小化する戦略をまとめます。
- 国の補助金(40~70万円)を必ず申請する
- 自治体補助金(10~50万円)を併用する
- 一括見積で複数業者を比較し、適正価格を見極める
- ソーラーローンで初期費用を分割する
- PPAモデルも選択肢として検討する
- 型落ちモデルや在庫処分品で本体価格を下げる
これらの方法を組み合わせることで、実質的な初期負担を半分以下に圧縮することも可能です。
失敗しない導入手順―最適タイミング・申請・工事の注意点

卒FIT/パワコン更新期など導入好機の見極め方
蓄電池を後付けするタイミングは、経済効果を最大化する上で極めて重要です。
適切なタイミングで導入することで、投資回収期間を大幅に短縮できます。
最も有力な導入タイミングは「卒FIT」を迎えた時です。
FIT制度では、太陽光発電の余剰電力を10年間、高単価(当初は40円/kWh前後)で買い取ってもらえました。
しかし、10年後の卒FIT以降は、買取単価が7円~10円/kWh程度まで急落します。
一方、電力会社から購入する電気の単価は25円~35円/kWhです。
つまり、卒FIT後は、余剰電力を売るよりも、蓄電池に蓄えて自家消費する方が圧倒的に有利なのです。
具体的な経済効果を計算してみましょう。
【卒FIT前(FIT期間中)】
- 余剰電力:年間2,000kWh
- 売電収入:2,000kWh × 40円 = 8万円
- 蓄電池導入のメリット:ほぼなし(売った方が得)
【卒FIT後(蓄電池なし)】
- 余剰電力:年間2,000kWh
- 売電収入:2,000kWh × 8円 = 1.6万円
- 年間収入減:8万円 → 1.6万円(6.4万円の減少)
【卒FIT後(蓄電池あり)】
- 余剰電力を蓄電池に充電して自家消費
- 電気代削減効果:2,000kWh × 30円 = 6万円
- さらに、深夜電力の活用で+3万円程度
- 年間メリット:約9万円
このように、卒FIT後に蓄電池を導入すれば、年間9万円程度の経済効果が期待でき、投資回収期間は15年~18年程度となります。
卒FITを迎えるのは、2009年~2012年頃に太陽光を設置した家庭で、2019年以降順次該当しています。
|
太陽光設置年 |
FIT開始年 |
卒FIT年 |
状況 |
|
2009年 |
2009年 |
2019年 |
すでに卒FIT |
|
2012年 |
2012年 |
2022年 |
すでに卒FIT |
|
2015年 |
2015年 |
2025年 |
今年卒FIT |
|
2018年 |
2018年 |
2028年 |
3年後に卒FIT |
自分の家がいつ卒FITを迎えるかは、FIT認定通知書や電力会社からの通知で確認できます。
卒FITの半年~1年前から準備を始めるのが理想的です。
**次に有力なタイミングは「パワーコンディショナーの更新時期」**です。
太陽光のパワコンの寿命は、通常10年~15年とされています。
保証期間も10年が一般的なため、10年目以降に故障するリスクが高まります。
もしパワコンが故障して交換が必要になった場合、どうせ交換するなら、ハイブリッド型パワコンに交換して同時に蓄電池も導入するという選択が合理的です。
単純にパワコンだけを交換すると15万円~25万円かかりますが、ハイブリッド型パワコン+蓄電池のセットで導入すれば、パワコン交換費を蓄電池導入の一部として組み込めるため、総コストが抑えられます。
パワコンの状態を確認するには、定期点検や発電量のモニタリングが有効です。
発電量が以前より明らかに減少している場合、パワコンの劣化が原因の可能性があります。
「電気料金の大幅値上げ」も導入の好機です。
2022年以降、電気料金は大幅に上昇しており、今後もさらなる値上げの可能性があります。
電気料金が上がれば上がるほど、蓄電池による削減効果も大きくなるため、投資回収期間が短縮されます。
逆に、避けるべきタイミングもあります。
FIT期間中で売電単価が高い場合は、蓄電池導入のメリットが薄いです。
売電単価が30円/kWh以上ある場合は、余剰電力は売電した方が得なため、卒FITまで待つのが賢明です。
また、引っ越しの予定がある場合も、導入は慎重に検討すべきです。
蓄電池は基本的に持っていけない設備であり、引っ越し先に移設するには多額の費用がかかります。
導入の好機を見極めるチェックリストをまとめます。
- 卒FITをすでに迎えたか、近い将来(1~2年以内)迎えるか
- 太陽光パワコンが10年前後経過し、更新時期に近いか
- 電気料金が高騰しており、今後も上昇が見込まれるか
- 最低でも10年以上は現在の住居に住む予定があるか
- 災害リスクが高まっており、停電対策の必要性を感じているか
これらの条件に多く当てはまるほど、蓄電池後付けの適切なタイミングといえます。
FIT変更認定・事前変更届出と配線図/区分計量のポイント
蓄電池を後付けする際、FIT制度との関係で必要な手続きがあります。
これを怠ると、FIT認定が取り消されるリスクもあるため、正確に理解しておくことが重要です。
まず、FIT制度と蓄電池の関係を整理しましょう。
FIT制度は、太陽光発電の余剰電力を高価格で買い取る制度ですが、蓄電池を経由した電力は原則としてFIT売電の対象外とされています。
これは、「太陽光で発電した電力を直接売電する場合はFIT適用だが、一度蓄電池に充電してから放電した電力は、太陽光由来と証明できないため対象外」という考え方です。
しかし、適切な手続きと設備構成を取れば、蓄電池を後付けしてもFIT売電を継続できます。
単機能型の蓄電池を後付けする場合、多くのケースでFIT認定の変更届出は不要です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 太陽光発電から蓄電池への充電は、余剰電力のみを使用する
- 太陽光からの直接売電ルートは維持する
- 蓄電池は系統からの充電(買電による充電)も可能とする
この構成であれば、太陽光の余剰電力は従来通り売電でき、蓄電池は補助的な役割として扱われます。
ハイブリッド型パワコンに交換する場合は、FIT認定の変更認定申請が必要です。
パワコンの交換は、FIT認定上「設備の変更」に該当するため、事前に変更認定を受けなければなりません。
変更認定の手続きは以下の流れです。
- 再生可能エネルギー電子申請システムにログイン
- 変更認定申請書を作成・提出
- 必要書類(パワコン仕様書、配線図など)を添付
- 審査(通常1~2か月)
- 変更認定通知の受領
- 工事実施
- 変更届出書の提出
変更認定を受けずに工事を実施すると、FIT認定が取り消され、以降の売電ができなくなるリスクがあります。
配線図と区分計量が重要なポイントです。
FIT売電を継続する場合、太陽光発電から直接売電される電力と、蓄電池を経由する電力を明確に区分する必要があります。
これを「区分計量」といい、適切な配線構成と計測装置が求められます。
|
配線構成 |
FIT売電 |
注意点 |
|
太陽光→直接売電 |
◎ 継続可能 |
従来通りの売電ルート |
|
太陽光→蓄電池→家庭 |
△ FIT対象外 |
自家消費として活用 |
|
太陽光→家庭(余剰→蓄電池) |
◎ 継続可能 |
余剰分のみ蓄電 |
|
系統→蓄電池→家庭 |
– FIT無関係 |
深夜電力活用 |
具体的な配線図は、施工業者が作成しますが、以下の点を確認しておきましょう。
- 太陽光からの直接売電ルートが維持されているか
- 蓄電池への充電は余剰電力のみか、系統からの充電も可能か
- 売電メーターと蓄電池の間に適切な計量装置があるか
- 配線図がFIT変更認定の要件を満たしているか
事前変更届出が必要なケースもあります。
FIT認定を受けた設備に、以下のような変更を加える場合、変更認定ではなく事前変更届出で済む場合があります。
- 軽微な配線変更
- 計量装置の追加
- 制御装置の追加
事前変更届出は、変更認定より手続きが簡単で、審査期間も短い(通常2~3週間)です。
自分のケースが「変更認定」が必要か「事前変更届出」で済むかは、再生可能エネルギー電子申請システムのガイドラインや、施工業者に確認しましょう。
FIT関連手続きで失敗しないためのポイントをまとめます。
- 単機能型なら変更届出は不要な場合が多い
- ハイブリッド型への変更は必ず変更認定を受ける
- 工事前に手続きを完了させる(工事後は認められない)
- 配線図は施工業者に作成してもらい、FIT要件を満たすか確認
- 不明点は、再エネ電子申請システムのサポートや施工業者に相談
- FIT認定取り消しリスクを避けるため、手続きを軽視しない
FIT制度との関係は複雑ですが、適切な手続きを踏めば、蓄電池を後付けしても売電を継続できます。
施工業者と密に連携し、確実に手続きを進めることが重要です。
まとめ
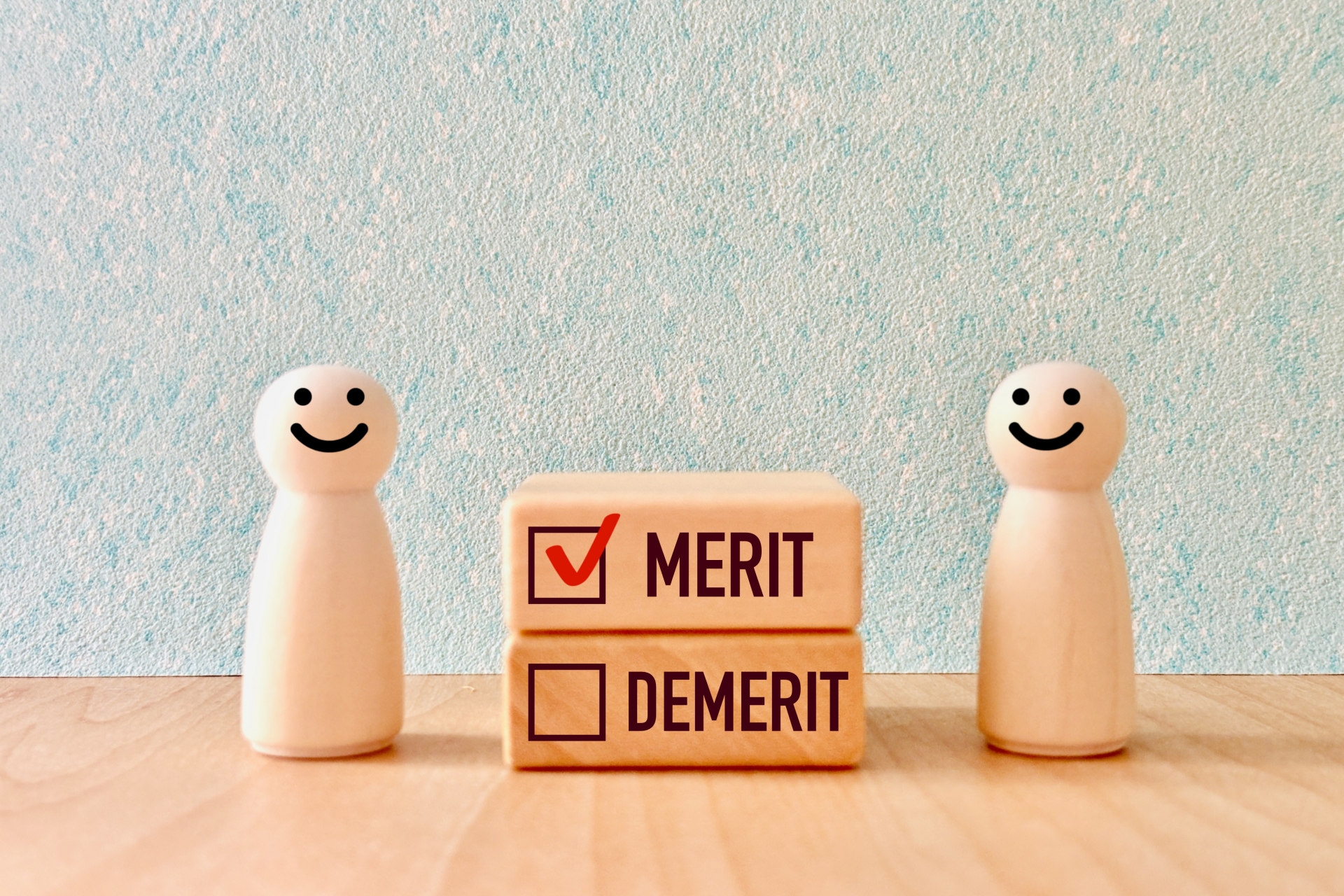
太陽光発電に蓄電池を後付けすることは、技術的にも経済的にも十分可能であり、特に卒FIT家庭では大きなメリットがあります。
後付けの方式には、単機能型、ハイブリッド型、ポータブル型の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
最も一般的なのは単機能型で、既設太陽光への影響が少なく、コストと効果のバランスが取れています。
ハイブリッド型は変換効率が高いですが、パワコン交換費用が追加でかかるため、パワコンの更新時期と重なる場合に適しています。
既設太陽光との適合性確認は極めて重要で、パワコンの型番、出力容量、設置スペース、配線ルートなどを事前にチェックする必要があります。
互換性がない場合、期待した性能が出ない、追加費用が発生するといったトラブルにつながります。
費用面では、後付けは同時設置より20万円~40万円程度高くなる傾向がありますが、補助金を活用すれば実質負担を大幅に削減できます。
国の補助金(40~70万円)と自治体補助金(10~50万円)を併用すれば、合計100万円近い補助を受けられるケースもあります。
導入の好機は、卒FITを迎えた時、パワコンの更新時期、電気料金の高騰時です。
特に卒FIT後は、売電収入が激減するため、蓄電池による自家消費が圧倒的に有利になります。
FIT制度との関係では、単機能型なら変更届出不要、ハイブリッド型なら変更認定が必要です。
適切な手続きを踏まなければ、FIT認定取り消しのリスクがあるため、必ず事前に確認しましょう。
蓄電池の後付けは、同時設置より複雑で費用も高めですが、適切なタイミングと方法を選べば、十分な経済効果と停電対策のメリットが得られます。
まずは、複数の施工業者に現地調査を依頼し、既設太陽光との適合性を確認することから始めてください。
そして、補助金情報を徹底的に調べ、申請タイミングを逃さないようにしましょう。
本記事が、あなたの蓄電池後付けの成功の一助となれば幸いです。
適切な準備と手順を踏めば、後付けでも満足度の高いエネルギーシステムを構築できます。
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。






