お役立ちコラム 2025.09.24
国の太陽光補助金2025年版|対象・申請・併用可否早見表
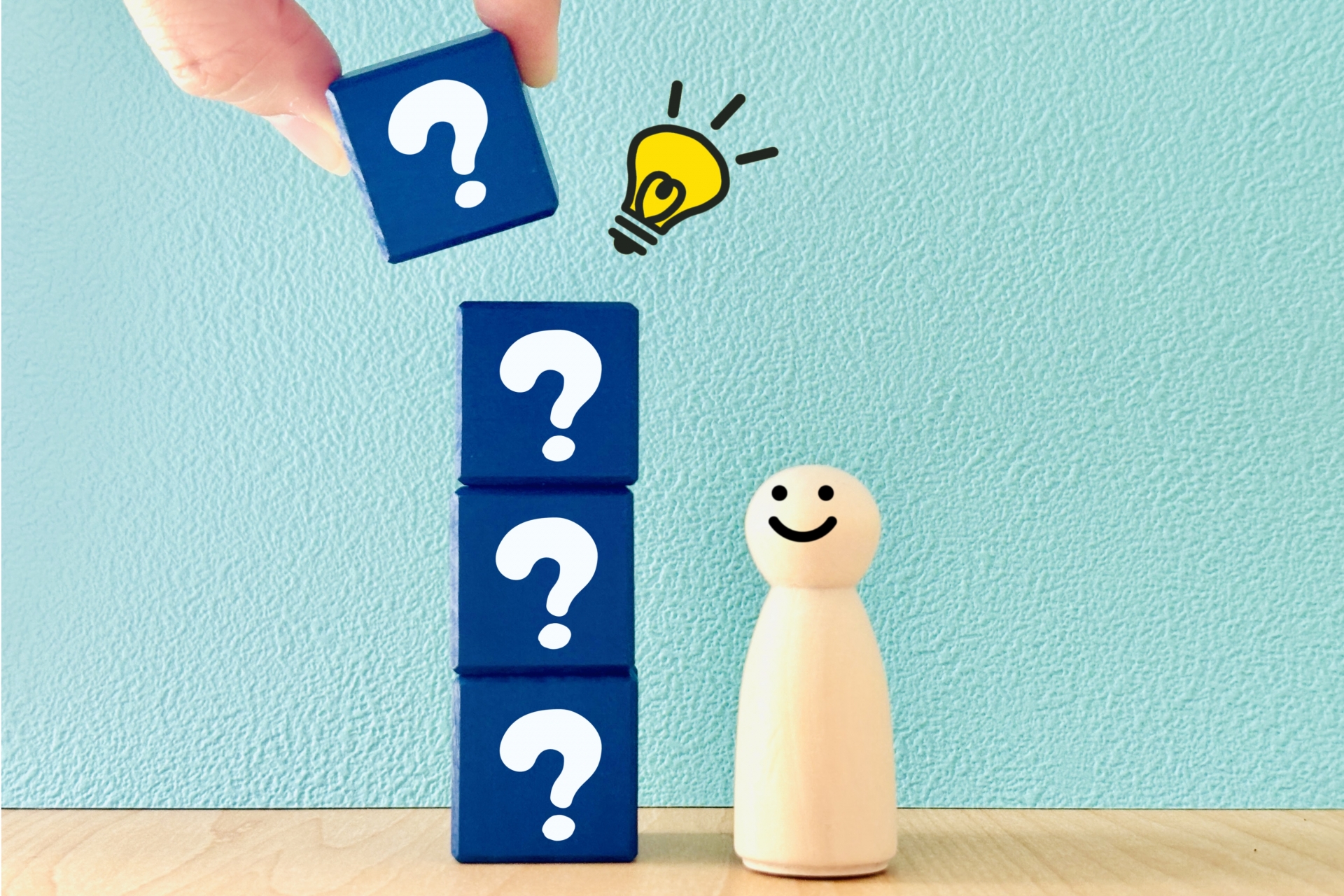
2025年に入り、脱炭素社会の実現に向けた国の取り組みがさらに加速しています。
太陽光発電システムの導入を検討されている方にとって、補助金制度の活用は設置費用を大幅に軽減できる重要な要素です。
しかし、「国の補助金はどれを使えばいいのか分からない」「申請方法が複雑で手続きが不安」「自治体の補助金と併用できるの?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
実際に、2025年度の国による太陽光発電関連の補助金制度は複数存在し、それぞれに異なる対象条件や申請要件が設定されています。
特に注意すべきは、太陽光発電システム単体では対象外となる制度が多く、住宅の省エネ性能向上と組み合わせた総合的なアプローチが求められる点です。
本記事では、2025年に利用可能な国の主要な補助金スキームを詳しく解説し、申請フローから必須要件、さらには自治体制度との併用可否まで、実務的な観点から分かりやすくお伝えします。
補助金を最大限活用して、お得に太陽光発電システムを導入するための完全ガイドとしてご活用ください。
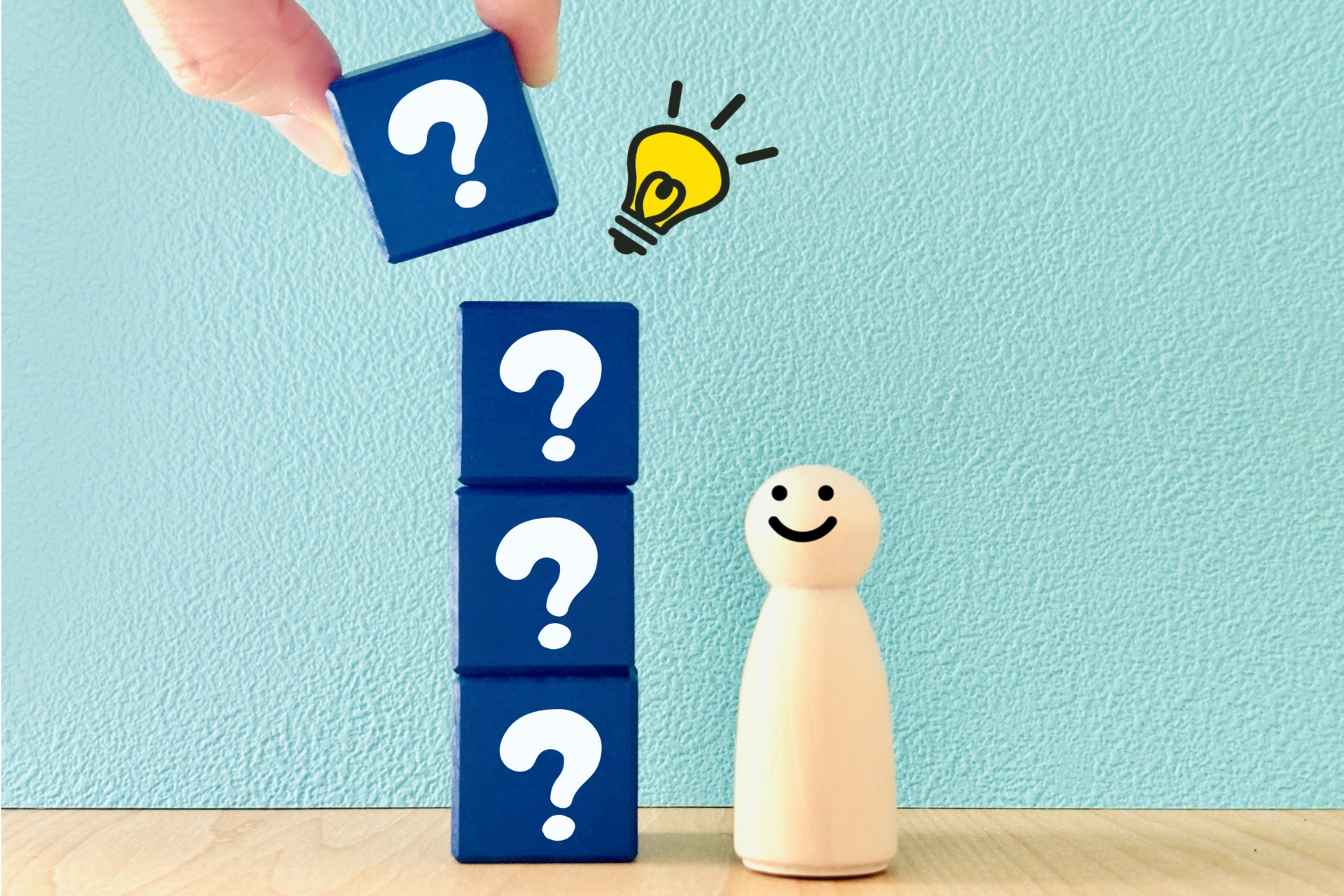
目次
2025年に使える”国の”主要スキーム

2025年度において、太陽光発電システムの導入に活用できる国の補助金制度は、主に2つの大きな枠組みに分けられます。
これらの制度は、単なる太陽光パネルの設置支援ではなく、住宅全体の省エネ性能向上を目的とした包括的な支援策として位置づけられています。
制度設計の背景には、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、新築・既築を問わず住宅の省エネ化を強力に推進したいという国の政策意図があります。
そのため、各制度では太陽光発電システムの設置と併せて、断熱性能の向上や高効率設備の導入が要件として設定されているのが特徴です。
ここでは、実際に2025年度予算が確保され、申請受付が開始されている主要制度について、対象範囲から補助額の上限まで詳しく解説していきます。
子育てグリーン住宅支援事業の対象と上限(新築・リフォーム)
子育てグリーン住宅支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、省エネ性能の高い住宅の取得やリフォームを支援する制度です。
2025年度版では、太陽光発電システムの設置が高い評価ポイントとして位置づけられ、補助額の大幅な増額が期待できる仕組みとなっています。
対象となる世帯は明確に定義されており、子育て世帯は18歳未満の子どもがいる世帯、若者夫婦世帯は夫婦いずれかが39歳以下の世帯が該当します。
新築住宅の場合、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)レベルの省エネ性能が基本要件となり、太陽光発電システムの設置により年間の一次エネルギー消費量を正味ゼロ以下にすることが求められます。
|
対象分類 |
基本補助額 |
太陽光加算 |
上限額 |
|
新築ZEH |
100万円 |
+20万円 |
120万円 |
|
新築ZEH+ |
100万円 |
+30万円 |
130万円 |
|
リフォーム |
60万円 |
+15万円 |
75万円 |
リフォームの場合は、既存住宅の省エネ改修と太陽光発電システムの新設・増設が対象となります。
重要なポイントは、単なる太陽光パネルの追加設置だけでは補助対象とならず、窓の断熱改修や給湯器の高効率化など、住宅全体の省エネ性能向上工事との組み合わせが必須となることです。
申請に当たっては、登録事業者による工事が前提条件となり、施主が個人で手続きを行うことはできません。
また、先着順での受付となるため、予算枠の消化状況を定期的に確認し、早めの申請準備が成功のカギとなります。
工事着手前の申請が必須条件となっているため、計画段階から登録事業者と密に連携を取り、必要書類の準備を進めることが重要です。
ZEH補助金の種別と加算(ZEH/ZEH+/蓄電池・V2H)
ZEH補助金制度は、経済産業省と環境省が連携して実施する、住宅の省エネルギー化を推進する代表的な支援策です。
2025年度版では、太陽光発電システムの設置を前提とした3つのカテゴリーに分類され、それぞれ異なる補助額と要件が設定されています。
基本のZEHでは、太陽光発電システムにより年間の一次エネルギー消費量を正味ゼロにすることが目標となり、**ZEH+**ではさらに25%以上の省エネルギーを実現することが求められます。
最も高い補助額が設定されているZEH+Rは、レジリエンス機能の強化が特徴で、停電時にも住宅機能を維持できる太陽光発電システムと蓄電池の組み合わせが評価されます。
|
ZEH種別 |
基本補助額 |
蓄電池加算 |
V2H加算 |
合計上限 |
|
ZEH |
55万円 |
+20万円 |
+75万円 |
150万円 |
|
ZEH+ |
100万円 |
+20万円 |
+75万円 |
195万円 |
|
ZEH+R |
125万円 |
+20万円 |
+75万円 |
220万円 |
蓄電池の加算措置は、太陽光発電システムで生成した電力を効率的に活用するためのインセンティブとして設計されています。
対象となる蓄電池は、蓄電容量4kWh以上で、太陽光発電システムと連携制御が可能な機器に限定されます。
V2H(Vehicle to Home)システムの加算は、電気自動車を家庭用蓄電池として活用する先進的な取り組みを評価するものです。
V2H対応の充放電設備と電気自動車の購入・リースが条件となり、災害時の電力確保という観点からも注目を集めています。
申請のタイミングは年4回の公募制となっており、各回の締切日までに必要書類を整備する必要があります。
省エネ基準への適合性を示すBELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)評価書の取得が必須となるため、設計段階からの準備が重要です。
注意すべきは、ZEH補助金と子育てグリーン住宅支援事業の併用は不可という点で、どちらがより有利かを慎重に検討する必要があります。
申請フローと必須要件の押さえどころ

太陽光発電システムに関する国の補助金申請は、一般的な設備投資の補助金とは大きく異なる特徴を持っています。
最も重要なポイントは、住宅所有者が直接申請することはできないという点で、必ず登録事業者が申請主体となる仕組みが採用されています。
この制度設計は、施工品質の確保と申請書類の正確性向上を目的としており、素人による不適切な工事や書類不備を防ぐ効果があります。
しかし同時に、事業者選びが成否を分ける重要な要素となるため、登録事業者の選定には十分な検討が必要です。
また、多くの制度で先着順の受付方式が採用されているため、予算枠の残り状況を常に把握し、タイミングを逸しないよう注意深く進める必要があります。
登録事業者が申請主体・先着方式への備え(書類不備ゼロ)
登録事業者制度は、補助金申請の品質向上と手続きの効率化を目的として導入されています。
対象となる事業者は、国の指定する研修を受講し、一定の技術基準と施工実績を満たした業者のみが登録される仕組みとなっています。
住宅所有者にとって重要なのは、登録事業者の選定基準を明確に設定し、補助金申請の実績と成功率を事前に確認することです。
優良な登録事業者は、過去の申請実績を具体的な数値で示すことができ、書類不備による申請遅延のリスクを最小限に抑える体制を整えています。
書類不備を防ぐためのチェックポイントは以下の通りです:
- 建築確認済証の有効性と記載内容の正確性
- 省エネ計算書の基準適合性と計算根拠の明確化
- 工事契約書における補助金の取り扱い条項の明記
- 登記事項証明書の最新性と申請者情報との整合性
- 住民票における世帯構成の正確な反映
先着順での受付という制約の中で、確実に補助金を獲得するためには、申請開始日の朝一番での提出を目指す必要があります。
そのためには、事前に全ての書類を完璧に準備し、申請システムの操作方法についても登録事業者と十分に打ち合わせを行うことが重要です。
特に人気の高い制度では、申請開始から数時間で予算枠が埋まるケースも報告されているため、油断は禁物です。
事業者との連携体制を構築する際は、申請日当日の連絡方法や、万一のシステムトラブル時の対応策についても事前に取り決めておくことをお勧めします。
太陽光単体不可の理由と”住宅性能”要件(断熱・一次エネ)
国の補助金制度において太陽光発電システム単体での申請が認められない理由は、政策目標の違いにあります。
従来の再生可能エネルギー普及策とは異なり、現在の制度は住宅全体の省エネルギー化を通じた脱炭素社会の実現を主眼としています。
単純な発電量の増加ではなく、エネルギー消費量の削減と効率的なエネルギー利用の両立を目指すアプローチが採用されているのです。
そのため、太陽光発電システムの設置と併せて、建物の断熱性能向上や高効率設備の導入が必須要件として設定されています。
具体的な住宅性能要件は以下の通りです:
|
性能分野 |
要求基準 |
確認方法 |
評価指標 |
|
断熱性能 |
UA値0.6以下 |
省エネ計算書 |
外皮平均熱貫流率 |
|
一次エネ |
△20%以上 |
BELS評価 |
基準一次エネ比 |
|
気密性能 |
C値2.0以下 |
気密測定 |
相当隙間面積 |
**UA値(外皮平均熱貫流率)**は、建物の断熱性能を示す指標で、値が小さいほど熱が逃げにくい高性能な住宅であることを意味します。
0.6以下という基準は、従来の省エネ基準より約30%厳しい水準で、高性能な断熱材や樹脂サッシなどの採用が必要となります。
一次エネルギー消費量の削減率20%以上という要件は、照明のLED化、高効率給湯器の導入、換気システムの改善など、設備面での省エネ対策も求められることを意味します。
これらの住宅性能要件を満たすことで、太陽光発電システムの効果が最大化され、真の意味でのゼロエネルギー住宅の実現が可能となります。
**BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)**による第三者評価は、これらの性能要件を客観的に証明する重要な書類です。
設計段階から省エネ性能の検討を行い、太陽光発電システムの容量設定と住宅性能のバランスを最適化することが、補助金獲得の成功につながります。
併用可否・地域別の実務ポイント

国の補助金制度と自治体制度の併用は、太陽光発電システムの導入費用を大幅に軽減できる重要な戦略です。
しかし、併用の可否は各制度の規定と自治体の条例により複雑に決定されるため、事前の詳細な調査が不可欠となります。
一般的な併用原則として、国の制度間での重複受給は禁止されていますが、国と自治体の制度間では併用が認められるケースが多数存在します。
ただし、自治体側の規定により国の補助金受給者を対象外とする場合もあるため、申請前の確認作業が成功の鍵を握ります。
特に注意すべきは、申請順序による制約で、先に申請した制度の結果によって後の申請の可否が左右される場合があることです。
国×自治体の併用原則と例外(自治体側規定の確認が必須)
国と自治体の補助金併用における基本原則は、「財源が異なる制度間では併用可能」というものです。
国の制度は主に一般会計予算や特別会計予算を財源としているのに対し、自治体制度は地方税や交付金を財源としているため、原理的には併用に問題はありません。
しかし実際には、自治体独自の制限規定により併用が制限されるケースが数多く存在するのが現実です。
併用可否の判定で最も重要なのは、自治体制度の実施要綱における他制度との重複に関する記載を詳細に確認することです。
|
併用パターン |
併用可否 |
注意点 |
確認事項 |
|
国ZEH+市太陽光 |
多くが可能 |
申請順序 |
市の要綱確認 |
|
国グリーン+県省エネ |
制限あり |
対象重複 |
県の制限規定 |
|
国制度+市制度+県制度 |
複雑 |
三重チェック |
全制度要綱 |
申請順序による制約は、特に注意を要するポイントです。
一部の自治体制度では「他の補助金の決定通知書」の提出を求める場合があり、国の制度を先に申請・決定させてから自治体制度に申請する必要があります。
逆に、国の制度申請時に自治体制度の決定済み証明を求める場合もあるため、事前の調整が重要となります。
例外的な制限規定として最も多いのは、「補助対象経費の重複禁止」です。
同一の太陽光パネルや工事費用に対して複数の補助金を適用することは禁止されていますが、異なる工事項目や異なる設備に対してであれば併用が認められるケースがあります。
実務的なアプローチとしては、計画段階で全ての利用可能制度をリストアップし、併用可能な組み合わせを事前にシミュレーションすることが効果的です。
自治体の担当窓口への事前相談は必須の手続きで、口頭での確認だけでなく、書面での回答を求めることでトラブルを防ぐことができます。
終了・競争率の高い補助の動向と東京都の厚い制度の活用
2025年度の補助金制度では、予算規模の縮小や応募者数の増加により、競争率の上昇が顕著となっています。
特にZEH補助金制度では、前年度比で応募倍率が1.5倍に上昇し、第1回公募で予算の70%が消化される事態が発生しました。
このような激戦状況の中で、確実な補助金獲得を目指すためには、複数制度への同時準備と戦略的な申請スケジュールの構築が不可欠です。
終了が決定している制度も存在し、2024年度で終了となった「住宅省エネ2024キャンペーン」の後継制度は、内容を大幅に縮小して継続されています。
東京都は全国でも最も手厚い太陽光発電支援制度を展開している自治体の一つです:
|
東京都制度 |
補助額 |
対象 |
特徴 |
|
太陽光発電設備 |
12万円/kW |
新築・既築 |
上限36万円 |
|
蓄電池システム |
15万円/kWh |
併設条件 |
上限120万円 |
|
V2H充放電設備 |
50万円/台 |
EV必須 |
工事費込み |
東京都の制度の特徴は、国制度との併用を明確に許可している点と、申請手続きの簡素化が図られている点です。
都独自の登録事業者制度により、事業者による代理申請が可能で、住宅所有者の手続き負担が大幅に軽減されています。
さらに、災害時の自立電源確保という観点から、蓄電池やV2Hシステムへの支援が特に手厚く設定されています。
地域特性を活かした制度設計として、東京都では集合住宅向けの特別枠も設けられており、マンションでの太陽光発電導入も積極的に支援されています。
申請戦略として重要なのは、国制度の申請結果を待たずに東京都制度への申請準備を並行して進めることです。
東京都制度は比較的予算に余裕があるため、国制度で採択されなかった場合のバックアップとしても機能します。
他の自治体においても、東京都ほどではないものの独自の支援制度を展開している地域が増加しており、居住地域の制度調査は必須の作業となっています。
まとめ
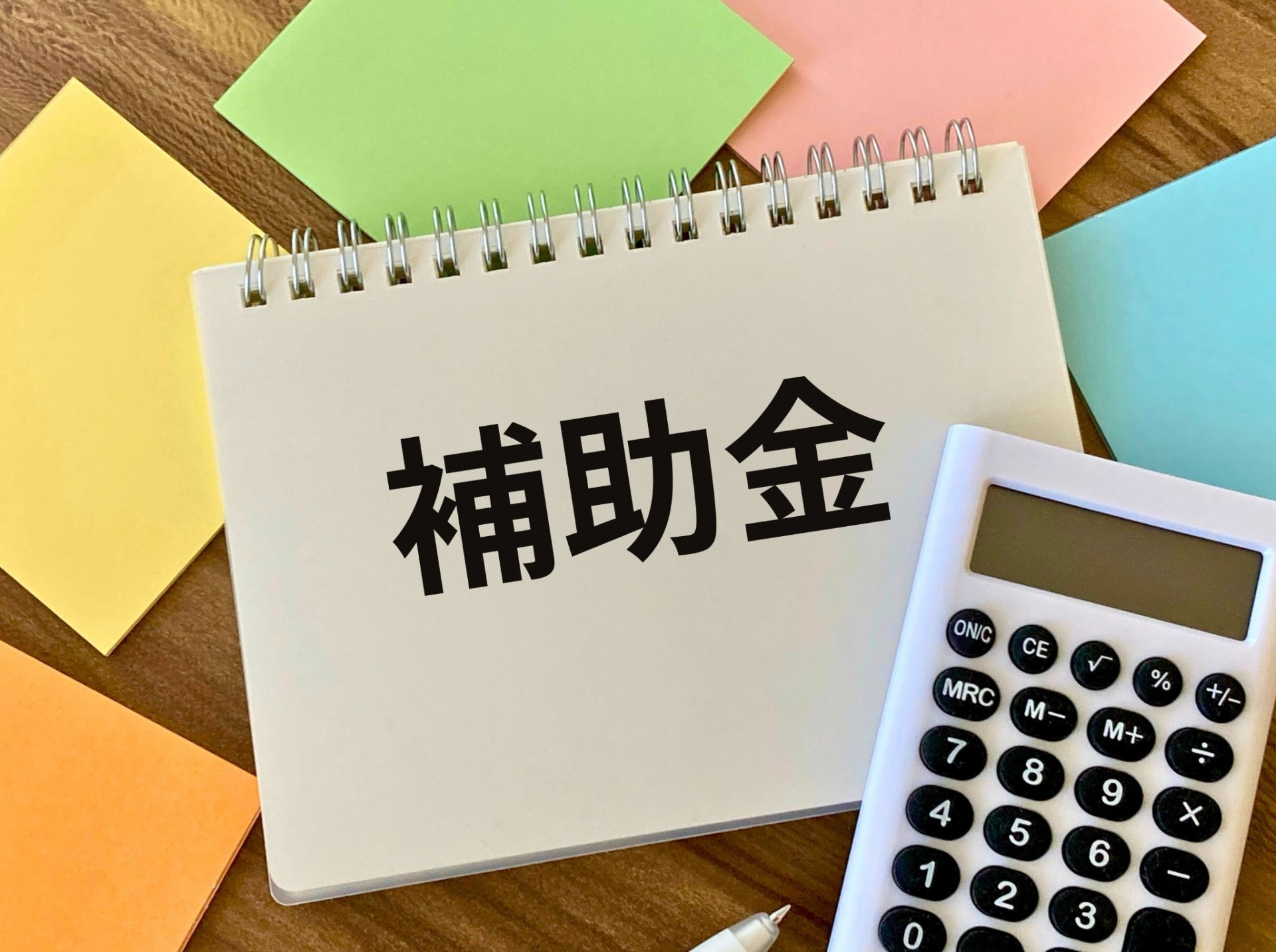
2025年度の国による太陽光補助金制度は、従来の設備普及支援から住宅全体の省エネ化を目指す包括的な政策へと大きく転換しています。
子育てグリーン住宅支援事業とZEH補助金制度という2つの主要スキームでは、太陽光発電システムの設置を前提としながらも、断熱性能や一次エネルギー消費量といった住宅性能要件をクリアすることが必須となりました。
申請に当たっては、登録事業者による代理申請が原則となり、住宅所有者は信頼できる事業者の選定と綿密な連携が成功の鍵となります。
先着順の受付方式という制約の中で、書類不備ゼロでの確実な申請を実現するためには、早期からの準備と戦略的なスケジュール管理が不可欠です。
併用可否の判断においては、国の制度間での重複は禁止されているものの、自治体制度との併用は多くの場合で可能となっています。
ただし、自治体側の独自規定により制限される場合もあるため、事前の詳細な調査と窓口での確認作業が重要となります。
特に東京都をはじめとする先進自治体では、国制度を上回る手厚い支援策が展開されており、地域特性を活かした戦略的な活用が大きなメリットをもたらします。
2025年の太陽光補助金活用を成功させるためには、単なる制度の理解にとどまらず、登録事業者との連携体制構築、申請スケジュールの最適化、併用戦略の検討という3つの要素を総合的に取り組むことが求められます。
脱炭素社会の実現に向けた国の政策転換は、住宅所有者にとって省エネ投資の絶好の機会でもあります。
本記事でご紹介した情報を参考に、最適な補助金活用戦略を構築し、快適で経済的な太陽光発電ライフを実現していただければと思います。
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。






