お役立ちコラム 2025.02.28
愛知県の太陽光発電・蓄電池補助金|2025年度最新版【市町村別・申請期限・併用可否まで解説】

愛知県で太陽光発電システムや家庭用蓄電池の導入を検討している方にとって、補助金の活用は初期費用を大幅に抑える最重要ポイントです。
しかし「自分の住む市町村でいくら補助金がもらえるのか」「県と市町村の補助金は併用できるのか」「国の補助金との組み合わせは可能なのか」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、愛知県の補助金制度は**「市町村が主体となり、県が協調補助する」という独特の仕組み**を採用しています。
このため、お住まいの市町村によって補助金額や申請条件が大きく異なり、さらに申請タイミングを誤ると一切受給できないケースも存在します。
本記事では、2025年度(令和7年度)の愛知県全54市町村の最新補助金情報を網羅的に整理し、名古屋市をはじめとする主要都市の詳細から、併用可能な国の補助金制度、申請時の注意点、施工業者の選び方まで、実務レベルで必要な情報をすべて解説します。
「まず結論」のセクションでは、郵便番号から30秒で自分の対象補助金を特定できるフローも用意していますので、お急ぎの方はそちらから確認してください。
太陽光発電と蓄電池の導入で、電気代削減と災害対策を同時に実現しましょう。
目次
まず結論|愛知の補助金は「市町村+県協調」が基本。自分の対象を30秒で確認

しくみの全体像(県・市町村・国の関係)
愛知県における太陽光発電・蓄電池の補助金制度は、3つの主体が連携して交付される重層構造になっています。
この仕組みを正確に理解しておかないと、「申請先を間違える」「併用できる補助金を見逃す」といった失敗につながります。
■ 市町村補助金(基礎となる補助)
愛知県内の各市町村は、独自の予算と条件で住宅用太陽光発電・蓄電池・V2H(Vehicle to Home)の補助金を用意しています。
補助金額は市町村ごとに大きく異なり、たとえば名古屋市では太陽光が最大29.97万円、蓄電池が**1.5万円/kWh(容量上限なし)**である一方、知立市では蓄電池単体で40万円という高額補助を実施しています。
申請先は必ずお住まいの市町村の担当窓口となり、個人が直接県に申請することはありません。
■ 愛知県協調補助(市町村補助への上乗せ)
愛知県は「住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金」という名称で、市町村の補助事業に対して協調補助を行っています。
つまり、市町村が補助金を交付する際に、県も追加で補助額を上乗せする形です。
ただし、この県補助金は市町村を通じて交付されるため、申請者が別途県に申請する必要はなく、市町村への申請が完了すれば自動的に県補助分も含めて交付されます。
重要なのは、市町村が補助事業を実施していない場合や、予算が終了した場合、県の協調補助も受けられないという点です。
■ 国の補助金(併用可能なケースが多い)
国は経済産業省や環境省を中心に、太陽光発電・蓄電池・V2Hに対する複数の補助金制度を運営しています。
代表的なものとして、蓄電池の「DR(デマンドレスポンス)補助金」や「住宅省エネキャンペーン」、V2Hの「CEV補助金」などがあります。
これらの国補助金は、市町村・県の補助金と併用できる場合が多いものの、申請順序や条件に制約があるため、事前に確認が必須です。
■ 3者の関係を図解すると
|
補助主体 |
申請先 |
特徴 |
|
市町村 |
市町村窓口 |
独自予算・独自条件。補助額は市町村で大きく異なる |
|
愛知県 |
市町村経由で自動交付 |
市町村補助への協調補助。個人から県への直接申請は不要 |
|
国 |
執行団体または事業者経由 |
市町村・県と併用可能なケース多数。申請順序に注意 |
このように、愛知県の補助金は「市町村が主、県が従」という構造であり、まずは自分の市町村がどのような補助を実施しているかを確認することが第一歩となります。
該当フロー(郵便番号→市町村→対象設備→併用可否)
ここでは、30秒で自分が受けられる補助金を特定するフローを示します。
以下の手順に従って、該当する補助金を確認してください。
■ ステップ1:郵便番号から市町村を特定
まず、お住まいの郵便番号を確認し、どの市町村に該当するかを特定します。
愛知県は54の市町村から構成されており、隣接する市でも補助金額が大きく異なるため、正確な市町村名の確認が必要です。
郵便番号から市町村を調べるには、日本郵便の公式サイトや自治体の公式ページを利用してください。
■ ステップ2:市町村の補助金制度を確認
市町村が特定できたら、その市町村が2025年度に太陽光発電・蓄電池・V2Hの補助金を実施しているかを確認します。
本記事の「市町村別|主要エリアの補助金早見表」セクションに、愛知県内全市町村の補助金額・申請期間・条件を一覧にしていますので、そちらを参照してください。
市町村によっては、特定の設備(太陽光のみ、蓄電池のみ等)に限定している場合もあるため、自分が導入したい設備が対象かどうかを必ず確認しましょう。
■ ステップ3:対象設備と補助額を確認
市町村の補助金制度が確認できたら、次に以下の項目をチェックします。
- 太陽光発電の補助金額(kW単価または一律額)
- 蓄電池の補助金額(kWh単価または一律額)
- V2Hの補助金額(一律額または設置費用の割合)
- 同時導入が条件かどうか(太陽光+蓄電池、HEMSなど)
- 上限額(kW・kWh数による上限、総額上限)
たとえば名古屋市の場合、太陽光発電は築年数によって単価が変動し、蓄電池は1.5万円/kWh(容量上限なし)、V2Hは一律5万円となっています。
また、多くの市町村では「太陽光+HEMS+蓄電池の同時導入」を条件としているため、単体導入では対象外となるケースもあります。
■ ステップ4:国の補助金との併用可否を確認
市町村・県の補助金が確認できたら、最後に国の補助金と併用できるかをチェックします。
蓄電池の場合、DR補助金や住宅省エネキャンペーンとの併用が可能なケースが多く、V2HはCEV補助金との併用が一般的です。
ただし、国の補助金は申請受付期間や予算枠が限られているため、市町村補助の申請タイミングと調整する必要があります。
詳細は「国の補助金との併用ガイド」セクションで解説します。
■ フローチャート(テキスト版)
【スタート】
↓
郵便番号を確認
↓
市町村を特定(例:名古屋市、豊田市、岡崎市…)
↓
市町村の補助金制度を確認(本記事の早見表を参照)
↓
対象設備を確認(太陽光 / 蓄電池 / V2H)
↓
補助額・条件を確認(同時導入、HEMSなど)
↓
国の補助金との併用可否を確認(DR / CEV / 省エネ支援)
↓
【該当補助金が確定】
このフローに従えば、わずか30秒で自分が受けられる補助金の全体像を把握できます。
申請で失敗しない3原則(交付決定前着工NG/中古・リースの可否/予算満了リスク)
補助金申請において、知らないと一切受給できない致命的なルールが3つ存在します。
これらを事前に理解しておかないと、工事を進めてから「対象外だった」「申請が間に合わなかった」といった事態に陥ります。
■ 原則1:交付決定前の着工は絶対NG
愛知県内のすべての市町村補助金において、交付決定通知を受け取る前に工事に着手すると、補助金は一切交付されません。
これは「交付決定前着工」と呼ばれ、補助金制度の根幹を成すルールです。
たとえば、見積を取って契約を結び、すぐに工事を開始してしまうと、その後申請しても「着工済み」として不交付となります。
交付決定までの期間は市町村によって異なりますが、通常は申請から2週間〜1か月程度かかります。
そのため、施工業者との契約時には「交付決定後に着工する」旨を明確に確認し、スケジュールを組む必要があります。
よくある失敗例:
- 業者に「早く工事したい」と急かされて着工してしまった
- 申請書類の準備中に「先に資材を発注しておこう」と進めてしまった
- 交付決定通知が届く前に、パネルの設置を開始してしまった
これらはすべて補助金が受けられない原因となります。
■ 原則2:中古機器・リース契約は原則対象外
ほぼすべての市町村補助金において、補助対象となるのは未使用品(新品)のみです。
中古の太陽光パネルや蓄電池を設置した場合、補助金は交付されません。
また、リース契約による導入も対象外となる市町村が大半です。
リース契約では、設備の所有権がリース会社に残るため、「自己所有の住宅に設備を設置する」という補助要件を満たさないためです。
ただし、PPA(電力購入契約)モデルは市町村によって扱いが異なるため、事前に確認が必要です。
PPAは「第三者が屋根に太陽光を設置し、発電した電力を住民が購入する」形式であり、一部の市町村では補助対象としているケースもあります。
よくある失敗例:
- ネットオークションで安く購入した中古パネルを設置した
- リース契約で初期費用を抑えようとした
- PPAモデルが対象かどうか確認せずに契約した
これらのケースでは、補助金を受けられない可能性が高いため、必ず事前に市町村窓口または施工業者に確認してください。
■ 原則3:予算満了リスクを常に意識する
市町村補助金は、年度ごとに予算枠が設定されており、予算に達した時点で受付終了となります。
愛知県内の多くの市町村では「先着順」で受け付けており、人気の高い市町村では年度の前半で予算が尽きるケースもあります。
たとえば、刈谷市や安城市など補助額が高額な市町村では、4月の受付開始から数か月で予算満了となることがあります。
そのため、導入を検討している方は、年度初めの早い時期に申請を完了させることが重要です。
また、予算満了後に「翌年度まで待つ」という選択肢もありますが、翌年度の補助金制度が継続されるかどうかは保証されないため、注意が必要です。
予算満了リスクを回避するポイント:
- 4月〜5月の早期に申請を完了させる
- 申請前に市町村窓口で予算残額を確認する
- 施工業者に「申請代行」をスムーズに行ってもらえるか確認する
これらの3原則を守ることで、補助金を確実に受給できる確率が大幅に高まります。
【名古屋市】太陽光・蓄電池・V2Hの補助金(2025年度)

太陽光|築年数別の単価・上限・同時導入条件
名古屋市は愛知県内で最も人口が多く、補助金制度も充実しています。
2025年度の名古屋市における太陽光発電の補助金は、住宅の築年数によって単価が変動する独自の仕組みを採用しており、築年数が古いほど高額な補助を受けられる設計となっています。
■ 築年数別の補助金額(名古屋市)
|
住宅の種類 |
補助金額(単価) |
上限 |
|
築10年超の戸建住宅 |
3万円/kW |
上限9.99kW(最大29.97万円) |
|
築10年以下の戸建住宅 |
2万円/kW |
上限9.99kW(最大19.98万円) |
|
新築の戸建住宅 |
1万円/kW |
上限9.99kW(最大9.99万円) |
|
集合住宅 |
2.5万円/kW |
上限9.99kW(最大約24.98万円) |
この仕組みにより、既存住宅のリフォームとして太陽光を導入する場合、より手厚い補助を受けられます。
たとえば、築15年の戸建住宅に5kWの太陽光発電システムを設置する場合、3万円/kW × 5kW = 15万円の補助金が交付されます。
一方、新築住宅の場合は1万円/kW × 5kW = 5万円となり、既築住宅との差は10万円にもなります。
■ 同時導入条件
名古屋市の太陽光発電補助を受けるためには、HEMSと、(蓄電池 または V2H)のいずれかを太陽光と一体的に同時導入することが条件です。
これは、発電した電力を効率的に管理・蓄積し、自家消費率を高めるための施策です。
HEMSとは、家庭内の電力使用状況をリアルタイムで把握し、最適な電力配分を行うシステムで、太陽光発電との連携により電気代削減効果が高まります。
蓄電池は、昼間に発電した電力を蓄え、夜間や停電時に使用できるようにする設備です。
名古屋市で太陽光補助を受けるためのセット:
- 太陽光発電システム(上限6.5kWまたは9.99kW)
- HEMS(エネルギー管理システム)
- 蓄電池(容量8kWhまで補助対象)
この3点セットを同時に導入することで、太陽光+蓄電池+V2Hの補助金を最大限に活用できます。
■ 補助額の計算例
ケース1:築12年の戸建住宅に5kWの太陽光を設置
- 補助単価:3万円/kW
- 補助額:3万円 × 5kW = 15万円
ケース2:新築住宅に9.99kWの太陽光を設置
- 補助単価:1万円/kW
- 補助額:1万円 × 9.99kW = 9.99万円(上限到達)
ケース3:集合住宅に8kWの太陽光を設置
- 補助単価:2.5万円/kW
- 補助額:2.5万円 × 8kW = 20万円
このように、築年数と住宅種別によって補助額が大きく変動するため、自分の住宅がどのカテゴリに該当するかを正確に把握することが重要です。
蓄電池|単価・上限・対象機器の要件
名古屋市における家庭用蓄電池の補助金は、容量に応じた補助額が設定されており、太陽光発電との同時導入または既設太陽光への後付けのいずれも対象となります。
■ 蓄電池の補助金額(名古屋市)
|
項目 |
補助額 |
|
補助単価 |
1.5万円/kWh |
|
上限容量 |
制限なし |
|
最大補助額 |
容量に応じて算出(例:8kWhなら12万円、10kWhなら15万円) |
たとえば、容量6kWhの蓄電池を導入した場合、1.5万円 × 6kWh = 9万円の補助金が交付されます。
容量が8kWhを超える蓄電池でも、全量が補助対象です(例:10kWh → 15万円)。
■ 対象機器の要件
名古屋市で補助対象となる蓄電池は、以下の要件を満たす必要があります。
- 既設の太陽光発電設備に接続可能であること 蓄電池単体での導入も可能ですが、太陽光発電システムと接続することが前提となっています。
- 未使用品であること 中古の蓄電池やリース契約による導入は対象外です。
- 電気事業者との契約を締結していること 太陽光発電で発電した電力を売電する契約(FIT契約など)、または蓄電池を活用した電力プランに加入していることが求められます。
- 一定の性能基準を満たしていること 国の補助金制度で認定されている機器であれば、名古屋市の補助対象となるケースが多いです。
具体的には、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が公開している「定置用リチウムイオン蓄電システム登録製品一覧」に掲載されている機器が該当します。
■ 補助額の計算例
ケース1:容量5kWhの蓄電池を導入
- 補助額:1.5万円 × 5kWh = 7.5万円
ケース2:容量10kWhの蓄電池を導入
- 補助額:1.5万円 × 10 = 15万円
ケース3:太陽光5kW+蓄電池6kWhを同時導入(築12年住宅)
- 太陽光:3万円 × 5kW = 15万円
- 蓄電池:1.5万円 × 6kWh = 9万円
- 合計:24万円
このように、太陽光と蓄電池を同時に導入することで、合計補助額が大幅に増加します。
V2H|補助額・対象条件(HEMS同時など)
V2H(Vehicle to Home)は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)のバッテリーを家庭用電源として活用するシステムです。
名古屋市では、V2Hの導入に対しても補助金を交付しています。
■ V2Hの補助金額(名古屋市)
|
項目 |
補助額 |
|
補助額 |
一律5万円 |
|
条件 |
太陽光発電システムと連系すること |
V2Hの補助を受けるためには、太陽光発電システムとHEMSを同時に導入することが条件となっています。
これにより、昼間に太陽光で発電した電力をEVに充電し、夜間や停電時に家庭で使用する「エネルギーの地産地消」が実現します。
■ 対象となるV2H機器
名古屋市で補助対象となるV2H機器は、国のCEV補助金制度で認定されている「V2H充放電設備」である必要があります。
一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が公開している「補助対象V2H充放電設備一覧」に掲載されている機器が該当します。
注意点:
- 普通充電設備や急速充電設備は対象外です。V2Hは「双方向充放電」が可能な設備である必要があります。
- 充電のみ可能な機器では補助対象となりません。
■ V2H導入のメリット
V2Hを導入することで、以下のようなメリットがあります。
- 停電時の非常用電源として活用 災害時や停電時に、EVのバッテリーを家庭用電源として使用できます。
たとえば、容量40kWhのEVであれば、一般家庭の1日分の電力をまかなうことが可能です。
- 電気代の削減 深夜電力の安い時間帯にEVを充電し、昼間に家庭で使用することで、電気代を削減できます。
- 太陽光発電との相乗効果 昼間に太陽光で発電した電力をEVに充電し、夜間に家庭で使用することで、自家消費率が大幅に向上します。
■ 補助額の計算例
ケース:太陽光5kW+蓄電池6kWh+V2Hを同時導入(築12年住宅)
- 太陽光:3万円 × 5kW = 15万円
- 蓄電池:1.5万円 × 6kWh = 9万円
- V2H:一律5万円
- 合計:29万円
このように、3つの設備を同時導入することで、最大29万円以上の補助金を受けることが可能です。
申請スケジュールと必要書類チェックリスト
名古屋市の補助金を確実に受給するためには、申請スケジュールと必要書類の準備が重要です。
ここでは、申請の流れと必要書類を具体的に解説します。
■ 申請期間(2025年度)
|
項目 |
期間 |
|
申請受付開始 |
2025年4月16日 |
|
申請受付終了 |
2026年2月13日 |
|
工事完了期限 |
2026年2月28日 |
名古屋市の補助金は、先着順で受け付けられ、予算に達した時点で終了となります。
そのため、できるだけ早い時期に申請を完了させることが重要です。
■ 申請の流れ(タイムライン)
ステップ1:事前準備(1〜2週間)
- 施工業者を選定し、見積を取得
- 設置する機器が補助対象かどうかを確認
- 必要書類を準備
ステップ2:交付申請(申請から2〜4週間で交付決定)
- 名古屋市の担当窓口に申請書類を提出
- 交付決定通知を受け取るまで待機
- この間は工事に着手しない
ステップ3:工事実施(交付決定後)
- 交付決定通知を受け取った後に工事を開始
- 工事完了後、設置写真や検査報告書を取得
ステップ4:実績報告(工事完了後2週間以内)
- 工事完了の実績報告書を提出
- 設置写真、領収書、検査報告書を添付
ステップ5:補助金の交付(実績報告後1〜2か月)
- 実績報告の審査が完了後、補助金が振り込まれる
■ 必要書類チェックリスト
以下の書類を事前に準備しておくと、申請がスムーズに進みます。
【交付申請時に必要な書類】
- 交付申請書(市の指定様式)
- 設置する機器のカタログまたは仕様書
- 設置場所の図面(配置図、立面図など)
- 見積書の写し
- 住民票の写し(申請者が居住していることを証明)
- 建物の登記事項証明書または固定資産税納税通知書の写し
- 電気事業者との契約書の写し(売電契約など)
- HEMSの設置を証明する書類
- 蓄電池またはV2Hの仕様書
【実績報告時に必要な書類】
- 実績報告書(市の指定様式)
- 設置完了後の写真(設備全体、銘板、シリアル番号など)
- 領収書または請求書の写し
- 検査報告書(電気工事の検査結果)
- 保証書の写し
■ よくある不備と対策
申請書類に不備があると、審査が遅れたり差し戻されたりします。
以下の点に注意してください。
- 設置写真が不鮮明 銘板やシリアル番号が読み取れない写真は再提出となります。
- 見積書に機器の型式が記載されていない 補助対象機器かどうかを確認できないため、詳細な型式を記載してもらいましょう。
- 図面が古い 既存住宅の場合、現在の状態と異なる図面では審査が通りません。
これらの書類を事前に準備し、施工業者と連携して申請を進めることで、スムーズに補助金を受け取ることができます。
愛知県の「協調補助」とは?—市町村補助に上乗せされるケース

対象設備(太陽光・HEMS・蓄電池・V2H・断熱等)の整理
愛知県が実施する「協調補助」は、市町村が住宅用地球温暖化対策設備の補助金を交付する際に、県が追加で補助額を上乗せする制度です。
この協調補助の対象となる設備は、国が推進する脱炭素社会の実現に寄与するものに限定されています。
■ 協調補助の対象設備一覧
|
設備名 |
概要 |
補助の考え方 |
|
太陽光発電施設 |
住宅用の太陽光発電システム(10kW未満) |
HEMSと蓄電池またはV2Hとの一体的導入が条件 |
|
HEMS |
家庭用エネルギー管理システム |
単体補助も可能(市町村による) |
|
蓄電池 |
定置用リチウムイオン蓄電システム |
単体補助も可能(市町村による) |
|
V2H |
電気自動車等充給電設備 |
充放電機能を持つ設備のみ対象 |
|
燃料電池 |
家庭用燃料電池システム(エネファームなど) |
単体補助も可能(市町村による) |
|
太陽熱利用システム |
自然循環型・強制循環型の太陽熱温水器 |
単体補助も可能(市町村による) |
|
高性能外皮等 |
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を満たす住宅 |
新築時のみ対象 |
|
断熱窓改修工事 |
既存住宅の窓を高性能な断熱窓に改修 |
リフォームのみ対象 |
これらの設備は、市町村が補助事業として実施している場合に限り、県の協調補助が適用されます。
■ 一体的導入とは?
愛知県の協調補助では、「一体的導入」という条件が設定されている設備があります。
これは、複数の設備を同時に導入することで、より高い補助額を受けられる仕組みです。
一体的導入の組み合わせ例:
- 太陽光発電+HEMS+蓄電池
- 太陽光発電+HEMS+V2H
- 太陽光発電+HEMS+高性能外皮等(ZEH)
- 太陽光発電+HEMS+断熱窓改修
たとえば、名古屋市では「太陽光発電の補助を受けるにはHEMSと蓄電池の同時導入」という条件がありますが、これが一体的導入の典型例です。
■ 単体補助が可能な設備
一方で、以下の設備は単体での導入でも補助対象となる市町村が多いです。
- HEMS(エネルギー管理システム)
- 蓄電池(既設太陽光への後付けも含む)
- V2H(充放電機能を持つ設備)
- 燃料電池(エネファーム)
- 太陽熱利用システム
ただし、市町村によっては「太陽光発電との同時導入を条件とする」場合もあるため、必ず事前に確認してください。
■ 対象外となる設備
以下の設備は、愛知県の協調補助の対象外です。
- オール電化設備(IHクッキングヒーター、エコキュート単体など)
- 太陽光発電の10kW以上の産業用システム
- 普通充電設備・急速充電設備(V2H機能がないもの)
これらの設備は、市町村独自の補助金がある場合を除き、県の協調補助は適用されません。
市町村の補助が無い/終了した場合の扱い
愛知県の協調補助は、市町村が補助事業を実施していることが前提条件です。
そのため、以下のケースでは県の協調補助を受けることができません。
■ ケース1:市町村が補助事業を実施していない
愛知県内の54市町村のうち、一部の町村では太陽光発電や蓄電池の補助金制度を設けていない場合があります。
このような市町村に居住している場合、県の協調補助も適用されません。
ただし、国の補助金(DR補助金やCEV補助金など)は市町村の制度とは独立しているため、国の補助金は申請可能です。
■ ケース2:市町村の補助予算が満了した
多くの市町村では、補助金は「先着順」で受け付けられ、予算に達した時点で終了します。
年度途中で予算が満了した場合、その後の申請は受け付けられず、県の協調補助も適用されません。
たとえば、刈谷市や安城市など補助額が高額な市町村では、年度前半で予算が尽きることがあります。
予算満了後の選択肢:
- 翌年度の補助金を待つ(ただし翌年度の制度継続は保証されない)
- 国の補助金のみを活用する
- 他の市町村に転居する(現実的ではないが)
■ ケース3:申請期間外に申請した
市町村ごとに申請期間が定められており、その期間外に申請しても受理されません。
たとえば、瀬戸市は「2025年6月2日〜6月20日」という非常に短い申請期間を設定しており、この期間を逃すと補助を受けられません。
対策:
- 年度初めに各市町村の申請期間を確認する
- 施工業者に「申請期間内に申請できるか」を事前確認する
■ 協調補助が受けられない場合の代替策
市町村または県の補助が受けられない場合でも、以下の制度を活用できる可能性があります。
- 国の補助金制度
- 蓄電池:DR補助金、住宅省エネキャンペーン
- V2H:CEV補助金
- 太陽光:ZEH補助金(新築時のみ)
- 固定資産税の減免 一部の市町村では、太陽光発電設備の設置に対して固定資産税の減免措置を実施しています。
- 金融機関のローン優遇 太陽光発電や蓄電池の導入に対して、低金利ローンを提供している金融機関もあります。
これらの代替策を組み合わせることで、補助金が受けられない場合でも初期費用の負担を軽減できます。
よくある誤解と注意点
愛知県の協調補助に関しては、制度の仕組みが複雑なため、誤解や勘違いが生じやすいポイントがあります。
ここでは、よくある誤解とその正しい理解を整理します。
■ 誤解1:「県に直接申請すれば県補助金がもらえる」
正しい理解: 愛知県の協調補助は、市町村を通じて自動的に交付されるため、個人が県に直接申請する必要はありません。
申請先はあくまで「お住まいの市町村」であり、市町村が県に代わって申請と交付を行います。
■ 誤解2:「市町村補助と県補助は別々に申請する」
正しい理解: 市町村に申請すれば、県の協調補助分も含めて一括で交付されます。
申請者が県と市町村に二重で申請する必要はありません。
■ 誤解3:「県の補助金があれば、市町村の補助がなくても大丈夫」
正しい理解: 県の協調補助は、市町村の補助事業が存在することが前提です。
市町村が補助を実施していない場合、県の協調補助も受けられません。
■ 誤解4:「補助金は工事前にもらえる」
正しい理解: 補助金は、工事完了後の実績報告を経て交付されます。
工事前に受け取れるわけではないため、初期費用は自己負担または施工業者のローンを利用する必要があります。
■ 注意点:申請内容の変更は原則不可
交付申請後に、設置する機器の型式や容量を変更する場合、再度申請が必要となるケースがあります。
また、変更が認められない場合もあるため、申請前に設置内容を確定させておくことが重要です。
■ 注意点:補助金の返還義務
以下のケースでは、交付された補助金の返還義務が発生します。
- 交付決定前に工事に着手していた
- 虚偽の申請を行っていた
- 補助対象外の機器を設置していた
- 工事完了後、一定期間内に設備を撤去または転売した
これらの注意点を理解し、正しく申請を進めることが重要です。
市町村別|主要エリアの補助金 “早見表”

西三河エリア(豊田・安城・刈谷・西尾 など)
西三河エリアは、愛知県の中央部に位置し、自動車産業を中心とした製造業が盛んな地域です。
このエリアの市町村は、比較的高額な補助金を設定していることが特徴です。
■ 西三河エリアの主要市町村補助金一覧
|
市町村名 |
太陽光発電 |
蓄電池 |
V2H |
申請期間 |
|
豊田市 |
一律21万円(蓄電池セット) |
1万円/kWh(上限15万円) |
1万円/kWh(上限15万円) |
2025/4/1〜予算満了 |
|
安城市 |
一律21万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/2/19 |
|
刈谷市 |
一律32万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
西尾市 |
設置価格×1/3(上限12万円) |
一律8万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
岡崎市 |
出力×7万円 または 補助対象経費×1/2(上限63万円) |
設置価格×20%(上限15万円) |
設置価格×20%(上限10万円) |
2025/4/1〜2025/12/26 |
|
碧南市 |
一律32万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
知立市 |
一律46万円(蓄電池セット) |
一律40万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
■ エリアの特徴と補助金のポイント
- 知立市は県内最高額の蓄電池補助 知立市は、蓄電池の補助額が一律40万円と、愛知県内で最も高額です。
太陽光+HEMS+蓄電池の同時導入であれば、合計46万円の補助を受けることができます。
- 刈谷市・碧南市も高額補助 刈谷市と碧南市は、太陽光+蓄電池の同時導入で一律32万円の補助を実施しており、西三河エリアの中でも手厚い支援が受けられます。
- 岡崎市は設置費用の割合で補助 岡崎市は、設置費用の一定割合を補助する方式を採用しており、高額な設備を導入するほど補助額が増加します。
- 申請期間に注意 刈谷市や知立市など人気の高い市では、年度前半で予算が満了することがあります。
早めの申請が重要です。
■ 西三河エリアで補助を最大化する方法
ケース:知立市で太陽光5kW+蓄電池8kWhを導入
- 市町村補助:46万円(太陽光+HEMS+蓄電池セット)
- 県協調補助:上乗せ分(市町村経由で自動交付)
- 国DR補助金:最大14万円(併用可能)
- 合計:約60万円以上の補助
このように、西三河エリアでは市町村・県・国の補助を組み合わせることで、初期費用の大部分をカバーできます。
尾張エリア(一宮・春日井・小牧・稲沢 など)
尾張エリアは、愛知県の北西部に位置し、名古屋市のベッドタウンとして発展している地域です。
このエリアの市町村も、太陽光発電と蓄電池の補助金を積極的に実施しています。
■ 尾張エリアの主要市町村補助金一覧
|
市町村名 |
太陽光発電 |
蓄電池 |
V2H |
申請期間 |
|
一宮市 |
1.8万円/kW(上限7.2万円) |
一律5万円 |
一律5万円 |
2025/5/1〜予算満了 |
|
春日井市 |
1.5万円/kW(上限6万円) |
一律6万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/2/27 |
|
小牧市 |
一律28万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/11〜2026/3/13 |
|
稲沢市 |
一律24万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
江南市 |
一律21.28万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
犬山市 |
一律20万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
岩倉市 |
設置価格×1/4(上限47万円) |
設置価格×1/4(上限40万円) |
設置価格×1/4(上限5万円) |
2025/4/1〜予算満了 |
■ エリアの特徴と補助金のポイント
- 小牧市は太陽光+蓄電池セットで高額補助 小牧市は、太陽光+HEMS+蓄電池の同時導入で一律28万円の補助を実施しており、尾張エリアの中でも高額です。
- 岩倉市は設置費用の1/4を補助 岩倉市は、設置費用の4分の1を補助する方式を採用しており、高額な設備ほど補助額が増加します。
- 一宮市・春日井市はkW単価方式 一宮市と春日井市は、太陽光発電の容量に応じたkW単価で補助額が決まります。
- 申請期間は市町村ごとに異なる 一宮市は5月1日からの受付開始、小牧市は4月11日からなど、申請開始日が市町村ごとに異なります。
■ 尾張エリアで補助を最大化する方法
ケース:小牧市で太陽光5kW+蓄電池8kWhを導入
- 市町村補助:28万円(太陽光+HEMS+蓄電池セット)
- 県協調補助:上乗せ分(市町村経由で自動交付)
- 国DR補助金:最大14万円(併用可能)
- 合計:約42万円以上の補助
尾張エリアでも、市町村・県・国の補助を組み合わせることで、大幅な費用削減が可能です。
知多エリア(半田・東海・知多・常滑 など)
知多エリアは、愛知県の南部に位置し、名古屋市の南側に広がる地域です。
このエリアの市町村は、太陽光+蓄電池の同時導入を条件とする補助が多いのが特徴です。
■ 知多エリアの主要市町村補助金一覧
|
市町村名 |
太陽光発電 |
蓄電池 |
V2H |
申請期間 |
|
半田市 |
一律21.78万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
– |
2025/4/1〜予算満了 |
|
東海市 |
上限20万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/3/19 |
|
知多市 |
一律20万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/3/31 |
|
大府市 |
– |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/2/28 |
|
常滑市 |
– |
– |
– |
実施なし |
|
高浜市 |
一律16万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/2/27 |
■ エリアの特徴と補助金のポイント
- 半田市は太陽光+蓄電池セットで高額 半田市は、太陽光+HEMS+蓄電池の同時導入で一律21.78万円の補助を実施しています。
- 常滑市は補助制度なし 常滑市は、2025年度時点で太陽光・蓄電池の補助金制度を実施していません。
国の補助金のみが活用可能です。
- 大府市は蓄電池・V2Hのみ対象 大府市は、太陽光発電の補助は行っていませんが、蓄電池とV2Hの補助は実施しています。
- 申請期間は年度末まで 知多市は2026年3月31日まで申請可能と、比較的長い期間を設定しています。
■ 知多エリアで補助を最大化する方法
ケース:半田市で太陽光5kW+蓄電池8kWhを導入
- 市町村補助:21.78万円(太陽光+HEMS+蓄電池セット)
- 県協調補助:上乗せ分(市町村経由で自動交付)
- 国DR補助金:最大14万円(併用可能)
- 合計:約36万円以上の補助
知多エリアでも、市町村補助が充実している市では大幅な費用削減が期待できます。
東三河エリア(豊橋・豊川・蒲郡・新城 など)
東三河エリアは、愛知県の東部に位置し、静岡県に接する地域です。
このエリアの市町村は、補助額は中程度だが、申請期間が比較的長いのが特徴です。
■ 東三河エリアの主要市町村補助金一覧
|
市町村名 |
太陽光発電 |
蓄電池 |
V2H |
申請期間 |
|
豊橋市 |
– |
1万円/kWh(上限7万円) |
– |
2025/4/1〜2026/3/31 |
|
豊川市 |
一律10万円(蓄電池セット) |
一律5万円 |
一律5万円 |
2025/4/25〜予算満了 |
|
蒲郡市 |
上限12万円(蓄電池セット) |
一律5万円 |
一律2.5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
新城市 |
一律7万円(蓄電池セット) |
一律5万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
田原市 |
設置価格×1/4(上限10万円) |
設置価格×1/4(上限15万円) |
設置価格×1/4(上限5万円) |
2025/4/1〜2026/3/31 |
■ エリアの特徴と補助金のポイント
- 豊橋市は蓄電池のみ補助 豊橋市は、太陽光発電の補助は行っていませんが、蓄電池はkWh単価で補助しています。
- 豊川市は同時導入で10万円 豊川市は、太陽光+HEMS+蓄電池の同時導入で一律10万円の補助を実施しています。
- 田原市は設置費用の1/4を補助 田原市は、設置費用の4分の1を補助する方式を採用しており、高額な設備ほど補助額が増加します。
- 申請期間は年度末まで 豊橋市と田原市は、2026年3月31日まで申請可能と、長い期間を設定しています。
■ 東三河エリアで補助を最大化する方法
ケース:田原市で太陽光5kW+蓄電池10kWhを導入(設置費用250万円)
- 市町村補助:設置費用250万円 × 1/4 = 62.5万円(ただし上限適用)
- 太陽光:上限10万円
- 蓄電池:上限15万円
- 合計:25万円
- 県協調補助:上乗せ分(市町村経由で自動交付)
- 国DR補助金:最大14万円(併用可能)
- 合計:約39万円以上の補助
東三河エリアは、西三河や尾張に比べて補助額はやや控えめですが、申請期間が長いため、余裕を持って申請できます。
郡部・町村(東郷・豊山・大口・扶桑 など)
愛知県内には、市だけでなく町村も多数存在し、それぞれ独自の補助金制度を設けています。
郡部・町村の補助金は、一律額での交付が多く、申請手続きも比較的シンプルなのが特徴です。
■ 郡部・町村の補助金一覧
|
市町村名 |
太陽光発電 |
蓄電池 |
V2H |
申請期間 |
|
東郷町 |
一律20万円(蓄電池セット) |
一律5万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
豊山町 |
1.32万円/kW(上限11.28万円) |
一律5万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
大口町 |
一律21.28万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
扶桑町 |
1.32万円/kW(上限5.28万円) |
設置価格×1/4(上限15万円) |
設置価格×1/4(上限5万円) |
2025/4/1〜予算満了 |
|
大治町 |
一律6万円(蓄電池セット) |
一律3万円 |
– |
2025/4/1〜予算満了 |
|
蟹江町 |
一律8万円(蓄電池セット) |
一律5万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
飛島村 |
一律65万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律10万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
阿久比町 |
一律20万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/2/27 |
|
東浦町 |
一律20万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/3/13 |
|
武豊町 |
一律46万円(蓄電池セット) |
補助対象経費の額(上限40万円) |
補助対象経費の額(上限5万円) |
2025/4/1〜2026/3/13 |
|
幸田町 |
一律21.28万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜予算満了 |
|
設楽町 |
一律20万円(蓄電池セット) |
一律10万円 |
– |
2025/4/1〜予算満了 |
|
東栄町 |
一律16.28万円(蓄電池セット) |
一律15万円 |
– |
2025/4/1〜予算満了 |
|
豊根村 |
一律46.28万円(蓄電池セット) |
一律40万円 |
一律5万円 |
2025/4/1〜2026/3/31 |
■ エリアの特徴と補助金のポイント
- 飛島村は県内トップクラスの高額補助 飛島村は、太陽光+蓄電池の同時導入で一律65万円と、県内でも突出した高額補助を実施しています。
人口が少ない村であるため、予算枠は限られていますが、該当する方は大きなメリットがあります。
- 武豊町・豊根村も高額 武豊町と豊根村は、太陽光+蓄電池セットで約46万円の補助を実施しており、郡部・町村の中でも手厚い支援が受けられます。
- 大治町は比較的控えめ 大治町は、太陽光+蓄電池セットで一律6万円と、他の町村に比べて補助額は控えめです。
- 申請期間は予算満了まで ほとんどの町村が「予算満了まで」という形で受付しており、具体的な終了日は定められていません。
■ 郡部・町村で補助を最大化する方法
ケース:飛島村で太陽光5kW+蓄電池8kWhを導入
- 市町村補助:65万円(太陽光+蓄電池セット)
- 県協調補助:上乗せ分(市町村経由で自動交付)
- 国DR補助金:最大14万円(併用可能)
- 合計:約79万円以上の補助
飛島村のように高額補助を実施している町村では、市町村・県・国の補助を組み合わせることで、初期費用の大部分をカバーできます。
■ 郡部・町村の注意点
郡部・町村は人口が少ないため、補助金の予算枠も小さい傾向があります。
そのため、年度初めに早めに申請しないと、予算が満了してしまう可能性が高いです。
また、町村によっては「過去に同一の補助金を受けていないこと」という条件を設けている場合もあるため、事前に確認が必要です。
国の補助金との併用ガイド(DR・CEV・住宅省エネキャンペーン 等)

蓄電池|DRや住宅省エネ関連の要点と併用の順序
国は、家庭用蓄電池の普及を促進するため、複数の補助金制度を運営しています。
愛知県内の市町村・県の補助金と併用できるケースが多く、うまく組み合わせることで初期費用を大幅に削減できます。
■ 蓄電池に関する主な国の補助金制度(2025年度)
|
補助金名 |
運営主体 |
補助額 |
申請期間 |
併用可否 |
|
DR補助金 |
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) |
最大14万円(容量・条件による) |
2025年4月〜予算満了 |
市町村・県と併用可 |
|
住宅省エネキャンペーン |
国土交通省・経済産業省・環境省 |
蓄電池:最大5万円 |
2025年3月〜予算満了 |
市町村・県と併用可 |
|
子育てグリーン住宅支援事業 |
国土交通省 |
蓄電池:設置条件により変動 |
2025年4月〜予算満了 |
市町村・県と併用可 |
■ DR補助金とは?
DR(デマンドレスポンス)補助金は、電力需給の調整に協力する家庭用蓄電池を対象とした補助金です。
DR補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
DR補助金の主な条件:
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が認定した蓄電池を設置すること
- DRに対応したエネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入すること
- 電力会社が実施するDRイベント(電力需要のピーク時に電力使用を抑制する取り組み)に参加すること
DR補助金の補助額は、蓄電池の容量や性能によって異なりますが、最大14万円程度が交付されます。
■ 住宅省エネキャンペーンとは?
住宅省エネキャンペーンは、国土交通省・経済産業省・環境省が連携して実施する補助金制度で、省エネ性能の高い住宅設備の導入を支援しています。
蓄電池も対象となっており、一定の条件を満たすことで補助金を受けられます。
住宅省エネキャンペーンの主な条件:
- 登録事業者による施工であること
- 一定の省エネ基準を満たす蓄電池であること
- 既存住宅へのリフォームとして設置すること(新築は別枠)
住宅省エネキャンペーンの補助額は、蓄電池単体で最大5万円程度です。
ただし、他の省エネ設備(断熱窓、高効率給湯器など)と組み合わせることで、補助額が増加する場合があります。
■ 併用の順序と注意点
市町村・県の補助金と国の補助金を併用する場合、申請の順序が重要です。
誤った順序で申請すると、一方の補助金が受けられなくなる可能性があります。
推奨される申請順序:
ステップ1:国の補助金(DR補助金など)を先に申請 国の補助金は、予算枠が限られており、早期に満了することが多いため、最初に申請することを推奨します。
ステップ2:市町村・県の補助金を申請 国の補助金の交付決定を受けた後、市町村・県の補助金を申請します。
市町村の申請書類に「国の補助金を受ける予定」または「既に受けた」旨を記載する欄がある場合があります。
ステップ3:工事実施 すべての補助金の交付決定を受けた後、工事を開始します。
ステップ4:実績報告 工事完了後、各補助金の実績報告を行います。
■ 併用時の注意点
- 補助金の重複受給の制限
一部の補助金制度では、「同一の設備に対して他の補助金を受けていないこと」という条件がある場合があります。
ただし、愛知県内の市町村補助金と国の補助金は、ほとんどの場合併用が認められています。
- 申請書類に他の補助金受給状況を記載
市町村の申請書類に「他の補助金を受ける予定か」という質問がある場合、正直に記載してください。
虚偽の記載は補助金の返還義務につながります。
- 国の補助金は施工業者が代行申請するケースが多い
DR補助金や住宅省エネキャンペーンは、施工業者が申請を代行することが一般的です。
施工業者に「国の補助金も併用したい」旨を事前に伝え、対応可能かどうか確認してください。
■ 併用例:名古屋市で蓄電池8kWhを導入
補助金の内訳:
- 名古屋市補助:1.5万円/kWh × 8kWh = 12万円
- 愛知県協調補助:上乗せ分(市町村経由で自動交付)
- 国DR補助金:最大14万円
- 合計:約26万円以上の補助
このように、市町村・県・国の補助を組み合わせることで、蓄電池の初期費用を大幅に削減できます。
V2H|CEV補助金の対象・上限・併用注意
V2H(Vehicle to Home)は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)のバッテリーを家庭用電源として活用するシステムです。
国は、V2Hの普及を促進するため、CEV補助金という制度を運営しています。
■ CEV補助金とは?
CEV補助金は、一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が運営する補助金制度で、クリーンエネルギー自動車(CEV)および関連設備の導入を支援しています。
V2H充放電設備もこの補助金の対象となります。
■ CEV補助金の対象設備
CEV補助金の対象となるV2H設備は、双方向充放電機能を持つ設備に限定されます。
具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
CEV補助金の対象条件:
- 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が認定した「補助対象V2H充放電設備」であること
- EVまたはPHEVのバッテリーから家庭へ電力を供給できる双方向充放電機能を持つこと
- 普通充電設備や急速充電設備(充電のみ可能)は対象外
■ CEV補助金の補助額
CEV補助金の補助額は、V2H充放電設備の購入費および設置工事費の合計額の2分の1以内で、上限は20万円です。
たとえば、V2H設備の購入費が30万円、設置工事費が20万円の場合、合計50万円の2分の1 = 25万円となりますが、上限が20万円のため、補助額は20万円となります。
■ 併用の可否と注意点
CEV補助金は、愛知県内の市町村・県の補助金と併用可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 申請の順序 CEV補助金は、工事完了後に申請する制度です。
一方、市町村の補助金は「交付決定前着工NG」というルールがあるため、以下の順序で進めることが推奨されます。
推奨される申請順序:
- ステップ1:市町村の補助金を申請(交付決定を待つ)
- ステップ2:交付決定後に工事を開始
- ステップ3:工事完了後、市町村とCEV補助金の両方に実績報告
- 対象機器の確認 市町村の補助対象機器とCEV補助金の対象機器が一致しているかを事前に確認してください。
一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)の公式サイトで「補助対象V2H充放電設備一覧」を確認し、自分が設置予定の機器が掲載されているかをチェックしましょう。
- 申請は施工業者が代行 CEV補助金の申請は、施工業者が代行することが一般的です。
施工業者に「CEV補助金も併用したい」旨を事前に伝え、対応可能かどうか確認してください。
■ 併用例:名古屋市でV2Hを導入
補助金の内訳:
- 名古屋市補助:一律5万円
- 愛知県協調補助:上乗せ分(市町村経由で自動交付)
- CEV補助金:最大20万円
- 合計:約25万円以上の補助
このように、市町村・県・国の補助を組み合わせることで、V2Hの初期費用を大幅に削減できます。
■ V2H導入時の注意点
- 対応車種の確認 V2Hは、すべての電気自動車に対応しているわけではありません。
自分が所有している(または購入予定の)EVやPHEVが、V2Hに対応しているかを事前に確認してください。
- 電気工事の必要性 V2Hの設置には、専門の電気工事が必要です。
一般的な電気工事業者ではなく、V2H設置の実績がある業者に依頼することを推奨します。
- 停電時の活用方法 V2Hを導入する主なメリットの一つは、停電時にEVのバッテリーを家庭用電源として使用できることです。
停電時の使用方法や、自動切り替え機能の有無を事前に確認しておきましょう。
併用の可否を最短で見極める手順
市町村・県・国の補助金を併用できるかどうかを最短で見極めるためには、以下の手順に従ってください。
■ ステップ1:市町村の補助金要綱を確認
まず、お住まいの市町村の補助金要綱を確認し、「他の補助金との併用が可能か」という記載があるかをチェックします。
多くの市町村では、補助金要綱の中に「国または県の補助金との併用を妨げない」といった記載があります。
確認方法:
- 市町村の公式ホームページで補助金要綱をダウンロード
- 「併用」「重複」「他の補助金」といったキーワードで検索
- 不明な場合は、市町村の担当窓口に電話で確認
■ ステップ2:国の補助金の要綱を確認
次に、国の補助金(DR補助金、CEV補助金、住宅省エネキャンペーンなど)の要綱を確認し、「地方自治体の補助金との併用が可能か」という記載があるかをチェックします。
確認方法:
- 国の補助金を運営する団体の公式サイトを確認(SII、NeV、国土交通省など)
- 「併用可否」「他の補助金」といった項目を確認
- 不明な場合は、補助金の問い合わせ窓口に電話で確認
■ ステップ3:施工業者に確認
市町村と国の補助金要綱を確認した後、実際に施工を依頼する業者に「併用が可能か」を確認します。
施工業者は、過去の実績から併用のノウハウを持っている場合が多く、具体的な申請手順や注意点をアドバイスしてくれます。
施工業者に確認すべきポイント:
- 市町村と国の補助金を併用した実績があるか
- 申請の順序はどうすべきか
- 申請書類の準備で注意すべき点はあるか
- 申請代行は可能か
■ ステップ4:申請スケジュールを調整
併用が可能であることが確認できたら、次に申請スケジュールを調整します。
国の補助金は予算枠が限られているため、早めに申請することが重要です。
推奨されるスケジュール:
- 4月〜5月:国の補助金を申請(DR補助金、CEV補助金など)
- 5月〜6月:市町村の補助金を申請
- 6月〜7月:交付決定を受けた後、工事を開始
- 7月〜8月:工事完了後、実績報告を提出
■ 併用可否の判断フローチャート(テキスト版)
【スタート】
↓
市町村の補助金要綱を確認
↓
「他の補助金との併用可能」の記載あり?
├─ あり → 国の補助金要綱を確認
└─ なし → 市町村窓口に電話確認
↓
国の補助金要綱を確認
↓
「地方自治体の補助金との併用可能」の記載あり?
├─ あり → 施工業者に併用実績を確認
└─ なし → 国の補助金窓口に電話確認
↓
施工業者に併用実績あり?
├─ あり → 申請スケジュールを調整
└─ なし → 別の業者を検討
↓
【併用可能と判断】
このフローに従えば、併用の可否を最短で見極めることができます。
発電量と費用対効果|愛知で導入が進む理由
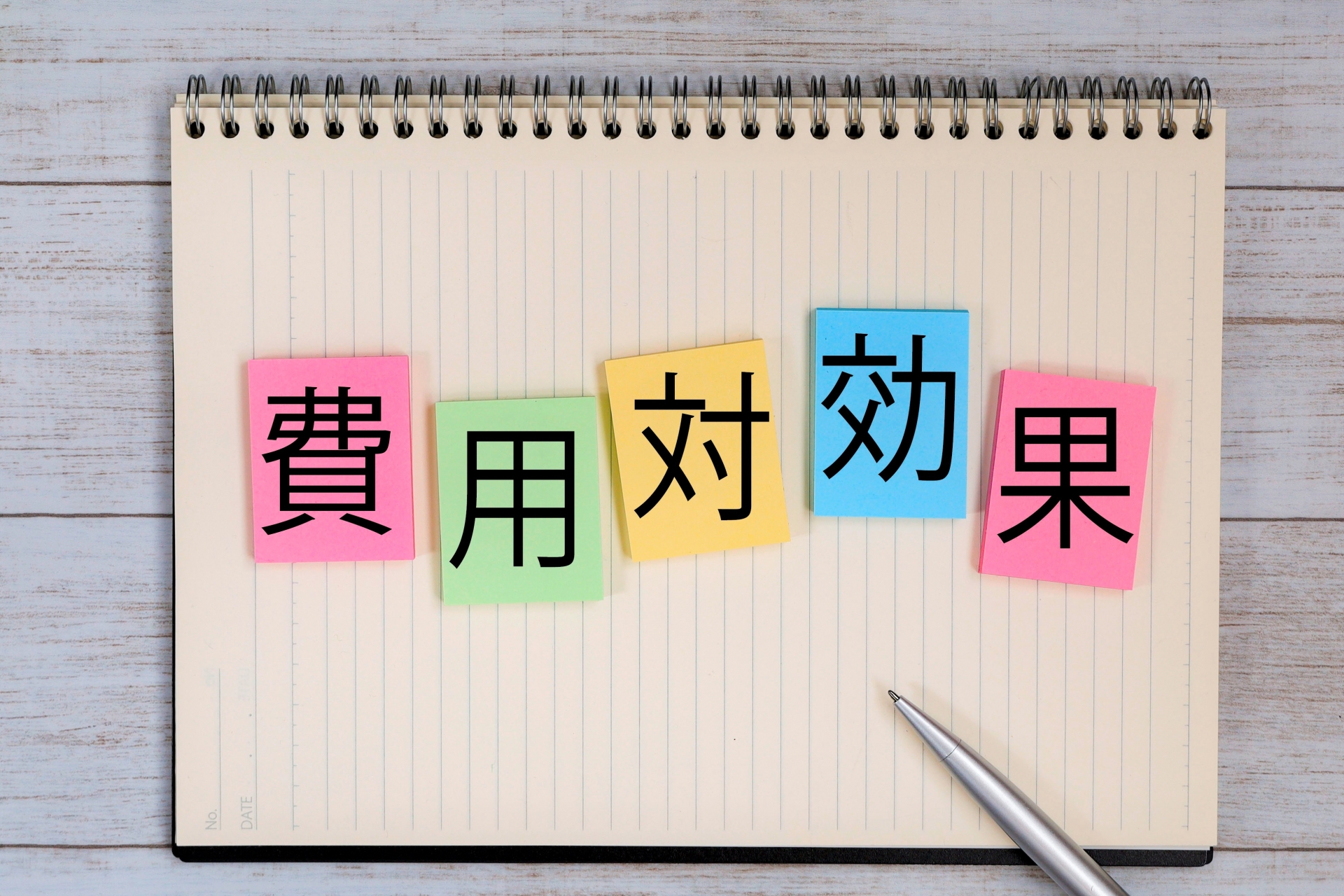
日照条件・想定発電量の目安(kWあたり)
愛知県は、日本有数の日照時間を誇る地域であり、太陽光発電の導入に非常に適した環境が整っています。
ここでは、愛知県における日照条件と、実際の発電量の目安を解説します。
■ 愛知県の日照時間
愛知県の年間平均日照時間は、約2,000時間に達します。
これは、全国平均の約1,800時間を大きく上回る数値であり、太陽光発電に適した日照条件といえます。
特に、県内の西部地域(名古屋市、一宮市、豊田市など)は、年間を通して安定した日照時間が確保できるため、太陽光発電の効率が高いことが知られています。
■ 想定発電量の目安(kWあたり)
愛知県内の太陽光発電所の発電量は、1kWあたり年間約1,100kWhに達すると推定されています。
これは、一般家庭の年間電力消費量の約1/3に相当する発電量であり、太陽光発電の高い潜在能力を示しています。
発電量の計算式:
年間発電量(kWh) = システム容量(kW) × 1,100kWh/kW
たとえば、5kWの太陽光発電システムを設置した場合、年間発電量は以下のようになります。
5kW × 1,100kWh/kW = 5,500kWh
■ 月別の発電量の目安
愛知県における月別の発電量は、季節によって大きく変動します。
以下は、5kWの太陽光発電システムを設置した場合の月別発電量の目安です。
|
月 |
日照時間(時間) |
発電量(kWh) |
|
1月 |
約170時間 |
約350kWh |
|
2月 |
約180時間 |
約380kWh |
|
3月 |
約190時間 |
約450kWh |
|
4月 |
約200時間 |
約500kWh |
|
5月 |
約220時間 |
約550kWh |
|
6月 |
約170時間 |
約400kWh |
|
7月 |
約180時間 |
約420kWh |
|
8月 |
約210時間 |
約500kWh |
|
9月 |
約160時間 |
約380kWh |
|
10月 |
約180時間 |
約450kWh |
|
11月 |
約170時間 |
約400kWh |
|
12月 |
約160時間 |
約350kWh |
|
年間合計 |
約2,190時間 |
約5,130kWh |
このように、愛知県では5月や8月など日照時間が長い月に発電量が増加し、逆に梅雨の時期や冬季は発電量がやや減少します。
■ 発電量に影響する要因
太陽光発電の発電量は、日照時間だけでなく、以下の要因にも影響されます。
- パネルの設置角度 太陽光パネルの設置角度は、発電効率に大きく影響します。
愛知県では、南向き・傾斜角30度が最も発電効率が高いとされています。
- パネルの向き 南向きが最も効率が良く、東向きや西向きは発電量がやや減少します。
北向きは発電効率が大幅に低下するため、避けるべきです。
- 日陰の影響 隣接する建物や樹木によって日陰ができると、発電量が大幅に減少します。
パネルの設置前に、日陰の影響をシミュレーションすることが重要です。
- パネルの劣化 太陽光パネルは、経年劣化により発電効率が低下します。
一般的に、年間0.5〜1%程度の劣化が見込まれます。
4kW太陽光+8kWh蓄電池のモデルケース
ここでは、愛知県内の一般的な戸建住宅に4kWの太陽光発電システムと8kWhの蓄電池を導入した場合のモデルケースを紹介します。
■ 導入費用の目安
|
項目 |
費用(税込) |
|
太陽光発電システム(4kW) |
約120万円 |
|
蓄電池(8kWh) |
約120万円 |
|
工事費・諸経費 |
約40万円 |
|
合計 |
約280万円 |
■ 補助金の活用(名古屋市の場合)
|
補助金名 |
補助額 |
|
名古屋市補助(太陽光:築10年超) |
3万円/kW × 4kW = 12万円 |
|
名古屋市補助(蓄電池) |
1.5万円/kWh × 8kWh = 12万円 |
|
愛知県協調補助 |
上乗せ分(市町村経由で自動交付) |
|
国DR補助金(蓄電池) |
最大14万円 |
|
補助金合計 |
約38万円以上 |
■ 実質負担額
導入費用280万円 − 補助金38万円 = 実質負担額242万円
■ 年間発電量と電気代削減効果
4kWの太陽光発電システムの年間発電量は、以下のように計算できます。
4kW × 1,100kWh/kW = 4,400kWh
一般家庭の年間電力消費量を約4,500kWhとすると、**年間電力自給率は約98%**となり、ほぼ電力を自給自足できる計算になります。
電気代削減効果(年間):
- 電力単価を30円/kWh(深夜電力含む平均)と仮定
- 自家消費分:4,400kWh × 30円/kWh = 約132,000円
- 売電収入:余剰電力を16円/kWhで売電(約1,000kWh) = 約16,000円
- 合計削減効果:約148,000円/年
■ 投資回収期間
実質負担額242万円 ÷ 年間削減効果14.8万円 = 約16.4年
太陽光発電システムの一般的な寿命は25〜30年であるため、16.4年で投資を回収した後は、純粋な利益となります。
■ 停電時の活用
8kWhの蓄電池があれば、停電時にも以下の電化製品を使用できます。
停電時に使用できる電化製品の目安:
- 冷蔵庫(200W):約40時間
- LED照明(10W × 5個):約160時間
- テレビ(100W):約80時間
- スマートフォン充電(10W):約800時間
- エアコン(600W):約13時間
これにより、災害時の安心感が大幅に向上します。
■ CO2削減効果
4kWの太陽光発電システムによる年間CO2削減量は、以下のように計算できます。
4,400kWh × 0.5kg-CO2/kWh = 約2,200kg-CO2/年
これは、約470本の杉の木が1年間に吸収するCO2量に相当します。
停電対策(自立運転・V2Hの活用)
愛知県では、台風や地震などの自然災害により、停電が発生するリスクがあります。
太陽光発電システムと蓄電池、V2Hを導入することで、停電時でも電力を確保できます。
■ 太陽光発電の自立運転機能
太陽光発電システムには、自立運転機能が標準装備されています。
これは、停電時に太陽光パネルで発電した電力を、家庭内で直接使用できる機能です。
自立運転の使い方:
- 停電が発生したら、パワーコンディショナーのスイッチを「自立運転モード」に切り替える
- 専用のコンセント(自立運転用コンセント)から電力を取り出す
- 最大1.5kW程度の電力を使用できる
自立運転で使用できる電化製品の例:
- 冷蔵庫
- LED照明
- スマートフォン充電
- ノートパソコン
- テレビ
ただし、自立運転は太陽光が発電している昼間のみ使用可能です。
夜間や曇りの日は使用できません。
■ 蓄電池による24時間電力供給
蓄電池を導入することで、昼間に発電した電力を蓄え、夜間や停電時に使用できます。
これにより、停電が夜間に発生した場合でも、電力を確保できます。
蓄電池の容量別使用可能時間:
- 5kWhの蓄電池:一般家庭の約半日分の電力
- 8kWhの蓄電池:一般家庭の約1日分の電力
- 10kWhの蓄電池:一般家庭の約1.5日分の電力
■ V2Hによる大容量電力の確保
V2Hを導入することで、電気自動車(EV)のバッテリーを家庭用電源として使用できます。
EVのバッテリー容量は40〜60kWh程度と非常に大きいため、停電時でも数日間の電力を確保できます。
V2Hの活用例:
- EVのバッテリー容量:40kWh
- 一般家庭の1日の電力消費量:約12kWh
- 使用可能日数:40kWh ÷ 12kWh/日 = 約3日間
■ 停電対策の組み合わせ
太陽光発電、蓄電池、V2Hを組み合わせることで、最強の停電対策が実現します。
組み合わせ例:
- 昼間:太陽光発電で電力を供給+余剰電力を蓄電池・EVに充電
- 夜間:蓄電池またはEVから電力を供給
- 長期停電:太陽光発電で昼間に充電→夜間に蓄電池・EVから供給を繰り返す
これにより、長期間の停電でも電力を確保できます。
申請の進め方|スケジュールと必要書類
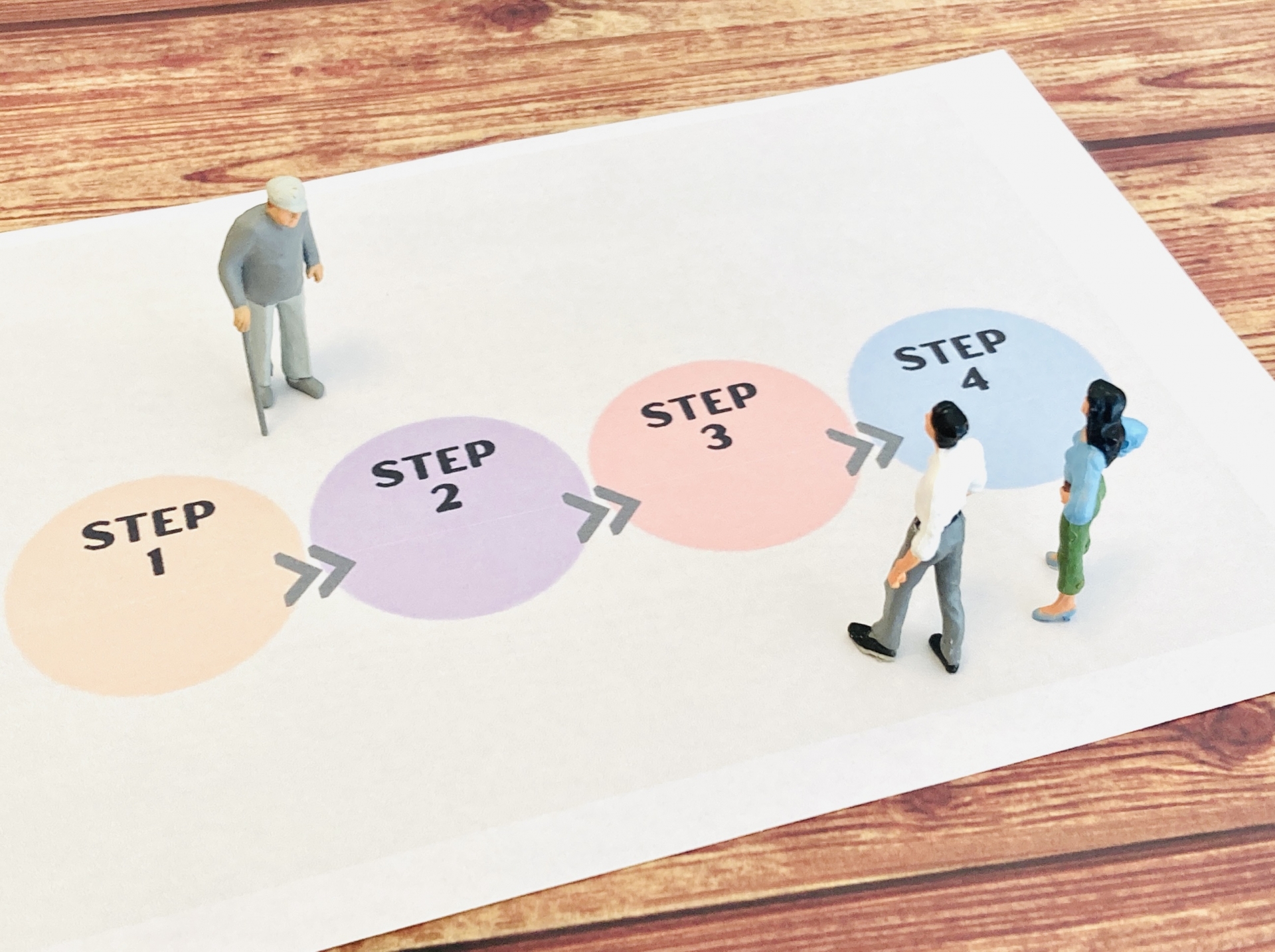
事前確認(対象機器・販売事業者・型式・見積条件)
補助金の申請をスムーズに進めるためには、事前確認が非常に重要です。
ここでは、申請前に確認すべき項目を詳しく解説します。
■ 対象機器の確認
まず、自分が設置予定の太陽光発電システム、蓄電池、V2Hが、補助金の対象機器であるかを確認します。
確認方法:
- 市町村の補助金要綱で「対象機器の要件」を確認
- 国の補助金(DR補助金、CEV補助金など)の対象機器一覧を確認
- メーカーまたは販売事業者に「補助対象機器か」を確認
対象機器の要件の例:
- 太陽光発電:JET認証(日本電気安全環境研究所)を取得していること
- 蓄電池:SII(環境共創イニシアチブ)の登録製品であること
- V2H:NeV(次世代自動車振興センター)の認定製品であること
■ 販売事業者の確認
補助金を受けるためには、一定の要件を満たす販売事業者から購入する必要がある場合があります。
特に、国の補助金(DR補助金、住宅省エネキャンペーンなど)では、登録事業者による施工が条件となっているケースが多いです。
確認方法:
- 国の補助金を運営する団体の公式サイトで「登録事業者一覧」を確認
- 施工業者に「補助金の登録事業者か」を確認
■ 型式の確認
補助金の申請書類には、設置する機器の**型式(モデル番号)**を記載する必要があります。
型式が不明確だと、補助対象機器かどうかを確認できず、申請が受理されない可能性があります。
確認方法:
- 見積書に機器の型式が明記されているかを確認
- メーカーのカタログで型式を確認
- 施工業者に「補助金申請用の型式情報を提供してほしい」と依頼
■ 見積条件の確認
補助金の申請には、施工業者からの見積書が必要です。
見積書には、以下の情報が明記されている必要があります。
見積書に必要な情報:
- 太陽光発電システムの容量(kW)
- 蓄電池の容量(kWh)
- V2Hの型式
- 各機器の単価
- 工事費・諸経費の内訳
- 合計金額(税込)
見積書に不備があると、申請が差し戻される可能性があるため、施工業者に「補助金申請用の見積書」を作成してもらうことを推奨します。
交付申請→交付決定→工事→実績報告の流れ
補助金の申請から交付までの流れは、以下のステップで進みます。
■ ステップ1:交付申請
補助金を受けるための最初のステップは、交付申請です。
交付申請では、以下の書類を市町村の担当窓口に提出します。
交付申請時の必要書類:
- 交付申請書(市の指定様式)
- 設置する機器のカタログまたは仕様書
- 設置場所の図面(配置図、立面図など)
- 見積書の写し
- 住民票の写し
- 建物の登記事項証明書または固定資産税納税通知書の写し
- 電気事業者との契約書の写し
- HEMSの設置を証明する書類
申請方法:
- 市町村の窓口に直接提出
- 郵送で提出(市町村による)
- オンライン申請(一部の市町村のみ)
■ ステップ2:交付決定
申請書類が受理されると、市町村が審査を行います。
審査には通常2週間〜1か月程度かかります。
審査が完了すると、交付決定通知書が郵送されます。
交付決定通知書に記載される内容:
- 交付決定額
- 工事着手の可否
- 実績報告の期限
- 注意事項
重要:交付決定通知を受け取るまで工事に着手しないでください。
交付決定前に工事を開始すると、補助金は一切交付されません。
■ ステップ3:工事実施
交付決定通知を受け取った後、施工業者と工事日程を調整し、工事を開始します。
工事期間は、システムの規模や施工内容によって異なりますが、通常1〜2週間程度です。
工事中に注意すべきポイント:
- 設置写真を撮影する(銘板、シリアル番号、設置状況など)
- 検査報告書を取得する
- 保証書を受け取る
■ ステップ4:実績報告
工事が完了したら、実績報告書を市町村に提出します。
実績報告は、工事完了後2週間以内に提出することが一般的です。
実績報告時の必要書類:
- 実績報告書(市の指定様式)
- 設置完了後の写真(設備全体、銘板、シリアル番号など)
- 領収書または請求書の写し
- 検査報告書
- 保証書の写し
■ ステップ5:補助金の交付
実績報告が審査され、問題がなければ、補助金が指定口座に振り込まれます。
振り込みまでの期間は、実績報告後1〜2か月程度です。
よくある差し戻し事例(図面不備・設置写真・シリアル不一致など)
補助金の申請では、書類に不備があると**差し戻し(再提出)**となります。
差し戻しが発生すると、審査が遅れるだけでなく、最悪の場合は補助金が受けられなくなる可能性もあります。
ここでは、よくある差し戻し事例とその対策を紹介します。
■ 事例1:設置写真が不鮮明
実績報告時に提出する設置写真が不鮮明だと、設備が正しく設置されているかを確認できず、差し戻しとなります。
対策:
- 写真は高解像度で撮影する
- 銘板やシリアル番号が明確に読み取れるように撮影する
- 設備全体が写るように撮影する
■ 事例2:図面が古い
既存住宅に設備を設置する場合、提出する図面が古く、現在の状態と異なると、差し戻しとなります。
対策:
- 最新の図面を用意する
- 図面がない場合は、施工業者に作成してもらう
■ 事例3:シリアル番号の不一致
申請時に記載した機器の型式・シリアル番号と、実際に設置した機器のシリアル番号が異なると、差し戻しまたは不交付となります。
対策:
- 申請時に記載した型式・シリアル番号を正確に確認する
- 工事前に施工業者に「申請した機器と同じものを設置する」ことを確認する
■ 事例4:見積書に機器の詳細が記載されていない
見積書に「太陽光発電システム一式」としか記載されておらず、容量や型式が不明だと、差し戻しとなります。
対策:
- 見積書には、容量(kW、kWh)、型式、メーカー名を明記してもらう
■ 事例5:領収書の日付が交付決定前
領収書の日付が交付決定前になっていると、「交付決定前着工」とみなされ、不交付となります。
対策:
- 工事代金の支払いは、交付決定後に行う
- 施工業者に「交付決定後に支払う」ことを事前に伝える
これらの差し戻し事例を事前に把握し、書類の準備を慎重に行うことで、スムーズに補助金を受け取ることができます。
施工業者の選び方|補助金に強い会社を見極める

認定・実績・メーカー関係(認定施工店・登録事業者)
太陽光発電や蓄電池の導入を成功させるためには、信頼できる施工業者を選ぶことが非常に重要です。
ここでは、補助金に強い施工業者を見極めるポイントを解説します。
■ 認定施工店かどうかを確認
太陽光発電や蓄電池のメーカーは、一定の基準を満たした施工業者を認定施工店として登録しています。
認定施工店は、メーカーから技術研修を受けており、高い施工品質が期待できます。
認定施工店のメリット:
- メーカー保証が適用される
- 施工ミスが少ない
- アフターサービスが充実している
確認方法:
- メーカーの公式サイトで「認定施工店一覧」を確認
- 施工業者に「認定施工店か」を確認
■ 国の補助金の登録事業者かどうかを確認
国の補助金(DR補助金、住宅省エネキャンペーンなど)を利用する場合、登録事業者による施工が条件となっている場合があります。
登録事業者でない業者に依頼すると、国の補助金が受けられない可能性があります。
確認方法:
- 国の補助金を運営する団体の公式サイトで「登録事業者一覧」を確認
- 施工業者に「国の補助金の登録事業者か」を確認
■ 施工実績を確認
施工業者の実績は、工事の品質に直結します。
太陽光発電や蓄電池の導入実績が豊富な業者を選ぶことで、高い施工品質が期待できます。
確認方法:
- 施工業者の公式サイトで施工事例を確認
- 施工業者に「愛知県内での施工実績」を確認
- 口コミサイトやレビューサイトで評判を確認
■ メーカーとの関係を確認
施工業者がメーカーと良好な関係を築いていることで、適切な製品選定やアフターサービスが受けられる可能性が高まります。
確認方法:
- 施工業者が取り扱っているメーカーの種類を確認
- 複数のメーカーを取り扱っている業者は、中立的な提案が期待できる
見積の透明性(機器明細・工賃・諸経費の内訳)
施工業者から提示される見積書の内容を確認することは、適正な価格で導入するために非常に重要です。
ここでは、見積書で確認すべきポイントを解説します。
■ 機器明細が詳細に記載されているか
見積書には、以下の情報が明記されている必要があります。
機器明細に必要な情報:
- 太陽光パネルのメーカー・型式・容量(kW)・枚数
- パワーコンディショナーのメーカー・型式・容量
- 蓄電池のメーカー・型式・容量(kWh)
- V2Hのメーカー・型式
- HEMSのメーカー・型式
「太陽光発電システム一式」といった曖昧な記載では、どのような機器が設置されるのか不明です。
■ 工賃の内訳が明記されているか
見積書には、工事費の内訳が明記されている必要があります。
工賃の内訳例:
- 太陽光パネル設置工事費
- 配線工事費
- 電気工事費
- 足場設置費
- 撤去・処分費(既存設備がある場合)
工賃が「工事費一式」としか記載されていない場合、適正な価格かどうかを判断できません。
■ 諸経費の内訳が明記されているか
諸経費には、以下のような項目が含まれます。
諸経費の内訳例:
- 現場管理費
- 申請代行費
- 設計費
- 保証費
諸経費が不明瞭な見積書は、後から追加費用が発生するリスクがあります。
■ 相見積もりを取る
複数の施工業者から見積を取り、価格と内容を比較することが重要です。
相見積もりを取ることで、適正な価格を把握できます。
相見積もりのポイント:
- 最低3社から見積を取る
- 同じ条件(容量、メーカーなど)で見積を依頼する
- 安すぎる見積には注意する(品質が低い可能性)
申請サポート体制(書類代行・進捗共有・不備対応)
補助金の申請は、書類の準備や提出など、手続きが煩雑です。
申請サポート体制が充実している施工業者を選ぶことで、スムーズに補助金を受け取ることができます。
■ 書類代行サービスの有無
多くの施工業者は、補助金の申請書類を代行で作成してくれます。
書類代行サービスを利用することで、手間を大幅に削減できます。
書類代行サービスの内容:
- 交付申請書の作成
- 必要書類の収集・整理
- 実績報告書の作成
- 市町村への提出
確認方法:
- 施工業者に「補助金の申請代行サービスはあるか」を確認
- 代行費用が別途発生するかを確認
■ 進捗共有の体制
補助金の申請から交付までの進捗状況を、定期的に共有してくれる業者を選ぶことが重要です。
進捗が不明だと、不安になります。
進捗共有の内容:
- 申請書類の提出状況
- 交付決定の通知状況
- 工事の進捗状況
- 実績報告の提出状況
確認方法:
- 施工業者に「進捗を定期的に報告してもらえるか」を確認
■ 不備対応の体制
申請書類に不備があった場合、迅速に対応してくれる業者を選ぶことが重要です。
不備対応が遅れると、補助金の交付が遅れる可能性があります。
不備対応の内容:
- 差し戻された書類の修正
- 追加書類の準備
- 市町村との調整
確認方法:
- 施工業者に「不備があった場合、どのように対応してもらえるか」を確認
市町村別Q&A(名古屋・豊田・春日井・刈谷・半田 など)

申請期限は?交付決定前に契約・着工できる?
Q:名古屋市の補助金の申請期限はいつまでですか?
A:名古屋市の補助金の申請期限は、2026年2月13日です。
ただし、予算に達した時点で受付終了となるため、早めの申請を推奨します。
Q:豊田市の補助金の申請期限はいつまでですか?
A:豊田市の補助金は、予算満了まで受け付けられます。
具体的な終了日は定められていませんが、人気が高いため、年度前半で予算が尽きる可能性があります。
Q:交付決定前に契約や着工をしても良いですか?
A:絶対にダメです。
交付決定前に契約や着工をすると、補助金は一切交付されません。
必ず交付決定通知を受け取った後に、工事を開始してください。
既設太陽光に”後付け蓄電池”は対象?
Q:既に太陽光発電を設置しているが、後から蓄電池を追加しても補助金は受けられますか?
A:多くの市町村では、既設太陽光への後付け蓄電池も補助対象となります。
たとえば、名古屋市では「既設の太陽光発電設備に接続する蓄電システムが対象」と明記されています。
ただし、市町村によっては「太陽光と蓄電池の同時導入が条件」としている場合もあるため、事前に確認してください。
Q:FIT期間が終了した太陽光発電に蓄電池を追加しても補助金は受けられますか?
A:はい、FIT期間終了後(卒FIT)の太陽光発電にも蓄電池を追加できます。
むしろ、卒FIT後は売電価格が大幅に下がるため、蓄電池を導入して自家消費率を高めることが推奨されています。
リース・中古機器・ネット購入は対象外?
Q:リース契約で太陽光や蓄電池を導入した場合、補助金は受けられますか?
A:ほとんどの市町村で、リース契約は補助対象外です。
補助金の要件として「自己所有の住宅に設置すること」が定められているため、リース契約では対象となりません。
Q:中古の太陽光パネルや蓄電池を設置した場合、補助金は受けられますか?
A:ほとんどの市町村で、中古機器は補助対象外です。
補助対象となるのは、未使用品(新品)のみです。
Q:ネットで購入した機器を自分で設置した場合、補助金は受けられますか?
A:ほとんどの市町村で、施工業者による設置が条件となっています。
自分で設置した場合、補助金は受けられません。
共同住宅(集合住宅)の扱いは?
Q:マンションやアパートに太陽光や蓄電池を設置した場合、補助金は受けられますか?
A:集合住宅の場合、各住戸ごとに設備を設置する場合は補助対象となります。
ただし、共用部分に設置する場合は、補助対象とならない市町村もあります。
Q:賃貸マンションに住んでいますが、補助金は受けられますか?
A:賃貸住宅の場合、所有者の承諾を得た上で設置する場合は補助対象となる市町村もあります。
ただし、所有者の承諾書が必要となるため、事前に確認してください。
よくある質問(共通編)
いつ・どこに申請?個人でできる?事業者経由が良い?
Q:補助金はいつ申請すれば良いですか?
A:補助金の申請は、**年度初めの早い時期(4月〜5月)**に行うことを推奨します。
多くの市町村は先着順で受け付けており、予算に達した時点で終了となるため、早めの申請が重要です。
Q:補助金はどこに申請すれば良いですか?
A:補助金の申請先は、お住まいの市町村の担当窓口です。
愛知県に直接申請する必要はありません。
Q:補助金は個人で申請できますか?それとも事業者経由が良いですか?
A:個人でも申請は可能ですが、施工業者に申請代行を依頼する方がスムーズです。
施工業者は申請のノウハウを持っており、書類の不備が少なく、迅速に申請を完了できます。
併用の順番を間違えるとどうなる?
Q:市町村と国の補助金の申請順序を間違えるとどうなりますか?
A:申請順序を間違えると、一方の補助金が受けられなくなる可能性があります。
一般的には、国の補助金を先に申請し、その後市町村の補助金を申請することが推奨されます。
ただし、市町村によっては「交付決定前着工NG」というルールがあるため、申請順序は慎重に決める必要があります。
Q:併用できるかどうか不安な場合、どうすれば良いですか?
A:不安な場合は、施工業者に相談することを推奨します。
施工業者は、過去の実績から併用のノウハウを持っており、適切なアドバイスをしてくれます。
予算満了時の代替策(翌年度・他制度・規模調整)
Q:市町村の補助金が予算満了で受けられなかった場合、どうすれば良いですか?
A:以下の代替策を検討してください。
代替策1:翌年度の補助金を待つ 翌年度も補助金制度が継続される可能性があります。
ただし、翌年度の補助金額や条件が変更される可能性もあるため、注意が必要です。
代替策2:国の補助金のみを活用する 市町村の補助金が受けられなくても、国の補助金(DR補助金、CEV補助金など)は申請可能です。
代替策3:設備の規模を調整する 予算が限られている場合、設備の規模を縮小することで、初期費用を抑えることができます。
たとえば、太陽光発電の容量を4kWから3kWに減らす、蓄電池の容量を8kWhから5kWhに減らすなどの調整が可能です。
代替策4:金融機関のローンを活用する 補助金が受けられない場合でも、金融機関の低金利ローンを活用することで、初期費用の負担を軽減できます。
まとめ

愛知県で太陽光発電や蓄電池を導入する際、補助金を最大限に活用することで、初期費用を大幅に削減できます。
本記事では、2025年度(令和7年度)の愛知県内54市町村の最新補助金情報を網羅的に整理し、名古屋市をはじめとする主要都市の詳細、国の補助金との併用方法、申請時の注意点、施工業者の選び方まで、実務レベルで必要な情報をすべて解説しました。
補助金を確実に受け取るための重要ポイント:
- 交付決定前の着工は絶対にNG。必ず交付決定通知を受け取った後に工事を開始してください。
- 中古機器・リース契約は補助対象外。未使用品(新品)を自己所有の形で導入してください。
- 予算満了リスクを常に意識し、年度初めの早い時期(4月〜5月)に申請を完了させてください。
- 市町村・県・国の補助金を組み合わせることで、最大60万円以上の補助を受けられるケースもあります。
- 施工業者選びが成功の鍵。認定施工店で、申請サポート体制が充実している業者を選んでください。
愛知県は日照時間が長く、太陽光発電に非常に適した地域です。
年間約1,100kWh/kWの発電量が期待でき、4kWの太陽光発電システムであれば年間約14万円の電気代削減効果があります。
さらに、蓄電池やV2Hを組み合わせることで、停電時の電力確保や災害対策も実現できます。
補助金制度は年度ごとに変更される可能性があるため、導入を検討している方は、今年度中に申請を完了させることを強く推奨します。
太陽光発電と蓄電池の導入で、電気代削減と環境保全、そして災害対策を同時に実現しましょう。
無料シミュレーションや詳細なご相談は、信頼できる施工業者にお気軽にお問い合わせください。
あなたの快適で持続可能な暮らしを、太陽光発電と蓄電池がサポートします。
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。





