お役立ちコラム 2025.11.10
太陽光FIT入門:仕組み・手続き・卒FIT徹底ガイド

太陽光発電を導入したものの、FIT制度の詳しい仕組みがよく分からないという方は少なくありません。
「固定価格買取制度って何年間続くの?」「卒FIT後はどうすればいいの?」「満了通知が来たけど、次にやることは?」こうした疑問を抱えたまま、なんとなく売電を続けている方も多いのではないでしょうか。
実は、FIT制度の終了は大きな転換点であり、適切な対応をするかどうかで年間数万円もの差が生まれることがあります。
売電収入を最大化したい方、電気代を削減したい方、環境に配慮したエネルギー活用をしたい方まで、卒FIT後の選択肢は想像以上に広がっています。
この記事では、FIT制度の基本的な仕組みから、満了前後に必要な手続き、さらには卒FIT後のベストな選択肢まで、太陽光発電オーナーが知っておくべき情報を網羅的に解説します。
初めて太陽光発電を検討している方から、すでに卒FITを迎えた方まで、それぞれの状況に応じた実践的な知識が得られる内容となっています。
トラブルを避けながら、あなたの太陽光発電を最大限に活用するための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
目次
FIT制度の基礎を最短理解

FITとは?固定価格で買い取る国の仕組み
FIT制度(Feed-in Tariff)とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた価格で一定期間買い取ることを電力会社に義務づける制度です。
正式には「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」と呼ばれ、2012年7月にスタートしました。
この制度が生まれた背景には、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの普及を加速させるという国の明確な目的があります。
当時、太陽光発電システムの導入費用は非常に高額で、一般家庭が設置するには大きな経済的ハードルがありました。
そこで政府は、高めの買取価格を保証することで初期投資の回収見込みを立てやすくし、設置を促進する戦略を取ったのです。
具体的な仕組みとしては、太陽光発電で作った電気のうち、自宅で使わずに余った分(余剰電力)を電力会社が買い取ります。
この買取にかかる費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、すべての電気利用者が電気料金の一部として負担しています。
つまり、太陽光発電を設置している家庭の売電収入は、全国の電気利用者によって支えられている構造なのです。
FIT制度における買取価格は、設置した年度によって決まります。
たとえば2012年度に住宅用太陽光発電(10kW未満)を設置した場合、1kWhあたり42円という高額な価格で電気を売ることができました。
2019年度には24円、2023年度には16円と、年々買取価格は下がっています。
これは太陽光パネルの価格が下がり、初期投資額が減少したことに対応した調整です。
重要なのは、一度決まった買取価格は契約期間中ずっと変わらないという点です。
2012年度に42円で契約した方は、10年間ずっと42円で売電できます。
後から買取価格が下がっても影響を受けないため、「固定価格」買取制度と呼ばれているのです。
この制度によって、日本国内の太陽光発電の導入量は飛躍的に増加しました。
2012年時点では累積導入量が約500万kWでしたが、2023年には約8,000万kWを超える規模にまで成長しています。
FIT制度は、日本のエネルギー政策における再生可能エネルギー普及の中核を担ってきた制度といえるでしょう。
|
項目 |
内容 |
|
制度名称 |
再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT) |
|
開始時期 |
2012年7月 |
|
主な目的 |
再生可能エネルギーの普及促進 |
|
対象設備 |
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス |
|
費用負担 |
再エネ賦課金として全電気利用者が負担 |
制度の本質を理解することで、自分の太陽光発電がどのような仕組みの中で運用されているのかが明確になります。
また、卒FIT後の選択肢を考える際にも、この基礎知識が判断材料として役立つでしょう。
10kW未満は10年など買取期間の考え方と注意点
FIT制度における買取期間は、太陽光発電システムの規模によって明確に区分されています。
最も重要な分岐点は、出力が10kW未満か10kW以上かという点です。
一般的な住宅用太陽光発電は10kW未満に該当し、この場合の買取期間は10年間と定められています。
一方、10kW以上の設備(産業用や大規模な住宅用)の場合、買取期間は20年間となります。
この期間の違いは、設置者の事業性や初期投資額の回収期間を考慮して設定されたものです。
10kW未満の住宅用では、主に余剰電力の売電が想定されており、自家消費と併用することで比較的早期に投資回収が可能と判断されています。
対して10kW以上の産業用では、全量売電を前提とした事業性の高い運用が想定されるため、より長期の収益保証が必要とされたのです。
ここで注意すべき重要なポイントがあります。
買取期間は「設置してから」ではなく、「売電を開始してから」10年または20年とカウントされます。
つまり、設置工事が完了してもすぐに売電契約が始まらなければ、その分だけ実質的な買取期間が後ろ倒しになります。
また、買取期間の満了日は、契約開始月から数えて正確に10年後または20年後の月末となります。
たとえば2013年4月15日に売電を開始した場合、10年間の買取期間は2023年4月30日に満了します。
満了の数か月前には、電力会社から「買取期間満了のお知らせ」が送付されますが、この通知を見落とすと次の契約準備が遅れる可能性があります。
買取期間中は固定価格が保証されていますが、期間満了後は自動的に新しい条件に切り替わるわけではありません。
何も手続きをしないと、従来よりも大幅に低い価格での買取となったり、場合によっては売電自体ができなくなる可能性もあります。
「10年経ったらどうなるの?」という疑問を持つ方は多いのですが、答えは「契約内容次第」です。
満了後も売電を継続したい場合は、新たに電力会社と契約を結ぶ必要があります。
この「卒FIT」と呼ばれる状況については、後の章で詳しく解説します。
買取期間に関するもう一つの注意点は、制度変更のリスクです。
FIT制度自体は2012年に始まりましたが、その後も法改正や制度改定が行われています。
2017年には改正FIT法(FIT法改正)が施行され、事業計画の認定制度が導入されました。
既存の設備にも一部手続きが必要となり、期限内に手続きをしなかった場合は買取が停止されるという厳しい措置が取られたケースもありました。
このように、FIT制度は国のエネルギー政策に基づいているため、社会情勢や政策方針によって変更される可能性があることを理解しておく必要があります。
- 10kW未満(住宅用)の買取期間は10年間
- 10kW以上(産業用)の買取期間は20年間
- 買取期間は売電開始日から計算される
- 満了日は契約開始月から数えた年数の月末
- 満了通知を見落とさないよう注意が必要
- 制度変更のリスクにも留意する
自分の太陽光発電がいつ満了を迎えるのか、正確に把握しておくことが最初のステップです。
契約書類を確認し、満了予定日をカレンダーに記入しておくことをお勧めします。
また、買取期間中であっても、定期的に制度の最新情報をチェックする習慣をつけることで、予期せぬトラブルを避けることができるでしょう。
申し込み〜運用の実務ポイント

開始前に確認する書類・通知とスケジュール管理(満了通知の見方)
太陽光発電のFIT制度を活用するには、複数の書類と通知を適切に管理することが不可欠です。
まず設置時に受け取る重要書類として、「再生可能エネルギー発電設備認定通知書」があります。
これは経済産業省(資源エネルギー庁)から発行される公式書類で、あなたの太陽光発電設備がFIT制度の対象として認定された証明となります。
この通知書には、認定日、設備ID、買取価格、買取期間などの基本情報が記載されています。
認定通知書は紛失すると再発行に時間がかかるため、必ず大切に保管してください。
次に、電力会社との間で交わす「電力受給契約」に関する書類があります。
これは実際に電気を売買するための契約書で、買取価格や契約期間、振込口座などの具体的な条件が明記されています。
契約書の控えは、満了後の契約更新や変更時にも参照する重要な資料となります。
また、年度が替わるタイミングで電力会社から「購入電力量のお知らせ」が届くことがあります。
これは年間でどれだけの電力を売電したかを示す明細で、確定申告が必要な場合の根拠資料にもなります。
売電収入が年間20万円を超える場合は確定申告の対象となるため、この明細は税務処理でも重要です。
そして最も見落としやすいのが、**買取期間満了の数か月前に届く「満了通知」**です。
この通知は電力会社から郵送で届きますが、一般的なダイレクトメールと混同して捨ててしまうケースが後を絶ちません。
満了通知には以下の情報が記載されています。
- 現在の契約の満了予定日
- 満了後の買取価格の提案(もしある場合)
- 契約継続または変更の手続き方法
- 手続きの期限
- 問い合わせ先
特に重要なのは、満了後も同じ電力会社で売電を継続する場合でも、新たな契約手続きが必要という点です。
何もしなければ自動継続されると勘違いしている方が多いのですが、実際には新規契約として扱われます。
満了通知が届くタイミングは電力会社によって異なりますが、一般的には満了日の3〜6か月前です。
この時期を逃さないために、自分で満了予定日の半年前にリマインダーを設定しておくことをお勧めします。
スマートフォンのカレンダーアプリや、手帳に書き込んでおくだけでも効果的です。
|
書類・通知の種類 |
発行元 |
重要度 |
保管期限 |
|
認定通知書 |
経済産業省 |
★★★ |
永久保管 |
|
電力受給契約書 |
電力会社 |
★★★ |
契約終了後5年 |
|
購入電力量の明細 |
電力会社 |
★★☆ |
7年間(税務用) |
|
満了通知 |
電力会社 |
★★★ |
手続き完了まで |
満了通知の見方についても具体的に解説します。
通知書の冒頭には「買取期間満了のご案内」などのタイトルが付いていることが多く、現在の契約番号や設備の情報が確認できる部分があります。
まずこの情報が自分の太陽光発電設備と一致しているかを確認しましょう。
次に、満了日が明記されている箇所を見つけます。
「○○年○月○日をもって買取期間が満了します」といった表現で書かれています。
この日付以降は、現在の買取価格での売電ができなくなります。
そして、満了後の選択肢として提示されている内容を確認します。
多くの電力会社は、満了後も引き続き買い取る場合の新しい単価を提示してくれます。
ただし、この単価はFIT期間中の価格と比べて大幅に低くなることが一般的です。
たとえば、FIT期間中は42円/kWhだったものが、満了後は7〜10円/kWh程度になることもあります。
通知書の最後には、手続きの方法や期限が記載されています。
「○月○日までに同封の申込書を返送してください」「Webサイトから手続きが可能です」など、具体的なアクションが求められる内容を見落とさないようにしましょう。
もし満了通知が届かない場合や、紛失してしまった場合は、すぐに電力会社のお客様センターに連絡してください。
再発行や電話での案内を受けることができます。
- 満了予定日の半年前にリマインダーを設定する
- 満了通知が届いたらすぐに内容を確認する
- 新しい買取単価と期限を把握する
- 不明点があればすぐに電力会社に問い合わせる
- 書類は写真を撮ってデジタル保存しておく
書類管理とスケジュール管理は、卒FIT対応の成否を左右する重要な実務ポイントです。
面倒に感じるかもしれませんが、これらの手続きを適切に行うことで、満了後もスムーズに最適な選択肢を選ぶことができます。
満了直前にやることチェック(売電先・契約条件の比較)
買取期間の満了が近づいたら、少なくとも満了3か月前から具体的な準備を始める必要があります。
この時期に何をするかで、満了後の経済性が大きく変わってきます。
まず最初にやるべきことは、現在の電力会社から提示された条件を正確に把握することです。
満了通知に記載されている新しい買取単価、契約期間、その他の条件をメモしておきましょう。
これが比較検討の基準となります。
次に、他の売電先の選択肢を調べます。
卒FIT後の売電先は、従来の電力会社に限定されません。
新電力会社や自治体が運営する地域新電力など、複数の事業者が卒FIT電力の買取サービスを提供しています。
これらの事業者の買取条件を比較することで、より有利な条件を見つけられる可能性があります。
比較する際のポイントは以下の通りです。
- 買取単価(円/kWh)
- 契約期間(1年更新か複数年契約か)
- 契約の解除条件や違約金の有無
- 支払いサイクル(毎月か年2回か)
- 付帯サービスの有無(電気料金プランとのセット割引など)
買取単価については、各社のWebサイトや比較サイトで確認できます。
一般的な相場としては、2024年時点で7〜12円/kWh程度が主流となっています。
ただし、地域や事業者によって差があるため、自分の地域で利用可能なサービスを調べることが重要です。
契約期間も見落としやすいポイントです。
1年ごとの自動更新型の契約なら、翌年により良い条件が出た場合に乗り換えやすくなります。
一方、複数年の契約で若干高い単価を保証する事業者もあります。
自分のライフプランや運用方針に合った契約形態を選ぶことが大切です。
また、売電だけでなく「電気の購入契約」とセットで考えることも有効です。
多くの新電力会社は、卒FIT電力の買取と電気料金プランをセットで提供しており、両方を同じ会社にすることで割引が適用されるケースがあります。
たとえば、売電単価が8円/kWhの会社Aと、売電単価が9円/kWhの会社Bがあったとします。
一見すると会社Bの方が有利に見えますが、会社Aで電気購入契約もセットにすると電気代が月額1,000円安くなる場合、トータルでは会社Aの方が得になる可能性があります。
このように、個別の条件だけでなく、総合的な経済性を計算することが重要です。
|
比較項目 |
従来の電力会社 |
新電力会社A |
新電力会社B |
|
買取単価 |
7.5円/kWh |
9.0円/kWh |
8.5円/kWh |
|
契約期間 |
1年自動更新 |
1年自動更新 |
3年固定 |
|
電気料金割引 |
なし |
月500円割引 |
月300円割引 |
|
その他特典 |
なし |
ポイント付与 |
地域貢献 |
実際に比較する際は、年間の予想発電量をもとに試算してみましょう。
たとえば、年間4,000kWhの余剰電力を売電する場合、単価1円の差でも年間4,000円の収入差になります。
さらに電気料金の割引が年間12,000円あれば、トータルで年間16,000円の差額が生まれます。
満了直前にやることのチェックリストをまとめると以下のようになります。
- 現在の電力会社から届いた満了通知の内容を確認する
- 複数の新電力会社の買取条件を調査する
- 買取単価だけでなく契約条件全体を比較する
- 年間の予想売電量をもとに収入を試算する
- 電気購入契約とのセット割引も検討する
- 最も有利な選択肢を決定する
- 必要な申し込み手続きを期限内に完了する
- 契約切り替えがスムーズに行われるか確認する
特に注意したいのは、新しい契約の申し込み期限です。
満了日ギリギリに申し込むと、手続きが間に合わず一時的に売電ができなくなる可能性があります。
理想的には満了日の1〜2か月前には新しい契約を完了させておくべきです。
また、複数の事業者に同時に申し込むことはできません。
どこか一社と契約することになるため、慎重に比較検討してから決定するようにしましょう。
もし判断に迷う場合は、各社のカスタマーサポートに相談することもできます。
自分の発電量や使用状況を伝えれば、具体的なシミュレーションを提供してくれる事業者もあります。
売電先の選択は、卒FIT後の経済性を左右する最も重要な判断です。
手間を惜しまず、複数の選択肢を比較検討することで、満了後も太陽光発電のメリットを最大限に享受できるでしょう。
卒FIT後のベスト選択肢

自家消費強化(蓄電池・EV/V2H活用)の考え方と効果
卒FIT後の選択肢として、近年最も注目を集めているのが自家消費の強化という考え方です。
FIT期間中は高い単価で売電できたため、できるだけ多くの電気を売ることが経済的に合理的でした。
しかし卒FIT後は買取単価が大幅に下がる一方で、電力会社から購入する電気の単価は上昇し続けています。
この状況では、太陽光で発電した電気をできるだけ自宅で使う方が経済的メリットが大きいのです。
具体的な数字で見てみましょう。
卒FIT後の売電単価が8円/kWhだとします。
一方、電力会社から電気を購入する単価は30円/kWh前後が一般的です。
もし太陽光発電の電気1kWhを売電せずに自宅で使えば、購入する電気が1kWh減ります。
つまり、8円の収入を得る代わりに30円の支出を削減できるため、実質的に22円分の経済効果があることになります。
この考え方に基づいて、自家消費を最大化する方法として注目されているのが蓄電池の導入です。
太陽光発電は日中にしか発電しませんが、家庭の電力消費は夕方から夜にかけてピークを迎えます。
日中に発電した電気を蓄電池に貯めておけば、夜間にも太陽光の電気を使うことができるのです。
蓄電池の容量は一般的な住宅用で5〜10kWh程度が主流です。
5kWhの蓄電池があれば、平均的な家庭の夕方から夜間の消費電力をカバーできます。
導入費用は容量や性能によって異なりますが、2024年時点で100万〜200万円程度が相場となっています。
蓄電池導入のメリットは経済性だけではありません。
災害時の非常用電源として活用できるという大きな利点もあります。
地震や台風などで停電が発生しても、蓄電池があれば冷蔵庫やスマートフォンの充電、照明など、最低限の電力を確保できます。
近年の災害の増加を考えると、この防災機能は無視できない価値です。
蓄電池導入の経済効果をシミュレーションしてみましょう。
1日あたり5kWhを蓄電池経由で自家消費すると仮定します。
- 購入電気の削減: 5kWh × 30円 = 150円/日
- 売電収入の減少: 5kWh × 8円 = 40円/日
- 正味のメリット: 150円 – 40円 = 110円/日
- 年間メリット: 110円 × 365日 = 40,150円
この計算では年間約4万円の経済メリットが生まれます。
150万円の蓄電池を導入した場合、単純計算で約37年の回収期間となり、一見すると長く感じられます。
しかし、電気料金の上昇傾向や災害対策の価値を加味すると、実質的な回収期間はより短くなると考えられます。
|
項目 |
蓄電池なし |
蓄電池あり |
|
日中の余剰電力 |
売電(8円/kWh) |
蓄電 |
|
夜間の電力 |
購入(30円/kWh) |
蓄電池から使用 |
|
経済効果 |
– |
差額22円/kWh分 |
|
災害時 |
停電で使えず |
自立運転可能 |
次に、電気自動車(EV)とV2H(Vehicle to Home)システムの活用について解説します。
EVとV2Hを組み合わせることで、車のバッテリーを巨大な蓄電池として利用できるという革新的なシステムです。
一般的なEVのバッテリー容量は40〜60kWhと、家庭用蓄電池の5〜10倍以上の容量があります。
V2Hシステムを導入すれば、日中に太陽光で発電した電気をEVに充電し、夜間にEVから家庭に電気を供給することができます。
この方法の大きなメリットは、すでにEVを所有している場合、V2H機器の導入だけで済むという点です。
V2H機器の価格は80万〜150万円程度で、専用の蓄電池を買うよりも初期投資を抑えられる可能性があります。
さらに、EVは移動手段としても使えるため、災害時には避難所への移動電源や、他の場所での電力供給源としても活用できます。
実際に災害時にEVが地域の電力供給拠点として機能した事例も報告されています。
ただし、EVとV2Hの活用には注意点もあります。
車を日中に使うことが多い場合、太陽光発電の電気を充電できる時間が限られます。
また、EVのバッテリーは使用とともに劣化するため、頻繁に充放電を繰り返すと車両の資産価値に影響する可能性があります。
自家消費強化の選択肢として、蓄電池とEV/V2Hのどちらを選ぶかは、それぞれの生活スタイルによって異なります。
- 家にいることが多く、日中の発電を最大限活用したい → 蓄電池
- すでにEVを所有しており、追加投資を抑えたい → V2H
- まだEVは持っていないが、将来的に購入予定 → 蓄電池とEVの両方を検討
- 予算が限られている → より小容量の蓄電池からスタート
自家消費強化のもう一つの方法として、家電の使用時間を調整するという簡単な方法もあります。
洗濯機や食洗機など、使用する時間帯が自由な家電を、太陽光が発電している日中に使うようにするだけでも、自家消費率を高めることができます。
これは設備投資が不要で、今日からでも実践できる方法です。
また、エコキュートなどの給湯機を太陽光発電の時間帯に動作させる設定にすることで、大きな電力消費を太陽光でまかなうこともできます。
自家消費強化は、卒FIT後の太陽光発電を最大限に活用する有力な選択肢です。
初期投資は必要ですが、長期的な経済メリットと災害対策を両立できる点で、多くの家庭にとって検討する価値があるでしょう。
相対・自由契約での売電(新電力・自治体新電力の活用)
卒FIT後のもう一つの大きな選択肢が、新電力会社や自治体新電力との相対契約による売電です。
FIT制度の買取とは異なり、売電先を自由に選べるため、より有利な条件を探すことができます。
相対契約とは、発電者と電力事業者が直接交渉して決める契約形態のことです。
FIT制度のように国が価格を決めるのではなく、双方が合意した条件で契約を結ぶ自由度の高い仕組みとなっています。
新電力会社とは、2016年の電力小売全面自由化以降に電力小売事業に参入した事業者のことです。
従来の大手電力会社(東京電力、関西電力など)以外にも、多くの企業が電力販売を行うようになりました。
これらの新電力会社の多くが、卒FIT後の太陽光発電の電気を買い取るサービスを提供しています。
新電力会社の買取単価は、事業者によって大きく異なります。
一般的には7円〜12円/kWh程度が相場ですが、中には環境価値を重視して高めの単価を設定している事業者もあります。
たとえば、再生可能エネルギーの普及に力を入れている新電力会社では、10円/kWh以上の単価を提示しているケースもあります。
新電力会社を選ぶ際の比較ポイントは以下の通りです。
- 買取単価の水準
- 契約期間と更新条件
- 電気購入契約とのセット割引
- 企業理念や環境への取り組み
- サービスの安定性と実績
- カスタマーサポートの質
単純に買取単価だけで選ぶのではなく、総合的なサービス内容を評価することが重要です。
たとえば、買取単価が若干低くても、電気購入契約をセットにすることで電気料金が大幅に安くなり、トータルではお得になるケースがあります。
また、企業の環境方針に共感できる事業者を選ぶことで、自分の太陽光発電が地域の再生可能エネルギー推進に貢献している実感を得られるという精神的なメリットもあります。
|
新電力会社の種類 |
特徴 |
代表例 |
|
総合エネルギー企業系 |
大規模で安定性が高い |
○○ガス、○○石油 |
|
通信・IT企業系 |
通信サービスとのセット割引 |
○○モバイル、○○通信 |
|
地域密着型 |
地域貢献や環境重視 |
○○電力、○○エナジー |
|
再エネ特化型 |
高い買取単価や環境価値 |
○○自然エネルギー |
次に、自治体新電力について解説します。
自治体新電力とは、地方自治体が主体となって設立した電力小売事業者のことです。
近年、地域のエネルギー自給率向上や地域経済の活性化を目的として、多くの自治体が電力事業に参入しています。
自治体新電力の大きな特徴は、地域で生まれた再生可能エネルギーを地域で消費する「地産地消」の考え方です。
卒FIT後の太陽光発電の電気を買い取り、それを地域の公共施設や住民に供給することで、地域内でエネルギーが循環する仕組みを作っています。
自治体新電力に売電するメリットは、買取単価だけではありません。
地域への貢献という社会的な意義も大きな魅力です。
あなたの太陽光発電が、地域の学校や病院、公共施設で使われると考えると、発電へのモチベーションも高まります。
また、自治体新電力の多くは、収益の一部を地域の環境事業や福祉事業に還元しています。
売電することが間接的に地域社会に貢献することにつながるのです。
自治体新電力の買取単価は、一般的な新電力会社と同程度か、やや高めに設定されているケースが多く見られます。
地域によっては10円/kWh以上の単価を提示している自治体もあります。
ただし、自治体新電力は全国すべての地域にあるわけではありません。
自分の住んでいる地域に自治体新電力があるかどうか、まず確認する必要があります。
- 自分の自治体で電力事業を行っているか調べる
- 自治体新電力のWebサイトで卒FIT買取サービスを確認する
- 買取単価や契約条件を確認する
- 地域貢献の仕組みや活動内容を理解する
- 申し込み方法と必要書類を準備する
相対契約での売電を選ぶ際には、契約内容をよく確認することも重要です。
特に注意すべきポイントは以下の通りです。
- 契約期間中の価格変動条項: 市場価格の変動に応じて買取単価が変わる場合がある
- 最低契約期間: 短期間での解約ができない場合がある
- 解約時の違約金: 契約期間中に解約すると違約金が発生する場合がある
- 支払い条件: 月払いか年払いか、振込手数料はどちらが負担するか
これらの条件を事前に確認し、納得した上で契約することが大切です。
また、複数の事業者の条件を比較する際には、年間の売電量をもとに実際の収入を試算することをお勧めします。
たとえば、年間3,000kWhの余剰電力がある場合、買取単価が1円違うだけで年間3,000円の差が生まれます。
5年間で15,000円、10年間で30,000円と、長期的には大きな差になります。
相対契約での売電は、卒FIT後も安定した収入を得ながら、環境や地域に貢献できる選択肢です。
自分の価値観やライフスタイルに合った事業者を選ぶことで、満足度の高い卒FIT生活を送ることができるでしょう。
トラブル回避と最新情報の取り方
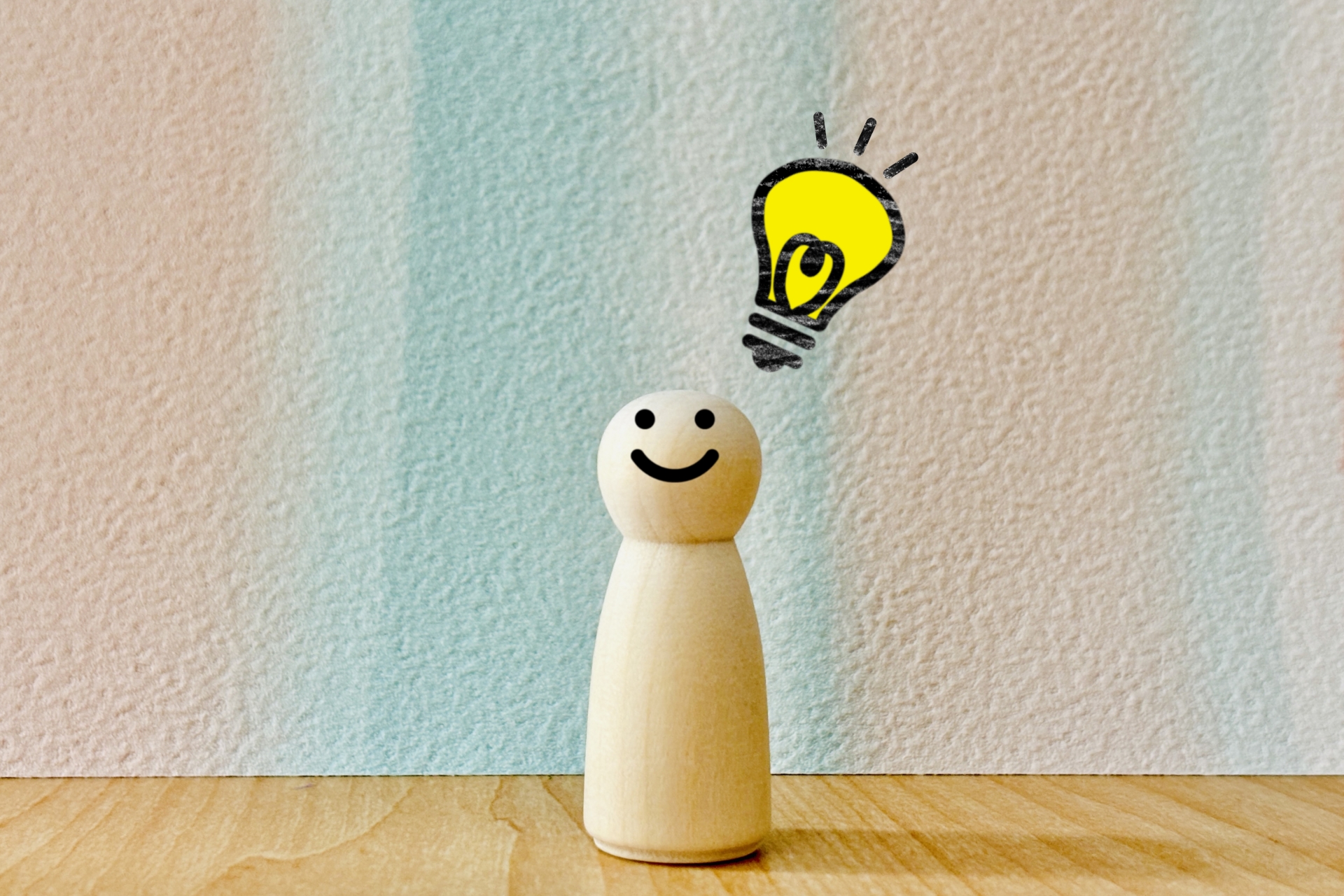
悪質勧誘への注意と公式FAQ・相談窓口の活用法
卒FIT後の太陽光発電オーナーを狙った悪質な勧誘や詐欺まがいの営業が増加していることをご存知でしょうか。
買取期間の満了を迎える家庭が増えるにつれて、不安や情報不足につけ込む業者が増えているのが実情です。
典型的な悪質勧誘のパターンをいくつか紹介します。
まず、「今すぐ契約しないと売電できなくなる」という緊急性を煽る手法です。
実際には卒FIT後も複数の選択肢があり、慌てて契約する必要はまったくありません。
こうした焦らせる言葉には十分注意してください。
次に、「当社だけの特別単価で買い取ります」と高額な買取価格を提示する手口があります。
相場を大きく上回る単価を提示し、実際には不透明な手数料や条件が隠されているケースがあります。
また、「蓄電池を設置すれば売電単価が上がる」といった根拠のない説明をして、高額な設備を売りつける悪質業者も存在します。
蓄電池には自家消費強化のメリットはありますが、それによって売電単価が変わることは通常ありません。
訪問販売や電話営業で不審な勧誘を受けた場合の対処法は以下の通りです。
- その場で契約や返事をしない
- 会社名や連絡先を確認し、後で調べる
- 複数の事業者と比較検討する時間を取る
- 不安を感じたら家族や専門家に相談する
- 必要に応じてきっぱりと断る
特に高齢者の方がターゲットにされやすいため、ご家族で情報を共有し、怪しい勧誘には家族で対応する体制を作っておくことをお勧めします。
もし悪質な勧誘を受けた場合や、すでに契約してしまって不安がある場合は、以下の公式相談窓口を活用してください。
|
相談窓口 |
電話番号 |
対応内容 |
|
消費者ホットライン |
188(いやや) |
消費者トラブル全般の相談 |
|
国民生活センター |
各地の消費生活センター |
契約トラブル、返金相談 |
|
経済産業省 なっとく再生可能エネルギー |
Web・電話対応 |
FIT制度に関する質問 |
|
各電力会社カスタマーセンター |
各社ホームページ参照 |
契約内容の確認 |
消費者ホットライン(188)は、全国どこからでも最寄りの消費生活センターにつながる便利な窓口です。
契約してしまった後でも、クーリングオフ制度を利用できる場合があります。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。
この期間内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できます。
クーリングオフを行う際は、必ず書面(ハガキまたは内容証明郵便)で通知してください。
電話や口頭での通知は法的効力がないため、後でトラブルになる可能性があります。
一方、信頼できる情報源として活用すべきなのが、経済産業省が運営する「なっとく再生可能エネルギー」のWebサイトです。
このサイトには、FIT制度に関する公式のFAQが充実しており、よくある質問とその回答が掲載されています。
- FIT制度の基本的な仕組み
- 買取期間満了後の手続き
- 制度変更に関する最新情報
- トラブル事例と対処法
- 事業者の認定状況の確認方法
特に「よくある質問」のページでは、実際に多くの人が抱える疑問に対する正確な回答を得ることができます。
業者から聞いた情報が正しいかどうか不安な場合は、このサイトで確認することをお勧めします。
また、電力会社の公式WebサイトにもFAQページが用意されています。
契約内容や手続きに関する具体的な疑問は、まず電力会社のFAQを確認することで、多くの場合解決できます。
それでも分からない場合は、カスタマーセンターに電話で問い合わせることができます。
- 疑問に思ったらまず公式情報を確認する
- 業者の説明だけを鵜呑みにしない
- 複数の情報源で内容を確認する
- 家族や信頼できる人に相談する
- 公式の相談窓口を積極的に利用する
トラブルを未然に防ぐためには、正しい知識を持つことが最も重要です。
この記事で解説している基本的な知識を身につけておくだけでも、悪質な勧誘を見抜く力が養われます。
また、何か不安なことがあれば一人で抱え込まず、公式の相談窓口や家族に相談することで、多くのトラブルは回避できます。
あなたの太陽光発電を守るため、正しい情報と信頼できる相談先を味方につけましょう。
「どうする?ソーラー」で最新メニューと選択肢を確認する
卒FIT後の選択肢について、より具体的で最新の情報を得るために活用したいのが、資源エネルギー庁が提供する「どうする?ソーラー」というWebサービスです。
このサービスは、卒FIT後の太陽光発電オーナーに向けて、各電力会社や新電力会社が提供している買取メニューをまとめて比較できる便利なプラットフォームです。
「どうする?ソーラー」の最大の特徴は、自分の地域で利用可能なすべての買取サービスを一覧で確認できるという点です。
地域を選択すると、その地域で卒FIT電力の買取を行っている事業者がリストアップされ、各社の買取単価や契約条件を簡単に比較できます。
このサービスの具体的な使い方を解説します。
まず、「どうする?ソーラー」のWebサイトにアクセスします。
検索エンジンで「どうする ソーラー」と入力すれば、資源エネルギー庁の公式ページが見つかります。
トップページには、卒FIT後の選択肢に関する基本的な情報や、制度の概要が分かりやすく説明されています。
「買取メニューを探す」というボタンをクリックすると、地域選択画面に移動します。
ここで自分が住んでいる都道府県を選択すると、その地域で利用可能な買取事業者の一覧が表示されます。
一覧には以下の情報が掲載されています。
- 事業者名
- 買取単価(円/kWh)
- 契約期間
- 電気購入契約とのセット条件
- 申し込み方法(Web・電話・郵送)
- 事業者のWebサイトへのリンク
各事業者の情報は定期的に更新されているため、常に最新の買取条件を確認できるのが大きなメリットです。
買取単価は市場状況や各社の戦略によって変動することがあるため、定期的にチェックすることをお勧めします。
|
地域 |
事業者数 |
買取単価の幅 |
特徴的なサービス |
|
関東 |
25社以上 |
7.0〜11.0円/kWh |
通信サービス連携が充実 |
|
関西 |
20社以上 |
7.5〜10.5円/kWh |
地域新電力が多い |
|
中部 |
18社以上 |
7.0〜10.0円/kWh |
ガス会社系が強い |
|
九州 |
15社以上 |
8.0〜11.5円/kWh |
再エネ特化型が多い |
「どうする?ソーラー」では、買取以外の選択肢についても情報が提供されています。
自家消費を強化したい場合に参考になる蓄電池の情報や、環境価値の活用方法などについても解説されています。
さらに、サイト内には「よくある質問」のコーナーもあり、卒FIT後の手続きに関する疑問に答えてくれます。
- 満了通知が届かない場合の対処法
- 契約変更の手続き方法
- 複数の事業者を比較する際のポイント
- トラブルが発生した場合の相談先
これらの情報は、すべて公式の情報源に基づいているため、信頼性が高く安心して参考にできます。
「どうする?ソーラー」を活用する際の注意点もあります。
サイトに掲載されている情報は、各事業者から提供された内容を整理したものです。
最終的な契約条件や詳細については、必ず各事業者のWebサイトや問い合わせで直接確認することが重要です。
また、サイトに掲載されていない小規模な地域事業者や、新規参入した事業者の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。
可能であれば、「どうする?ソーラー」の情報に加えて、自分でも独自に情報収集を行うとより良い選択ができます。
「どうする?ソーラー」の活用手順をまとめると以下のようになります。
- 資源エネルギー庁の「どうする?ソーラー」にアクセスする
- 自分の地域を選択して利用可能な事業者を確認する
- 買取単価や契約条件を比較する
- 気になる事業者を2〜3社ピックアップする
- 各事業者のWebサイトで詳細情報を確認する
- 必要に応じて問い合わせや資料請求をする
- 最終的な判断をして申し込みを行う
このサービスは、国が卒FIT後の太陽光発電オーナーを支援するために提供している公式サービスです。
民間の比較サイトとは異なり、特定の事業者への誘導や広告はなく、中立的な情報が得られます。
卒FIT後の選択肢に迷ったら、まず「どうする?ソーラー」で情報収集を始めることをお勧めします。
また、このサービスは定期的に内容が更新されているため、満了が近づいたタイミングで何度か訪問して、最新の選択肢を確認することが有効です。
「どうする?ソーラー」を活用することで、情報収集の時間を大幅に短縮でき、より効率的に最適な選択肢を見つけることができるでしょう。
公式の情報源を味方につけて、自信を持って卒FIT後の選択をしましょう。
まとめ

太陽光発電のFIT制度について、基本的な仕組みから卒FIT後の選択肢まで、幅広く解説してきました。
FIT制度は、固定価格での買取を10年または20年間保証することで、太陽光発電の普及を促進してきた重要な制度です。
しかし、買取期間の満了後は新たな判断が必要になります。
まず重要なのは、満了時期を正確に把握し、満了通知を見落とさないことです。
満了の数か月前から、複数の売電先の条件を比較検討し、自分に最適な選択肢を見つける準備を始めましょう。
卒FIT後の選択肢は大きく分けて2つあります。
一つは、新電力会社や自治体新電力と契約して売電を継続する方法です。
買取単価は従来より下がりますが、事業者を比較することでより有利な条件を見つけることができます。
もう一つは、蓄電池やEV/V2Hを活用して自家消費を強化する方法です。
電気料金の削減効果に加えて、災害時の備えとしても価値がある選択肢です。
どちらを選ぶかは、あなたのライフスタイルや価値観によって異なります。
経済性だけでなく、環境への貢献や地域への貢献といった要素も含めて、総合的に判断することが大切です。
トラブルを避けるためには、悪質な勧誘に注意し、公式の情報源を活用することが重要です。
「どうする?ソーラー」などの公式サービスを使えば、信頼できる最新情報を効率的に収集できます。
卒FITは終わりではなく、新しい選択肢が広がる転換点です。
この記事で紹介した知識を活用して、あなたの太陽光発電を最大限に活かしてください。
適切な準備と判断によって、卒FIT後も長く太陽光発電のメリットを享受できることを願っています。
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。






