お役立ちコラム 2025.04.22
系統用蓄電池の仕組みとビジネスモデル – 利益の出し方を解説
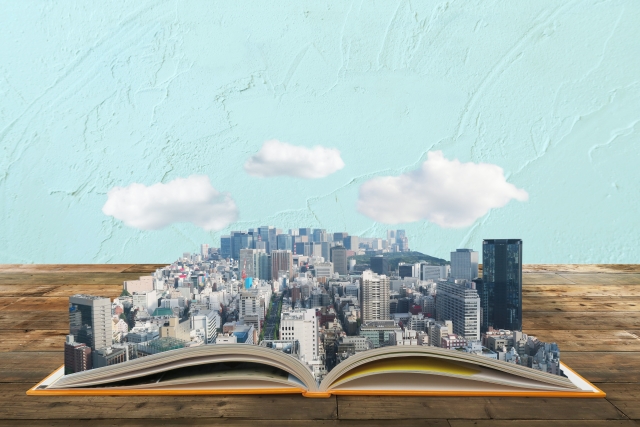
目次
系統用蓄電池の役割と注目される理由

電力系統の安定化への貢献
系統用蓄電池は、電力系統の安定化に重要な役割を果たしています。
電力の需要と供給のバランスを常に保つことは、安定した電力供給には不可欠です。
しかし、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、天候によって発電量が変動しやすくなっているのが現状です。
そこで、系統用蓄電池が活躍します。
電力が余っているときに充電し、足りないときに放電することで、需給バランスを調整できるのです。
また、周波数調整や電圧調整といった、電力品質の維持にも貢献しています。
このように、系統用蓄電池は、電力系統の安定化に欠かせない存在となっているのです。
再生可能エネルギーの導入拡大への寄与

系統用蓄電池は、再生可能エネルギーの導入拡大にも大きく寄与しています。
太陽光発電や風力発電は、天候に左右されるため、発電量が不安定になりがちです。
これでは、電力系統に大量に接続することが難しくなります。
しかし、系統用蓄電池を活用すれば、再生可能エネルギーの変動を吸収し、安定的に電力系統に供給することができるのです。
また、再生可能エネルギーの余剰電力を蓄電池に蓄えておくことで、無駄なく活用することも可能です。
このように、系統用蓄電池は、再生可能エネルギーの導入拡大に欠かせない技術となっています。
電力市場の変化と新たなビジネスチャンス

近年、電力自由化が進み、電力市場は大きく変化しています。
これに伴い、系統用蓄電池を活用した新たなビジネスチャンスも生まれています。
例えば、電力価格の変動を利用して、安い時間帯に充電し、高い時間帯に放電することで、収益を得ることができます。
また、需給調整市場や容量市場といった新しい市場でも、系統用蓄電池の活躍が期待されています。
需給調整市場では、電力の需給バランス調整に貢献することで報酬を得られます。
容量市場では、電力供給能力を提供することで、安定的な収益を確保できる可能性があります。
このように、系統用蓄電池は、電力市場の変化に対応した新たなビジネスモデルを生み出しているのです。
系統用蓄電池を活用した主な取引市場
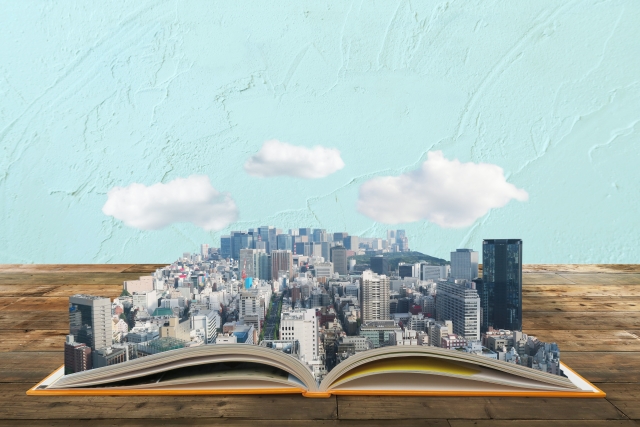
電力卸売市場での価格差を利用した取引
系統用蓄電池を活用した取引の中で、最も一般的なのが電力卸売市場での価格差を利用した取引です。
この市場では、電力の需要と供給のバランスによって、電力価格が刻々と変動しています。
系統用蓄電池は、この価格変動を巧みに利用することで、収益を上げることができるのです。
安値時に充電、高値時に放電することで利益を獲得
具体的には、以下のような運用が行われます。
– 電力価格が安い時間帯(主に深夜から早朝)に、安価な電力を購入して蓄電池に充電する
– 電力価格が高騰する時間帯(主に日中から夕方)に、蓄電池に蓄えた電力を高値で売電する
– この「安く買って、高く売る」という価格差を利用することで、利益を得るのです
実際、電力価格の変動幅が大きい日などは、1日の中だけでも数十円/kWhもの価格差が生じることがあります。
系統用蓄電池は、この価格差を的確に捉えて運用することで、大きな収益を上げられる可能性を秘めているのです。
精度の高い需要予測と最適な運用が鍵
ただし、この取引を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
まず、精度の高い電力需要予測が欠かせません。
電力価格は需要と供給のバランスで決まるため、正確な需要予測なくしては、適切なタイミングでの充放電は難しいでしょう。
また、蓄電池の特性を理解し、最適な運用を行うことも重要です。
充放電のタイミングや回数、充電状態の管理など、細かな運用の工夫が求められます。
加えて、電力市場の制度変更やルールの把握も欠かせません。
これらを総合的に勘案し、収益を最大化する運用を実現することが、この取引の鍵となるのです。
容量市場での電力供給能力の提供

もう一つの主要な取引市場が、容量市場です。
容量市場とは、将来の電力需要に対して、十分な供給力を確保するために設けられた市場のことを指します。
この市場では、電力供給能力を提供することで、報酬を得ることができます。
系統用蓄電池は、発電所と同様に、この容量市場に参加することができるのです。
具体的には、一定期間、一定の出力を提供できる契約を結ぶことで、容量の提供に対する報酬を得られます。
この報酬は、kWに対して支払われるため、蓄電池の容量に応じた収入を安定的に得られるのが特徴です。
また、実際に電力を供給しなくても、供給可能な状態を維持していれば報酬を得られるため、電力卸売市場とは異なるメリットがあるとも言えるでしょう。
ただし、容量市場には一定の参加条件があり、要件を満たす必要があります。
例えば、一定の供給力を一定期間提供できることや、指令に応じて速やかに供給できることなどが求められます。
系統用蓄電池は、その機動性の高さから、これらの条件を満たしやすいと言えますが、適切な運用体制の構築は欠かせません。
容量市場は、系統用蓄電池にとって、新たな収益源となる有望な市場の一つと言えるでしょう。
一定期間の電力供給能力を約束し、安定収益を確保
容量市場では、系統用蓄電池は一定期間、一定の電力供給能力を提供することを約束します。
この約束に基づいて、電力供給能力に対する報酬が支払われるのです。
この報酬は、実際に電力を供給したかどうかにかかわらず、約束した容量を提供できる状態を維持していれば受け取ることができます。
つまり、容量市場への参加は、系統用蓄電池にとって安定的な収益源となるのです。
容量の提供期間や報酬額は、通常、オークションを通じて決定されます。
長期的な収益の見通しを立てやすいのも、容量市場の魅力の一つと言えるでしょう。
調整力の提供による追加収入の可能性
容量市場への参加は、電力供給能力の提供が主目的ですが、それ以外の収益機会もあります。
その一つが、調整力の提供です。
調整力とは、電力需給のバランスを保つために、短時間で出力を調整できる能力のことを指します。
系統用蓄電池は、その高い応答性から、この調整力の提供に適しているのです。
実際に調整力の提供が求められた場合、追加の報酬を得られる可能性があります。
この追加収入は、容量市場の収益に上乗せされるため、収益性をさらに高めることができるでしょう。
ただし、調整力の提供には、より高度な制御技術が必要とされます。
適切な設備と運用体制の構築が、この追加収益を得るための鍵となります。
需給調整市場での周波数調整への参加

系統用蓄電池が参加できるもう一つの重要な市場が、需給調整市場です。
この市場では、電力系統の周波数を一定に保つために、リアルタイムで電力の需給バランスを調整する取引が行われています。
周波数は、電力の需要と供給のバランスが崩れると変動します。
この変動を抑え、一定の範囲内に保つことが、安定的な電力供給には欠かせません。
系統用蓄電池は、その高速な応答性を活かして、この周波数調整に貢献できるのです。
電力需給のアンバランスを解消し、報酬を獲得
需給調整市場では、電力の需要と供給の予測がずれた場合に生じる、電力需給のアンバランスを解消するための調整力が取引されます。
具体的には、以下のようなケースが想定されます。
・予測よりも需要が多く、供給が不足した場合 → 系統用蓄電池が放電して不足分を補う
・予測よりも需要が少なく、供給が余った場合 → 系統用蓄電池が充電して余剰分を吸収する
このように、系統用蓄電池は電力需給のアンバランスを解消することで、電力系統の安定化に寄与します。
そして、その貢献に対して、市場から報酬を得ることができるのです。
報酬額は、調整力の提供量や応答の速さなどに応じて決定されます。
需給調整市場は、系統用蓄電池の特性を最大限に活かせる市場と言えるでしょう。
高速応答性と制御技術が重要
ただし、需給調整市場で成功するためには、いくつかの重要な要素があります。
まず、高速な応答性が求められます。
電力需給のアンバランスは、秒単位で変動します。
これに対応するためには、速やかに充放電を行える性能が不可欠です。
また、精緻な制御技術も欠かせません。
需給調整市場では、系統運用者からの指令に基づいて、正確な量の電力を調整する必要があります。
そのためには、蓄電池の状態を適切に管理し、最適な制御を行う技術が求められるのです。
さらに、需給調整は24時間365日、絶え間なく行われるため、高い稼働率も必要です。
系統用蓄電池の設計と運用は、これらの要求を満たすことができるよう、綿密に計画されなければなりません。
需給調整市場は、系統用蓄電池にとって魅力的な収益機会である一方、高度な技術力も求められる市場なのです。
系統用蓄電池の導入を支援する補助金制度

系統用蓄電池は、電力系統の安定化や再生可能エネルギーの導入拡大に大きく貢献する技術です。
しかし、その導入には多額の初期投資が必要となるため、事業者にとっては大きな負担となります。
そこで、国や自治体では、系統用蓄電池の導入を支援するための補助金制度を設けています。
これらの制度を活用することで、事業者の初期投資負担を軽減し、系統用蓄電池の普及を後押しすることができるのです。
ここでは、系統用蓄電池の導入に活用できる主な補助金・助成金制度と、その申請方法や留意点について解説します。
国や自治体の補助金・助成金の概要
系統用蓄電池の導入に対する補助金・助成金制度は、国と地方自治体の両方で設けられています。
まず、国レベルでは、経済産業省が「エネルギー対策特別会計」の一部を活用した補助金制度を設けています。
この制度では、一定の要件を満たす系統用蓄電池の導入に対して、初期費用の一部を補助します。
補助率や上限額は年度によって異なりますが、通常、数千万円から数億円規模の補助が受けられます。
また、地方自治体でも、独自の補助金・助成金制度を設けているところがあります。
例えば、東京都では「東京都地産地消型再エネ増強プロジェクト」の一環として、系統用蓄電池の導入に対する補助制度を設けています。
この制度では、都内で再生可能エネルギーを活用する事業者に対し、蓄電池システムの導入費用の一部を補助しています。
このように、国と地方自治体の補助金・助成金制度を組み合わせることで、系統用蓄電池の導入コストを大幅に抑えることができるのです。
申請方法と留意点

補助金・助成金の申請方法は、制度ごとに異なります。
通常、以下のような流れになります。
・公募要領や申請様式を入手する
・必要書類を準備する(事業計画書、見積書、図面など)
・申請期間内に書類を提出する
・審査結果を待つ
・採択された場合、交付決定を受ける
・事業を実施し、完了報告を提出する
・補助金を受け取る
申請にあたっては、いくつかの留意点があります。
まず、公募要領をよく読み、要件を満たしているか確認することが大切です。
対象となる事業者や設備、期間などが定められているため、これらに合致しない場合は補助を受けられません。
また、申請書類の作成には一定の時間と手間がかかります。
特に、事業計画書や見積書など、専門的な知識が必要な書類もあるため、十分な準備が必要です。
さらに、事業完了後の報告や調査にも対応しなければなりません。
補助金を受けた後も、一定期間は事業の状況を報告する必要があるため、これらの作業も見込んでおく必要があります。
これらの点を踏まえ、計画的に申請を進めることが重要です。
必要に応じて、専門家の助言を受けることも検討しましょう。
補助金・助成金制度は、系統用蓄電池の導入を経済的に支援する有力な手段です。
事業者はこれらの制度を積極的に活用し、蓄電池の導入を進めることが期待されています。
同時に、国や自治体には、さらなる支援制度の拡充と、申請手続きの簡素化が求められていると言えるでしょう。
系統用蓄電池への投資とリスク管理

系統用蓄電池は、電力系統の安定化や再生可能エネルギーの導入拡大に大きく貢献する有望な技術です。
同時に、大規模な設備投資を必要とし、市場環境の変化にもさらされるため、慎重な投資判断とリスク管理が求められます。
ここでは、系統用蓄電池への投資にあたって考慮すべき主な点と、リスクを適切に管理するための方策について解説します。
投資家や事業者は、これらを踏まえて、長期的視点に立った戦略的な意思決定を行うことが重要です。
初期投資と運用コストの考慮

系統用蓄電池への投資を検討する際、まず考慮すべきは初期投資と運用コストです。
蓄電池システムの購入や設置には多額の費用がかかるため、資金調達の方法や返済計画を綿密に立てる必要があります。
また、蓄電池の運用には電力料金やメンテナンス費用などの継続的なコストがかかります。
これらのコストを適切に見積もり、事業の収支計画に反映させることが重要です。
初期投資を抑えるためには、国や自治体の補助金・助成金制度を積極的に活用することも有効です。
ただし、申請には一定の手間がかかるため、十分な準備と体制づくりが必要です。
運用コストを抑えるには、蓄電池の適切な維持管理が欠かせません。
定期的な点検や部品交換などを計画的に実施し、トラブルや性能低下を未然に防ぐことが求められます。
また、電力市場の動向を注視し、電力の調達や売却のタイミングを最適化することも重要です。
これにより、電力料金の負担を軽減し、収益性を高めることができるでしょう。
市場動向と規制変更のリスク評価
系統用蓄電池の事業性は、電力市場の動向に大きく左右されます。
電力価格の変動や、需給調整市場の状況などは、蓄電池の収益に直結するため、常に注視が必要です。
また、政府のエネルギー政策や規制の変更にも注意が必要です。
例えば、再生可能エネルギーの導入目標や、系統接続ルールの変更などは、蓄電池事業に大きな影響を与える可能性があります。
これらのリスクを適切に評価し、対応策を講じることが重要です。
具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
– 電力市場の動向を定期的に分析し、事業計画に反映させる
– 政府の政策動向や業界団体の情報を収集し、規制変更に備える
– 複数の市場や収益源を組み合わせ、リスクを分散させる
– 電力会社や他の事業者との連携を探り、事業の安定性を高める
これらの取り組みを通じ、市場リスクを適切にコントロールし、事業の持続性を高めることが求められます。
同時に、規制変更をビジネスチャンスと捉え、新たな事業機会を探ることも重要です。
柔軟な発想と機動的な対応が、リスク管理の鍵となるでしょう。
長期的な収益性の見通し

系統用蓄電池への投資は、長期的視点に立った判断が求められます。
蓄電池システムの耐用年数は10年以上に及ぶため、その間の収支を見通しておく必要があります。
長期的な収益性を評価する際には、以下のような点を考慮する必要があります。
– 電力市場の将来見通し(価格の推移、需要の変化など)
– 技術革新による蓄電池の性能向上と価格低下の可能性
– 再生可能エネルギーの導入拡大と、蓄電池需要の増加見込み
– 競合他社の動向と、市場シェアの獲得可能性
これらを総合的に分析し、長期的な事業の採算性を見極めることが重要です。
また、収益性の向上に向け、継続的な効率化と差別化も欠かせません。
運用の自動化やデータ分析の活用などを通じ、コスト削減と最適化を図ることが求められます。
さらに、蓄電池の性能や付加価値を高め、競合他社との差別化を図ることも重要です。
例えば、AIを活用した高度な需給調整機能の開発や、再生可能エネルギーとの組み合わせによる環境価値の訴求などが考えられます。
長期的視点に立ち、市場の変化に適応しながら、持続的な収益性を追求することが、系統用蓄電池への投資の成功の鍵となるでしょう。
事業者には、不断の努力と革新が求められています。
系統用蓄電池の主要メーカーと技術動向

系統用蓄電池は、電力系統の安定化や再生可能エネルギーの導入拡大に欠かせない技術として、世界中で活発な開発競争が繰り広げられています。
ここでは、国内外の主要な蓄電池メーカーと、その製品ラインナップを概観します。
また、次世代蓄電池技術の開発状況と、将来の技術トレンドについても展望します。
事業者や投資家は、これらの情報を踏まえ、適切な技術選択とパートナー選びを行うことが重要です。
国内外の主要メーカーと製品ラインナップ
系統用蓄電池の市場には、大手電機メーカーやエネルギー企業が多数参入しています。
国内では、東芝、日立製作所、NEC、ソニーなどが代表的なメーカーとして知られています。
これらの企業は、長年培ってきた電池技術を活かし、大規模な蓄電池システムを提供しています。
例えば、東芝の「SCiB」は、高い安全性と長寿命を特長とするリチウムイオン電池で、メガワット級の大型蓄電システムに採用されています。
日立製作所も、「CrystEna」ブランドで、コンテナ型の大規模蓄電システムを展開しています。
一方、海外では、テスラ、LG化学、サムスンSDI、BYD、ネオエンなどが有力なプレイヤーとして知られています。
米国のテスラは、「PowerPack」や「MegaPack」といった大型蓄電システムで、世界的にも高いシェアを誇っています。
韓国のLG化学とサムスンSDIも、電気自動車用電池で培った技術を活かし、系統用蓄電池市場に積極的に参入しています。
中国のBYDは、低価格を武器に、アジアや欧州市場で存在感を高めています。
また、オーストラリアのネオエンは、再生可能エネルギーと蓄電池を組み合わせたプロジェクトで、独自の地位を確立しつつあります。
このように、系統用蓄電池の市場は、国内外の有力企業が激しい競争を繰り広げる、ダイナミックな状況にあると言えるでしょう。
各社とも、大容量化、長寿命化、コストダウンなどに注力し、差別化を図っています。
事業者は、これらのメーカーの技術力や実績、サポート体制などを比較検討し、最適なパートナーを選ぶことが求められます。
次世代蓄電池技術の開発状況と将来展望

系統用蓄電池の分野では、リチウムイオン電池が主流となっていますが、さらなる性能向上と低コスト化を目指した次世代技術の開発も活発化しています。
その代表格が、全固体電池と、レドックスフロー電池です。
全固体電池は、電解質に固体材料を使用することで、安全性と エネルギー密度の大幅な向上が期待されています。
国内では、トヨタ自動車や村田製作所などが精力的な研究開発を進めており、2020年代後半の実用化を目指しています。
海外でも、QuantumScape社やSolidPower社などのスタートアップが、全固体電池の事業化を加速させています。
一方、レドックスフロー電池は、電解液を外部タンクに蓄えるため、容量と出力を独立して設計でき、スケーラビリティに優れるのが特長です。
住友電工や新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などが、低コスト化と大型化に向けた開発を進めています。
米国のESS社は、鉄を用いたレドックスフロー電池を商用化し、注目を集めています。
また、ナトリウムイオン電池や亜鉛イオン電池など、よりレアメタルに依存しない電池技術の研究も活発化しています。
これらの技術は、将来的に低コストで安全な系統用蓄電池の選択肢を広げると期待されます。
ただし、次世代技術はまだ開発途上の段階にあり、実用化までには一定の時間を要します。
当面は、リチウムイオン電池の継続的な進化と、新技術の実証試験の進展を注視していく必要があるでしょう。
中長期的には、多様な電池技術が共存し、用途に応じて最適な選択ができる時代が到来すると予想されます。
事業者には、技術動向を見据えつつ、柔軟な技術選択と計画的な投資が求められています。
次世代蓄電池が実用化されれば、系統用蓄電池の経済性と利便性はさらに向上し、再生可能エネルギーの大量導入を支える強力なツールとなるでしょう。
技術革新の恩恵を最大限に活用し、持続可能な電力システムの構築を加速させることが期待されます。
まとめ – 系統用蓄電池は電力システムの変革を支える有望な投資先

本記事では、系統用蓄電池の役割、ビジネスモデル、技術動向、投資機会について詳しく解説しました。
系統用蓄電池は、電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大に不可欠な技術であり、今後ますます重要性が高まることが予想されます。
電力卸売市場や容量市場、需給調整市場など、多様な収益機会を提供する点も大きな魅力です。
国や自治体の補助金・助成金制度も、初期投資の負担を軽減し、事業化を後押ししています。
一方で、系統用蓄電池への投資には、一定のリスクも伴います。
初期投資と運用コストの管理、市場動向と規制変更への対応、長期的な収益性の見極めなど、慎重な検討が必要です。
ただし、これらのリスクは、適切な管理と戦略的な意思決定によって、十分にコントロールできるものと言えるでしょう。
技術面でも、リチウムイオン電池の進化に加え、全固体電池やレドックスフロー電池など、次世代技術の開発が活発化しており、将来的な経済性の向上が期待されます。
系統用蓄電池は、単なる設備投資ではなく、電力システムの変革を支える重要なインフラであり、社会的意義の高い投資でもあります。
再生可能エネルギーの大量導入と、クリーンで安定した電力供給の実現に貢献することで、持続可能な社会の構築に寄与できるのです。
事業者や投資家には、長期的視点に立ち、社会的価値と経済的リターンのバランスを取りながら、果敢に挑戦していくことが求められていると言えるでしょう。
系統用蓄電池は、まさに今、参入すべき有望な投資分野なのです。
本記事が、読者の皆様の意思決定の一助となれば幸いです。
系統用蓄電池の将来に、大いに期待しましょう。
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。






