お役立ちコラム 2025.06.25
太陽光パネルの増設で発電量アップ!メリットと注意点

電気料金の高騰がつづくなか、太陽光発電をすでに導入しているご家庭でも、さらなる電気料金削減をめざして太陽光パネルの追加を検討される方がふえています。 太陽光パネルを増設することで、発電量をアップさせ、売電収入の増加や自家消費による電気代削減効果をたかめることができます。 しかし、増設にはメリットだけでなく、FIT制度への影響や保証の問題など、事前に知っておくべき注意点もあります。
この記事では、太陽光発電の増設について、基本的な知識からメリット・デメリット、さらには具体的な対策まで、くわしく解説します。 太陽光パネルの追加を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
太陽光発電の増設とは

太陽光発電の増設はソーラーパネルを追加すること
太陽光発電の増設とは、すでに稼働している太陽光発電システムに、あらたにソーラーパネルを追加することをさします。 設置済みのシステムの発電容量をふやすことで、より多くの電力を生みだすことができるようになります。 増設は、10kW未満の住宅用太陽光発電でも、10kW以上の産業用太陽光発電でも可能です。
増設と混同されやすい言葉に「過積載」がありますが、これらは異なる概念です。 過積載は、パワーコンディショナの出力容量をこえる太陽光パネルを設置することをいいます。 一方、増設は、パワーコンディショナの容量をこえるかどうかにかかわらず、太陽光パネルを追加することをさします。
太陽光パネルの増設には、以下のような方法があります。
• 既存の屋根のあきスペースに追加設置
• カーポートなど別の場所への設置
• 既存パネルの一部を高効率パネルに交換
• パワーコンディショナの増設もあわせて実施
増設を検討する際は、現在のシステムの状況をしっかりと把握することが大切です。 設置容量、パワーコンディショナの容量、屋根のあきスペースなどを確認し、最適な増設プランをたてましょう。 また、増設によってFIT制度の適用条件がかわる場合があるため、事前の確認が必要です。
太陽光発電の増設に関するルール

太陽光発電の増設には、FIT制度(固定価格買取制度)に関連するルールがあります。 増設の規模や既存設備の容量によって、売電価格や買取期間への影響がことなります。 2024年度からは、増設をうながすためのあらたなルール変更も予定されています。
現行のルールでは、増設によって出力が増加する場合、設備全体の買取価格が最新価格に変更されることがあります。 ただし、増出力分が3kW未満かつ3%未満であれば、価格は変更されません。 しかし、2024年度からは、増設分のみに最新価格を適用するルールに変更される予定です。
増設に関するルールを理解するうえで重要なポイントは以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 買取価格の変更 | 増設の規模により変更される場合がある |
| 買取期間 | 基本的に当初の期間を維持 |
| 申請手続き | 変更認定申請が必要 |
| 2024年度からの変更 | 増設分のみ最新価格適用 |
増設を検討する際は、これらのルールを十分に理解し、経済的なメリットを最大化できるよう計画をたてることが大切です。 特に、FIT認定をうけている設備の増設では、事前の確認と適切な手続きが必要となります。 次に、増設後の容量別に、具体的なルールを解説します。
増設後でも10kW未満のケース
増設後も出力が10kW未満のままであれば、買取価格への影響はもっともちいさくなります。 既存の太陽光発電システムが10kW未満で、増設後も10kW未満におさまる場合、受給開始時点の買取単価がそのまま維持されます。 買取期間も当初の10年間から変更されることはありません。
たとえば、2015年に4kWの太陽光発電を設置し、2024年に2kWを増設して合計6kWになった場合をかんがえてみましょう。 この場合、2015年の住宅用買取価格(33円/kWh)がそのまま適用されます。 増設分も含めて、すべての発電電力が同じ単価で売電できるため、経済的なメリットがおおきくなります。
増設後も10kW未満におさえるメリットは以下のとおりです。
• 既存の高い買取価格を維持できる
• 余剰売電のまま運用できる
• 手続きが比較的かんたん
• 住宅用の各種優遇制度を継続利用できる
ただし、パワーコンディショナの容量には注意が必要です。 既存のパワーコンディショナで対応できない場合は、交換や増設が必要になることがあります。 また、屋根のスペースにも制限があるため、効率的な配置をかんがえる必要があります。
増設により10kW以上になるケース
増設前は10kW未満だった設備が、増設によって10kW以上になる場合は、買取価格と期間の両方に影響があります。 このケースでは、増設時点での事業用(10kW以上)の買取価格が適用されることになります。 買取期間は20年に延長されますが、売電方式は余剰売電のままとなります。
たとえば、2020年に8kWで設置し、2024年に4kWを増設して合計12kWになった場合をみてみましょう。 2020年の住宅用買取価格(21円/kWh)から、2024年の事業用買取価格(10円/kWh程度)に変更されます。 買取価格は大幅にさがりますが、買取期間が10年から20年にのびるというメリットもあります。
10kW以上になることによる変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 変更前(10kW未満) | 変更後(10kW以上) |
|---|---|---|
| 買取価格 | 住宅用価格 | 事業用価格(低い) |
| 買取期間 | 10年 | 20年 |
| 売電方式 | 余剰売電 | 余剰売電のまま |
| メンテナンス | 努力義務 | 義務化 |
増設により10kW以上になる場合は、慎重なシミュレーションが必要です。 買取価格の低下と買取期間の延長を比較し、トータルでの収益性を検討しましょう。 また、事業用となることで、メンテナンスの義務化など、運用面での負担もふえることに注意が必要です。
増設前から10kW以上のケース
すでに10kW以上の太陽光発電を運用している場合の増設は、もっとも注意が必要です。 わずかでも認定出力が増加すると、既存設備も含めて全体の買取価格が最新価格に変更されてしまいます。 買取期間は当初の20年のままで延長されません。
たとえば、2018年に50kWで運転開始し、18円/kWhで売電していた設備に5kWを増設する場合をかんがえてみましょう。 増設により、既存の50kW分も含めて、すべてが2024年の買取価格(10円/kWh程度)に変更されます。 これは、売電収入に大きな影響をあたえる可能性があります。
10kW以上の設備で増設する際の注意点は以下のとおりです。
• 3kW未満かつ3%未満の増設なら価格変更なし
• それをこえると全量が最新価格に変更
• 買取期間の延長はない
• 事前の収益シミュレーションが必須
ただし、2024年度からのルール変更により、増設分のみに最新価格が適用されるようになる予定です。 これにより、既存設備への影響をおさえながら増設できるようになります。 新ルールの詳細が発表されたら、増設計画を再検討する価値があるでしょう。
太陽光発電の増設のメリット

発電量と売電収入を増やせる
太陽光パネルを増設する最大のメリットは、発電量の増加により売電収入をふやせることです。 太陽光発電システムの維持管理コストは、パネルの枚数がふえてもほとんど変わりません。 そのため、増設により純粋に発電量と収益をアップさせることができます。
たとえば、4kWの太陽光発電システムに2kWを増設した場合、発電量は約1.5倍になります。 年間発電量が4,000kWhから6,000kWhに増加すれば、売電収入も比例して増加します。 10kW未満の範囲内での増設なら、既存の高い買取価格のまま売電量をふやせるため、投資回収も早まります。
増設による経済効果の例をみてみましょう。
| 項目 | 増設前(4kW) | 増設後(6kW) | 増加分 |
|---|---|---|---|
| 年間発電量 | 4,000kWh | 6,000kWh | 2,000kWh |
| 売電収入(30円/kWh) | 12万円 | 18万円 | 6万円 |
| 自家消費削減額 | 4万円 | 6万円 | 2万円 |
| 年間メリット合計 | 16万円 | 24万円 | 8万円 |
また、電気料金の高騰がつづく現在では、自家消費による電気代削減効果も見逃せません。 発電量がふえれば、より多くの電力を自家消費にまわすことができます。 昼間の電力使用量がおおい家庭では、特に大きなメリットを享受できるでしょう。
ピークカットがあっても発電量をカバーできる
太陽光パネルを増設して過積載状態になると、ピークカットが発生することがあります。 ピークカットとは、パワーコンディショナの容量をこえる発電があった場合に、超過分がカットされる現象です。 しかし、ピークカットによる損失があっても、トータルでの発電量は増加します。
ピークカットが発生するのは、晴天時の正午前後の2~3時間程度にかぎられます。 それ以外の時間帯では、増設したパネルの能力をフルに活用できます。 朝夕の発電量が増加し、くもりや雨の日でも、より多くの電力を生みだすことができます。
ピークカットを考慮した発電量の変化を以下にしめします。
• 晴天時:ピーク時はカットされるが、朝夕の発電量が増加
• くもり時:カットなしで増設分がフルに活用できる
• 雨天時:わずかでも発電量の増加が期待できる
• 年間トータル:ピークカット分を差し引いても15~20%の増加
過積載率150%程度までであれば、ピークカットによる損失は年間発電量の5%程度におさまります。 一方で、増設による発電量増加は20%以上になることがおおく、十分なメリットがあります。 特に、自家消費をメインにかんがえている場合は、ピークカット時も自家消費にまわせるため、無駄がありません。
卒FIT後でも活用可能
FIT制度の買取期間が終了した「卒FIT」後も、増設した太陽光パネルは継続的に活用できます。 卒FIT後は、電力会社との個別契約により、7~10円/kWh程度の価格で売電を継続できます。 または、蓄電池とくみあわせて自家消費をメインにする選択肢もあります。
卒FIT後の太陽光発電活用において、増設のメリットは以下のとおりです。
• 発電量増加により自家消費率をたかめられる
• 蓄電池への充電量をふやせる
• 電気自動車への充電にも活用できる
• 災害時の電力確保量が増加する
特に、電気料金が高騰しているいま、自家消費のメリットは非常におおきくなっています。 1kWhあたり30円以上の電気を買わずに、自家発電でまかなえる量がふえれば、家計への貢献度もたかまります。 また、将来的に電気自動車の導入をかんがえている場合も、増設により充電用電力を確保できます。
卒FIT後の運用パターン別メリットは以下のとおりです。
| 運用パターン | 増設のメリット |
|---|---|
| 売電継続 | 売電量増加による収入アップ |
| 自家消費重視 | 電気代削減効果の向上 |
| 蓄電池併用 | 蓄電量増加で夜間も自給可能 |
| V2H導入 | 電気自動車への充電量確保 |
長期的な視点でみれば、太陽光パネルの寿命は25~30年といわれています。 FIT期間終了後も、15年以上は発電をつづけることができるため、増設による恩恵を長期間うけることができます。
蓄電池の充電量に余裕があればさらに電気を貯められる
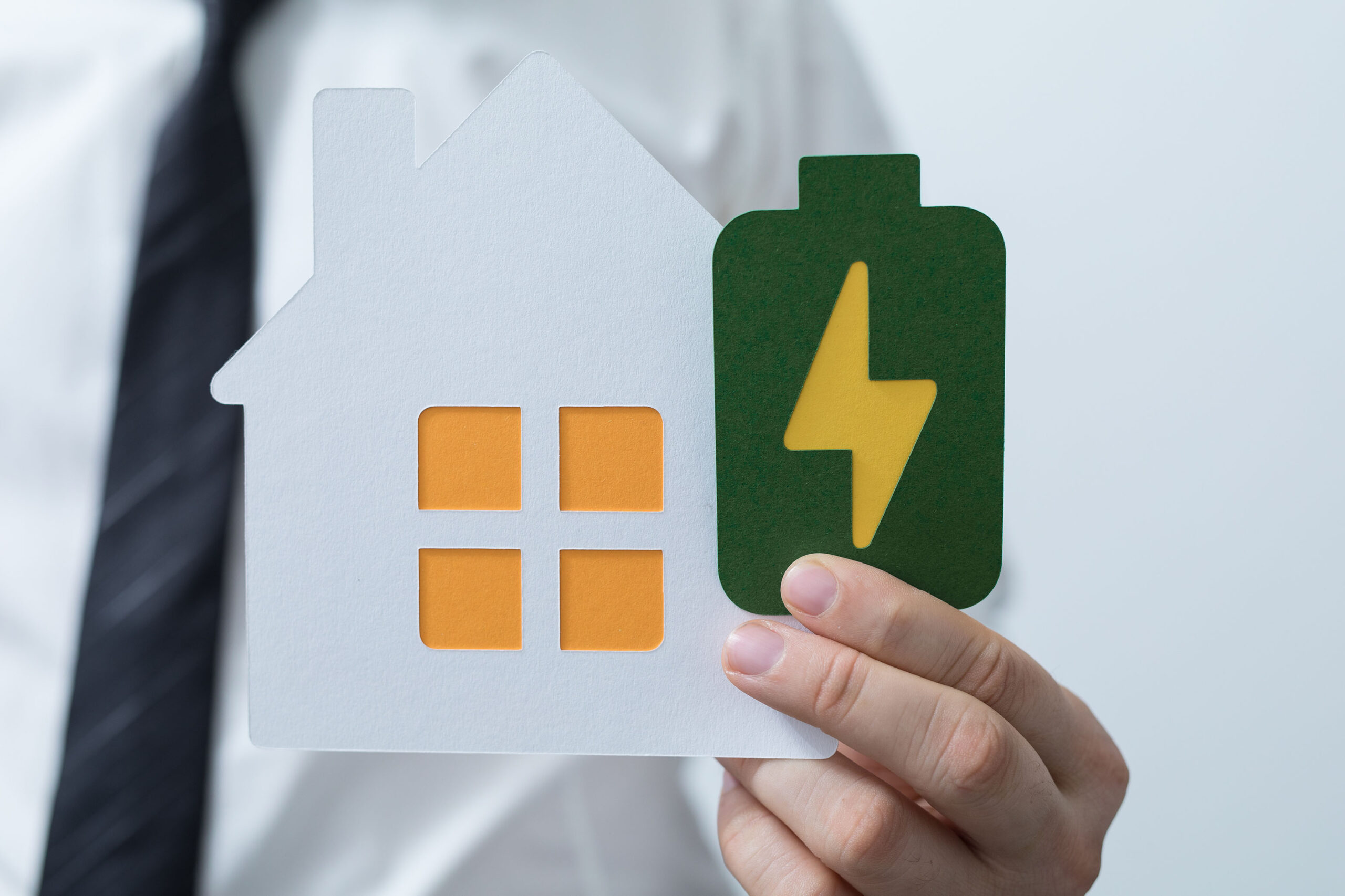
家庭用蓄電池を導入している場合、太陽光パネルの増設により、より多くの電力を貯めることができます。 蓄電池の容量に余裕があれば、増設分の余剰電力を有効活用できるため、電気の自給率をさらにたかめることができます。 夜間や早朝の電力も、蓄電池からの供給でまかなえるようになります。
たとえば、10kWhの蓄電池を設置していて、現在の太陽光発電では満充電にならない場合をかんがえてみましょう。 太陽光パネルを増設することで、日中により多くの電力を蓄電池に貯めることができます。 これにより、夜間の電力購入量をさらに削減でき、電気代削減効果がたかまります。
蓄電池との併用における増設のメリットは以下のとおりです。
• 蓄電池の能力をフルに活用できる
• 深夜電力の購入量を削減できる
• 停電時の電力供給時間が延長される
• 天候不良時でも一定の充電量を確保できる
また、最近の蓄電池システムには、AIによる最適制御機能がついているものもあります。 天気予報や電力使用パターンを学習し、効率的な充放電をおこないます。 太陽光パネルを増設すれば、このような高機能システムの性能を最大限にいかすことができます。
蓄電池容量と太陽光発電容量の最適なバランスは、一般的に1:1~1:1.5程度といわれています。 10kWhの蓄電池なら、10~15kW程度の太陽光発電があれば、効率的な運用ができます。 現在の設備容量をかくにんし、最適なバランスになるよう増設を検討しましょう。
太陽光発電の増設の注意点

違うメーカーや業者で増設すると保証が外れる可能性がある
太陽光パネルの増設において、もっとも注意すべき点のひとつが保証の問題です。 既存のシステムとちがうメーカーのパネルを追加したり、別の施工業者に依頼したりすると、メーカー保証が無効になる可能性があります。 保証がなくなると、故障や不具合が発生した際の修理費用が全額自己負担となってしまいます。
メーカー保証に関する注意点は以下のとおりです。
• 同一メーカーでも型番がちがうと保証対象外になることがある
• パワーコンディショナの許容量をこえると保証が無効になる
• 施工業者がちがうと施工保証がうけられない
• システム全体の保証が失われる可能性がある
たとえば、A社のパネルを使用している既存システムに、価格の安いB社のパネルを追加した場合をかんがえてみましょう。 この場合、A社はシステム全体の保証をおこなわなくなる可能性があります。 また、B社も既存システムとの相性については保証しないため、トラブル時の責任の所在があいまいになります。
保証を維持するための対策は以下のとおりです。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 同一メーカー選択 | 既存と同じメーカーのパネルを使用 |
| 事前確認 | メーカーに増設の可否を確認 |
| 施工業者の統一 | 設置時と同じ業者に依頼 |
| 保証内容の再確認 | 増設後の保証範囲を明確化 |
また、パワーコンディショナの容量についても注意が必要です。 メーカーが推奨する過積載率をこえると、パワーコンディショナの保証が無効になることがあります。 一般的に、過積載率は150%程度までが推奨されていますが、メーカーによってことなるため、事前の確認が必要です。
売電価格が下がる可能性がある

太陽光パネルの増設により、FIT制度の売電価格が下がってしまう可能性があります。 特に、増設によって設備認定の変更が必要になる場合は、最新の買取価格が適用されることになります。 FIT制度開始当初とくらべて買取価格は大幅に下落しているため、慎重な検討が必要です。
売電価格が変更になるケースをまとめると以下のとおりです。
• 10kW未満から10kW以上になる場合
• 10kW以上で3kWまたは3%をこえる増設
• システム全体の出力が20%以上減少する改修
たとえば、2012年に設置した10kW以上の設備(42円/kWh)に増設する場合、2024年の価格(約10円/kWh)に変更される可能性があります。 この場合、売電収入は4分の1程度に減少してしまいます。 増設による発電量増加を考慮しても、トータルの売電収入が減少することもあります。
売電価格下落の影響を最小限にする方法は以下のとおりです。
• 10kW未満の設備は10kW未満の範囲で増設
• 10kW以上の設備は3kW未満かつ3%未満で増設
• 自家消費をメインにした運用に切りかえ
• 2024年度からの新ルールをまつ
ただし、2024年度からは増設分のみに最新価格を適用する新ルールが導入される予定です。 これにより、既存設備の高い買取価格を維持しながら増設できるようになります。 急ぎでない場合は、新ルールの詳細が確定してから増設を検討するのも選択肢のひとつです。
FIT期間中の増設には手間がかかる
FIT認定をうけている期間中に太陽光パネルを増設する場合、各種の手続きが必要になります。 変更認定申請とよばれる手続きをおこなわなければ、増設後も売電することができません。 申請から認定までには時間がかかるため、余裕をもった計画が必要です。
必要な手続きの流れは以下のとおりです。
• 事前相談:電力会社への接続検討依頼
• 申請準備:必要書類の収集と作成
• 変更認定申請:経済産業省への申請
• 審査期間:1~3ヶ月程度
• 認定取得:正式な認定書の受領
• 工事着工:認定後に増設工事開始
出力50kW未満の設備では、再生可能エネルギー電子申請システムをつかってオンラインで申請できます。 しかし、50kW以上の設備では、管轄の経済産業局へ書類を郵送する必要があります。 また、電力会社との系統連系協議も必要になるため、全体で3~6ヶ月程度の期間をみておく必要があります。
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 変更認定申請書 | 設備の変更内容を記載 |
| 設備の配置図 | 増設後のレイアウト |
| 配線図 | 電気系統の接続状況 |
| 仕様書 | 増設するパネルの詳細 |
| 印鑑証明書 | 申請者の本人確認 |
手続きの煩雑さをかんがえると、経験豊富な施工業者に依頼することをおすすめします。 申請書類の作成から提出まで、トータルでサポートしてくれる業者をえらびましょう。 また、申請中は工事に着手できないため、スケジュールには十分な余裕をもたせることが大切です。
太陽光発電の増設を検討すべきタイミング

消費電力が増えている状態
家庭の消費電力が増加している場合は、太陽光パネルの増設を検討する絶好のタイミングです。 在宅勤務の増加、家族構成の変化、新しい家電の導入などにより、電力使用量は変動します。 既存の太陽光発電では電力をまかないきれなくなったとき、増設により電気料金の負担を軽減できます。
消費電力が増加する主な要因は以下のとおりです。
• 在宅勤務によるパソコンやエアコンの使用増加
• 家族の増加(出産、同居など)
• オール電化機器の導入(IHクッキングヒーター、エコキュートなど)
• 電気自動車の購入
• ペットの飼育による空調使用の増加
たとえば、在宅勤務により昼間の電力使用量が月200kWh増加した場合をかんがえてみましょう。 電気料金単価を30円/kWhとすると、月6,000円、年間72,000円の負担増となります。 太陽光パネルを2kW程度増設すれば、この増加分の大部分をカバーでき、電気料金の上昇をおさえることができます。
消費電力の変化を把握する方法は以下のとおりです。
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 電気料金明細 | 前年同月との使用量比較 |
| HEMS | 時間帯別の使用量確認 |
| スマートメーター | 30分単位の使用量データ |
| 省エネ診断 | 専門家による詳細分析 |
また、将来的な電力需要の増加も考慮することが大切です。 電気自動車の購入予定がある場合は、充電に必要な電力量をあらかじめ計算にいれておきましょう。 一般的な電気自動車では、月1,000km走行で約150~200kWhの電力が必要になります。
蓄電池を導入・増設する

家庭用蓄電池の導入や増設をかんがえている場合も、太陽光パネルの増設を検討すべきタイミングです。 蓄電池の性能を最大限にいかすには、十分な発電量が必要になります。 既存の太陽光発電だけでは蓄電池を満充電にできない場合、太陽光パネルの増設が効果的です。
蓄電池導入時に太陽光パネル増設をかんがえるメリットは以下のとおりです。
• 蓄電池の容量をフル活用できる
• 工事を同時におこなうことで費用を削減
• システム全体の最適化が可能
• 補助金を一括で申請できる場合がある
たとえば、10kWhの蓄電池を導入する場合、理想的な太陽光発電容量は10~15kW程度です。 既存の太陽光発電が5kWしかない場合、5~10kW程度の増設により、蓄電池の能力を最大限にひきだすことができます。 これにより、夜間の電力自給率が大幅に向上し、電気料金削減効果もたかまります。
蓄電池との組みあわせを検討する際のポイントは以下のとおりです。
• 蓄電池容量と太陽光発電容量のバランス
• 家庭の電力使用パターンの分析
• 災害時の必要電力量の計算
• 将来の電力需要予測
• V2H(Vehicle to Home)導入の可能性
また、既存の蓄電池に追加で蓄電池を増設する場合も、太陽光パネルの増設を同時に検討しましょう。 蓄電容量だけをふやしても、充電する電力がなければ意味がありません。 太陽光発電と蓄電池のバランスをとることで、最適なエネルギーマネジメントが実現できます。
太陽光発電の増設前の対策

売電期間の延長が可能か確認する
太陽光パネルの増設をおこなう前に、売電期間の延長が可能かどうかを確認することが重要です。 FIT制度では、増設の内容によって買取期間が変更される場合があります。 特に、10kW未満から10kW以上になる場合は、買取期間が10年から20年に延長されます。
売電期間に関する確認事項は以下のとおりです。
• 現在の認定内容(出力、買取価格、残り期間)
• 増設後の出力と適用される制度
• 全量売電か余剰売電かの確認
• 2012年7月1日以前の設置かどうか
たとえば、2015年に8kWで認定をうけ、あと3年でFIT期間が終了する設備があるとします。 この設備に4kWを増設して12kWにした場合、買取期間が20年に延長される可能性があります。 ただし、買取価格は最新のものに変更されるため、慎重な収支計算が必要です。
売電期間の延長判断フローは以下のとおりです。
| ステップ | 確認内容 |
|---|---|
| 1 | 現在の認定内容を確認 |
| 2 | 増設後の出力を計算 |
| 3 | 適用される制度を確認 |
| 4 | 収支シミュレーション実施 |
| 5 | 延長のメリット・デメリット比較 |
また、2024年度から導入される新ルールでは、増設分のみに最新価格が適用される予定です。 これにより、既存設備の買取価格を維持しながら、期間延長のメリットをうけられる可能性があります。 最新の制度情報を確認し、最適なタイミングで増設を実施しましょう。
増設による補助金があるかを確認する

太陽光発電の増設においても、自治体によっては補助金が支給される場合があります。 新規設置とくらべて補助額はちいさくなることがおおいですが、初期費用の負担軽減につながります。 増設前に、お住まいの地域の補助金制度を必ず確認しましょう。
増設に関する補助金の特徴は以下のとおりです。
• 新規設置時の補助金との差額が支給される
• 上限額が設定されている場合がおおい
• 蓄電池との同時導入で補助額が増加することがある
• 申請期限や予算枠に注意が必要
たとえば、ある自治体では1kWあたり2万円、上限10万円の補助金があるとします。 以前4kWを設置した際に8万円の補助金をうけていた場合、2kWの増設では上限までの残り2万円が支給されます。 金額はおおきくありませんが、工事費用の一部として活用できます。
補助金申請の注意点は以下のとおりです。
• 事前申請が必要な場合がおおい
• 工事着工前に申請を完了させる
• 必要書類を早めに準備する
• 予算がなくなり次第終了する
• 他の補助金との併用可否を確認
また、国の補助金制度についても確認しましょう。 蓄電池やV2Hシステムとの同時導入では、より充実した補助金がうけられる可能性があります。 複数の補助金を組みあわせることで、初期投資の負担を大幅に軽減できることもあります。
屋根の空きスペースを確認する

太陽光パネルの増設において、もっとも基本的でありながら重要なのが、屋根の空きスペースの確認です。 既存のパネル配置、屋根の形状、方角などを詳細に調査し、増設可能な容量を把握する必要があります。 専門業者による現地調査をおこない、正確な情報をもとに計画をたてましょう。
屋根の空きスペース確認のポイントは以下のとおりです。
• 既存パネルの配置と空きスペースの測定
• 屋根の耐荷重の確認
• 日当たりや影の影響調査
• 配線ルートの確保
• メンテナンススペースの確保
一般的な住宅用太陽光パネル(約1.6m×1m)の場合、1枚あたり約1.6平方メートルの設置スペースが必要です。 これに加えて、パネル間の隙間やメンテナンス用の通路も確保する必要があります。 屋根の形状によっては、台形パネルや小型パネルの使用も検討しましょう。
屋根の種類別の注意点は以下のとおりです。
| 屋根の種類 | 注意点 |
|---|---|
| 切妻屋根 | 南面の空きスペースを優先活用 |
| 寄棟屋根 | 台形パネルの活用を検討 |
| 片流れ屋根 | 全面活用が可能だが影に注意 |
| 陸屋根 | 架台の設置スペースも考慮 |
また、屋根の劣化状況も重要な確認事項です。 太陽光パネルの寿命は25年以上ありますが、屋根の寿命がそれより短い場合は、先に屋根のメンテナンスが必要になることがあります。 増設前に屋根の点検をおこない、必要に応じて補修や塗装をおこなうことをおすすめします。
ソーラーカーポートの導入も検討する
屋根に十分な空きスペースがない場合は、ソーラーカーポートの導入を検討しましょう。 ソーラーカーポートは、駐車場の屋根として機能しながら、太陽光発電もおこなえる一石二鳥の設備です。 住宅の屋根とは独立して設置できるため、増設の選択肢としてひろく活用されています。
ソーラーカーポートのメリットは以下のとおりです。
• 駐車スペースを有効活用できる
• 車を日差しや雨から守れる
• 住宅の美観を損なわない
• メンテナンスがしやすい
• EV充電設備との相性がよい
一般的な2台用ソーラーカーポートでは、3~5kW程度の太陽光パネルを設置できます。 これは、住宅用太陽光発電の平均的な容量に匹敵する発電能力です。 既存の屋根置き太陽光発電とあわせれば、大幅な発電量アップが期待できます。
ソーラーカーポート導入の注意点は以下のとおりです。
• 建築確認申請が必要な場合がある
• 基礎工事が必要で費用がかかる
• 高さ制限や建ぺい率に注意
• 積雪地域では強度計算が重要
• 隣地への影の影響を確認
費用面では、一般的な2台用ソーラーカーポートで200~300万円程度が目安となります。 ただし、駐車場の屋根としての価値もあるため、単純な太陽光パネル増設とはことなる投資価値があります。 また、自治体によってはソーラーカーポートにも補助金が適用される場合があるので、確認してみましょう。
太陽光パネルの増設に適した製品

低反射(防眩)太陽光パネル
太陽光パネルの増設において、近隣への配慮から低反射(防眩)タイプのパネルがえらばれることがふえています。 通常の太陽光パネルは、表面のガラスが太陽光を反射し、まぶしさの原因となることがあります。 低反射パネルは、特殊な表面処理により反射をおさえ、周囲への影響を最小限にします。
低反射太陽光パネルの特徴は以下のとおりです。
• 反射率を通常の半分以下におさえる
• 発電効率はほぼ同等を維持
• 景観になじみやすい外観
• 近隣トラブルのリスクを軽減
• 航空機の運航への影響も考慮
特に、住宅密集地での増設では、低反射パネルの採用が推奨されます。 既存のパネルが通常タイプでも、増設分だけ低反射タイプにすることで、全体的な反射量を軽減できます。 また、北面設置など、反射が問題になりやすい場所への設置にも適しています。
主要メーカーの低反射パネルの例は以下のとおりです。
| メーカー | 製品特徴 |
|---|---|
| パナソニック | 独自の反射防止膜技術 |
| シャープ | 低反射ガラス採用 |
| 京セラ | 防眩処理済みモデル |
| 三菱電機 | 特殊表面加工タイプ |
価格面では、通常のパネルとくらべて5~10%程度高くなることがおおいです。 しかし、近隣への配慮や将来的なトラブル回避をかんがえれば、十分に投資価値があります。 また、自治体によっては、低反射パネルの採用を補助金の条件にしている場合もあります。
フレームによる段差がないフルスクリーンモジュール
最新の太陽光パネル技術として注目されているのが、フレームレスデザインのフルスクリーンモジュールです。 従来のパネルは、アルミフレームで囲まれていましたが、フルスクリーンタイプは段差がなく、スマートな外観が特徴です。 増設時に既存パネルとならべても、統一感のある仕上がりになります。
フルスクリーンモジュールのメリットは以下のとおりです。
• すっきりとした外観で美観向上
• 段差がないため汚れがたまりにくい
• 軽量化により屋根への負担軽減
• 設置面積あたりの発電量が向上
• 風圧や積雪への耐性も確保
特に、デザインを重視する住宅や、街なみ景観に配慮が必要な地域での増設に適しています。 フレームがないことで、パネル端部まで発電セルを配置でき、同じ面積でもより多くの発電量を確保できます。 これは、限られた屋根スペースを最大限活用したい増設においては、大きなメリットとなります。
フルスクリーンモジュールの技術的特徴は以下のとおりです。
• 強化ガラスによる高い耐久性
• 特殊な封止材で防水性能確保
• 独自の取付金具で確実な固定
• メンテナンス性の向上
• 長期保証にも対応
価格は従来型とくらべて10~20%程度高くなりますが、発電効率の向上と美観の改善をかんがえれば、選択する価値は十分にあります。 また、将来的な住宅の資産価値向上にもつながるため、長期的な視点での投資効果も期待できます。 増設を機に、最新技術を取りいれることで、太陽光発電システム全体のグレードアップをはかることができるでしょう。
まとめ

太陽光パネルの増設は、既存の太陽光発電システムの発電量をアップさせ、電気料金削減効果や売電収入の増加をもたらす有効な手段です。 特に、電気料金の高騰がつづく現在においては、自家消費による経済メリットがますます大きくなっています。 10kW未満の範囲での増設であれば、既存の高い買取価格を維持しながら発電量をふやすことができ、投資効果も高くなります。
ただし、増設にあたっては、FIT制度のルールや保証の問題など、注意すべき点もあります。 特に、増設により10kW以上になる場合や、既に10kW以上の設備への増設では、買取価格への影響を慎重に検討する必要があります。 2024年度からは、増設分のみに最新価格を適用する新ルールが導入される予定ですので、最新情報を確認しながら計画をたてることが大切です。
増設を成功させるためには、事前の準備が欠かせません。 屋根の空きスペースの確認、補助金の活用、適切な製品選択など、さまざまな要素を総合的に検討しましょう。 また、蓄電池との組みあわせや、ソーラーカーポートの活用など、柔軟な発想で最適な増設プランをみつけることも重要です。
太陽光発電の増設は、単なる設備の追加ではなく、エネルギーの自給自足にむけた大切な一歩です。 専門業者としっかりと相談し、ご家庭にとって最適な増設計画をたてて、より快適で経済的な暮らしを実現してください。
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。






