お役立ちコラム 2025.01.04
オール電化とガス併用の光熱費比較
近年、新築・リフォームの際にオール電化を選ぶ家庭が増えています。一方で、従来のガス併用を続ける世帯も少なくありません。
オール電化とガス併用、どちらがお得なのでしょうか。光熱費の観点から、それぞれの特徴とメリット・デメリットを比較し、おすすめの世帯についても解説します。
省エネと光熱費削減を意識しながら、ライフスタイルに合った選択ができるよう、ぜひ参考にしてください。
目次
オール電化の特徴とメリット・デメリット

光熱費の基本料金一本化と災害時の安全性
オール電化の最大の特徴は、光熱費の基本料金が電気代のみに一本化できる点です。
ガスの基本料金がかからないため、支払いや管理がシンプルになり、家計の把握がしやすくなります。
また、オール電化は火を使わないので、ガス漏れや火災のリスクが低いのも大きなメリットです。
地震などの災害時には、ガスよりも電気の方が復旧が早い傾向にあるため、ライフラインの確保という面でも優れています。
初期費用とメンテナンス費用の高さ
オール電化のデメリットとして挙げられるのが、初期費用の高さです。
IHクッキングヒーターやエコキュートなど、オール電化対応の設備機器は一般的に高価であり、導入時のイニシャルコストがかさみます。
また、これらの機器は高性能な分、メンテナンスや修理にも費用がかかる傾向にあります。
長期的な視点で見ると、ランニングコストでは光熱費を抑えられる可能性がありますが、初期投資と維持費用については十分に考慮する必要があるでしょう。
停電時の備えの必要性

オール電化の場合、停電時には電気を使った調理や給湯ができなくなるため、何らかの対策が必要です。
例えば、ガスコンロやガスストーブなどの代替手段を用意しておくことが望ましいでしょう。
また、冬場の停電では暖房が使えなくなるため、防寒対策も重要です。
こうした非常時の備えについては、オール電化ならではの課題として認識しておく必要があります。
停電に備えて、カセットコンロや懐中電灯、携帯用の充電器などを常備しておくことをおすすめします。
ガス併用の特徴とメリット・デメリット
都市ガスによるエネルギーコストの抑制
ガス併用の大きなメリットは、都市ガスのエネルギーコストの安さです。
1kWhあたりの料金を比較すると、都市ガスは電気よりも割安であることが多く、効率的にエネルギーを使用できます。
特に暖房や給湯など、大量のエネルギーを必要とする用途において、都市ガスの優位性が発揮されます。
ただし、プロパンガスの場合は都市ガスほどの価格メリットが期待できないため、注意が必要です。
日中の給湯・調理での割安感
オール電化向けの料金プランでは、夜間の電力使用を促進するために、日中の電気料金が割高に設定されていることが一般的です。
一方、ガス併用の場合、ガス料金は時間帯に関係なく一定であるため、日中の給湯や調理にガスを使用することで、光熱費を抑えられる可能性があります。
家族構成や生活スタイルによっては、ガス併用の方が経済的になるケースもあるでしょう。
二重の基本料金と火災リスク

ガス併用のデメリットとしては、電気とガスの両方の基本料金がかかる点が挙げられます。
オール電化と比べて、毎月の固定費が割高になる傾向にあります。
また、ガスの使用には火災のリスクが伴うことも忘れてはいけません。
ガス漏れや不完全燃焼による事故の危険性は、オール電化に比べて高くなります。
特に高齢者や小さな子どものいる家庭では、安全面での配慮が求められるでしょう。
こまめな換気や設備の点検など、日頃からの注意が欠かせません。
オール電化とガス併用の年間光熱費比較
モデルケースによる基本料金の比較
オール電化とガス併用の光熱費を比較するために、まずは基本料金に着目してみましょう。
ここでは、一般的な3人家族を想定し、電気の契約アンペアを30Aとした場合の基本料金を見ていきます。
【基本料金の比較(東京電力管内の場合)】
オール電化(電気のみ):2,277円/月
ガス併用(電気+都市ガス):1,391円/月+896円/月=2,287円/月
ガス併用(電気+プロパンガス):1,391円/月+1,500円/月=2,891円/月
表からわかるように、オール電化とガス併用(都市ガス)の基本料金はほぼ同じです。
一方、プロパンガスを利用する場合、基本料金だけで月々500円以上の差が生じています。
地域や事業者によって多少の差はありますが、基本料金の観点からは、オール電化とガス併用(都市ガス)が拮抗していると言えるでしょう。
ランニングコストの比較

次に、実際に使用するエネルギー量に応じて変動するランニングコストを比較してみます。
オール電化とガス併用では、エネルギー料金の仕組みに違いがあるため、一概にどちらが有利とは言えません。
生活スタイルや使用量によって、光熱費の優劣が変わってくるのです。
1kWhあたりのエネルギーコスト
オール電化とガス併用のランニングコストを比べるには、1kWhあたりのエネルギーコストを知ることが重要です。
東京電力管内の料金を例に、それぞれのエネルギーコストを見てみましょう。
【1kWhあたりのエネルギーコスト(税込)】
オール電化(電気のみ):27円~29円
ガス併用(都市ガス):22円~28円
ガス併用(プロパンガス):60円~80円
この表から、都市ガスのエネルギーコストが最も安いことがわかります。
オール電化の電気料金は、都市ガスとほぼ同等か、やや高めの水準にあります。
プロパンガスは、圧倒的に高コストであることが明らかです。
日中と夜間の料金差
オール電化の料金プランには、時間帯別の電力料金が設定されているものが多くあります。
具体的には、日中の電力需要が高い時間帯は割高に、深夜など需要が低い時間帯は割安になるよう、メリハリがつけられています。
【オール電化の時間帯別料金例(東京電力エリア)】
昼間(8時~22時):29.5円/kWh
夜間(22時~翌8時):17.8円/kWh
一方、ガス料金には時間帯の区別がありません。
したがって、在宅時間が長く、日中に電気をよく使う家庭ではガス併用の方が有利になる可能性があります。
逆に、日中は家を空けていて、夜間に電力をメインで使う家庭ならオール電化の方が光熱費を抑えられるでしょう。
このように、オール電化とガス併用のランニングコストは、ライフスタイルに応じて使い分けることが賢明だと言えます。
画一的な判断ではなく、自家庭の生活パターンをよく分析した上で、最適な選択をすることが肝要です。
オール電化とガス併用のおすすめ世帯
オール電化が適している家庭

オール電化は、以下のような家庭におすすめです。
【オール電化に向いている家庭】
- 日中は家を留守にしていることが多い共働き世帯
- 深夜や早朝に電気をよく使う生活パターンの世帯
- 火を使うことへの不安やリスクを避けたい世帯
- 光熱費の支払いを一本化したい世帯
オール電化の料金プランでは、夜間の電力料金が割安になっていることが特徴です。
そのため、日中は家を空けていて、帰宅後や休日に電気を集中的に使うライフスタイルの家庭では、光熱費を抑えられる可能性が高いです。
また、オール電化は火を使わないので、火災のリスクや料理の際のヤケドの心配が少ないのも魅力です。
小さな子どもやペットがいる家庭、高齢者の単身世帯などでは、安全面からオール電化を選ぶケースが増えています。
ガス併用が適している家庭
一方、ガス併用は次のような家庭に向いています。
【ガス併用に向いている家庭】
- 在宅時間が長く、日中もエネルギーをよく使う世帯
- 都市ガスが利用可能な地域に住んでいる世帯
- ガスならではの料理や暖房方式を好む世帯
- 停電時のリスクヘッジを重視する世帯
ガス併用の最大のメリットは、都市ガスの安価なエネルギーコストを活用できる点にあります。
特に、日中から給湯や暖房をよく使う家庭では、都市ガスの利用によって光熱費の節約が可能です。
また、ガスコンロの火力の強さを生かした料理を好む人や、ガスファンヒーターの暖かさを好む人にとっては、ガス併用の方が快適に過ごせるでしょう。
さらに、災害時の停電リスクを分散できるのもガス併用の利点の一つです。
オール電化だと停電時に何もできなくなりますが、ガス併用なら電気とガスを使い分けられるので、どちらかが止まっても生活への影響を最小限に抑えられます。
ライフスタイルに合わせた選択の重要性
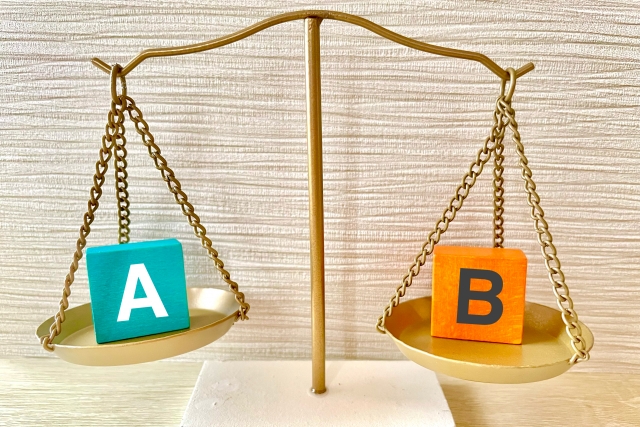
以上のように、オール電化とガス併用にはそれぞれ向き不向きがあることがわかります。
したがって、新築やリフォームの際は、自分の家庭の生活スタイルをよく見極めた上で選択することが重要です。
単に光熱費の安さだけでなく、安全性や利便性、将来的な変化への適応力なども考慮に入れましょう。
また、オール電化とガス併用は、それぞれ 地域や住宅の特性によって導入のしやすさが異なることにも留意が必要です。
都市ガスが通っていない地域では、ガス併用のハードルが高くなります。
一方、狭小地や都心部の高層マンションでは、ガスボンベの設置スペースが確保しにくいため、オール電化の方が現実的だったりします。
このように、ライフスタイルや住環境に合わせてトータルで判断することが、賢明な選択につながるのです。
それぞれの特徴をよく理解した上で、自分に合ったシステムを選びましょう。
光熱費を抑えるための工夫
オール電化の料金プラン見直し

オール電化ユーザーにとって、光熱費を抑える最も効果的な方法の一つが、電力会社や料金プランの見直しです。
特に、近年は電力自由化の影響で、多様な料金メニューが登場しています。
中でも、時間帯別料金制は、オール電化ユーザーにおすすめのプランと言えます。
これは、電力の需要が少ない夜間や早朝の時間帯に合わせて、割安な電気料金を設定するしくみです。
在宅時間が短い共働き世帯や、深夜にエコキュートを稼働させている家庭などでは、この時間帯別プランに切り替えることで、大幅な節約効果が期待できます。
また、最近は再生可能エネルギー由来の電力を扱う新電力会社も増えてきました。
これらの事業者は、環境に優しいだけでなく、料金体系もシンプルでお得なケースが少なくありません。
自分の生活スタイルに合った電力会社やプランを選ぶことが、賢い光熱費削減の第一歩と言えるでしょう。
プロパンガス会社の切り替えや値下げ交渉
ガス併用の家庭、特にプロパンガスユーザーにとって頭の痛い問題が、ガス料金の高さです。
都市ガスと違って、プロパンガスは料金が自由化されているため、地域や事業者によって大きな価格差があります。
そこで、光熱費を抑えるための有効な手段が、ガス会社の切り替えや値下げ交渉です。
プロパンガスは、都市ガスのような導管網を必要としないため、契約の切り替えが比較的容易に行えます。
複数の事業者から見積もりを取り、料金や サービス内容を比較することで、よりお得な会社に乗り換えられる可能性があります。
また、現在の契約先と値下げ交渉を行うことも一つの選択肢です。
ほかの事業者の料金表を提示して、競争原理を働かせることで、ガス料金の引き下げにつなげられるかもしれません。
ただし、安さだけでなく、サービスの質や信頼性、緊急時の対応力なども総合的に判断することが大切です。
安易な乗り換えは、かえってトラブルのもとになりかねないので、慎重に検討しましょう。
省エネ家電の導入と適切な使用方法

光熱費を抑えるもう一つの重要なポイントが、家電製品の選び方と使い方です。
オール電化もガス併用も、家電の消費電力が光熱費に直結するため、省エネタイプの機器を選ぶことが賢明だと言えます。
特に、エアコンや冷蔵庫、給湯器など、電力消費量の大きい家電は、少し高くても省エネモデルを選ぶだけで、トータルの光熱費を大幅に下げられる可能性があります。
また、製品の性能を十分に発揮させるためには、適切な使い方を心がけることも大切です。
エアコンであれば、フィルターを定期的に掃除したり、設定温度を適切に管理したりすることが電気代の節約につながります。
冷蔵庫なら、開け閉めの回数を減らしたり、詰め込みすぎないようにしたりすることで、無駄な電力消費を抑えられます。
こうしたちょっとした工夫の積み重ねが、光熱費削減の大きな武器になるのです。
省エネ家電への買い替えは初期投資が必要ですが、長い目で見れば、光熱費の節約につながる賢明な選択だと言えるでしょう。
まとめ

オール電化とガス併用、どちらの光熱費が安くなるかは、一概には言えません。
世帯人数や在宅時間、料理や暖房の使用頻度など、ライフスタイルによって最適な選択は異なるからです。
したがって、新築やリフォームの際は、各家庭の生活パターンをよく分析した上で、トータルコストを見極めることが重要です。
その上で、電力会社の料金プランを見直したり、ガス会社の切り替えを検討したり、省エネ家電を導入したりと、光熱費を抑えるための具体的な工夫を実践していくことが求められます。
無理のない範囲で、できることから始めるのが賢明でしょう。
何より大切なのは、オール電化とガス併用の特徴を正しく理解し、自分の家庭に合ったシステムを選ぶことです。
イニシャルコストだけでなく、ランニングコストやメンテナンス性、安全性など、さまざまな角度から総合的に判断することが肝要だと言えます。
そして、選んだシステムの特性を生かしながら、光熱費削減のための日々の努力を重ねていくことが、快適で経済的な暮らしへの近道なのです。
オール電化もガス併用も、上手に付き合えば、どちらも私たちの豊かな生活を支えてくれる心強いパートナーになるはずです。
この記事を書いた人
TRENDLINE編集部
TRENDLINE編集部
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。





