スタッフ紹介 2025.08.26
賃貸でも使える家庭用蓄電池!選び方と設置方法を徹底解説
近年、台風や地震などの自然災害が増加するなか、停電への備えとして家庭用蓄電池への関心が高まっています。 しかし、賃貸住宅にお住まいの方のなかには「蓄電池は戸建て専用では?」「工事ができないから無理かも」とあきらめている方も多いのではないでしょうか。 じつは、賃貸マンションやアパートでも設置できる蓄電池があることをご存じですか? 本記事では、賃貸住宅でも導入可能な家庭用蓄電池の種類から、選び方、設置方法まで詳しく解説します。 電気代の節約や災害への備えを検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

目次
賃貸住宅でも設置できる蓄電池の種類と条件

賃貸住宅における蓄電池の設置は、適切な製品選びと事前確認により実現可能です。 太陽光発電システムがなくても、系統に連系しなくても使える蓄電池があり、マンションやアパートにお住まいの方でも十分に活用できます。 ここでは、賃貸住宅に設置可能な蓄電池の種類と、導入にあたって確認すべき条件について詳しく解説していきます。
工事不要で使える2つのタイプ
賃貸住宅で蓄電池を導入する場合、大規模な工事ができないという制約があります。 しかし、工事不要または簡易な工事で設置できる蓄電池なら、賃貸でも問題なく導入可能です。 賃貸向けの蓄電池は、主に「ポータブル型」と「スタンドアロン型」の2種類に分けられ、それぞれに特徴があります。
ポータブル型蓄電池の特徴
ポータブル型蓄電池は、その名のとおり持ち運び可能なコンパクトサイズの蓄電池です。 容量は主に1kWh以下のものが多く、価格帯は3万円から10万円程度と比較的手頃な価格で購入できます。 最大の特徴は、コンセントから充電するだけで使用でき、特別な工事が一切不要な点にあります。
ポータブル型蓄電池の主な特徴: ・重量が10kg〜30kg程度で移動が容易 ・家電量販店やネット通販で購入可能 ・即日使用開始できる手軽さ ・キャンプやアウトドアでも活用可能 ・停電時はすぐに持ち出して使用できる
ただし、容量が小さいため、冷蔵庫や電子レンジなどの消費電力が大きい家電を長時間使用することは困難です。 スマートフォンの充電やLED照明、扇風機などの小型家電の使用に適しており、非常時の最低限の電力確保を目的とする場合に最適です。 また、日常的な電気代節約効果は限定的なため、主に防災用品としての位置づけで考えるとよいでしょう。
スタンドアロン型蓄電池の特徴
スタンドアロン型(非連系型)蓄電池は、定置型でありながら系統連系工事が不要な蓄電池です。 容量は1kWh〜5kWh程度と、ポータブル型より大きく、価格は50万円〜130万円程度となります。 本体に付属のコンセントから電気を供給する仕組みで、賃貸住宅でも簡単に導入できるのが特徴です。
スタンドアロン型の主なメリット: ・ポータブル型より大容量で実用的 ・簡易な設置工事で済む(配線工事程度) ・屋内・屋外両方に設置可能な製品もある ・普段使いと非常用の両方に対応 ・タイマー機能で深夜電力を活用できる製品も
設置にあたっては、本体を固定する程度の簡単な工事で済むため、賃貸住宅でも導入しやすくなっています。 なかには、エアコンの配管穴を利用して配線を通すことで、壁に新たな穴を開けずに設置できる製品もあります。 容量が大きいぶん、日常的な電気代節約効果も期待でき、停電時にも複数の家電を同時に使用できる実用性の高さが魅力です。
賃貸での設置可否の確認方法
賃貸住宅で蓄電池を設置する際は、事前の確認作業が非常に重要です。 勝手に設置してトラブルになることを避けるため、必要な手続きをしっかりと踏んでから導入しましょう。 ここでは、確認すべき事項と手順について詳しく解説します。
オーナー・管理会社への確認事項
賃貸住宅に蓄電池を設置する場合、まず最初にオーナーまたは管理会社への確認が必須です。 たとえ工事不要のポータブル型であっても、事前に相談しておくことでトラブルを回避できます。 確認の際は、以下の点を明確に伝えることが重要です。
確認時に伝えるべき項目:
- 設置したい蓄電池の種類とサイズ
- 設置予定場所(室内・ベランダなど)
- 工事の有無と内容(簡易工事の場合は詳細を説明)
- 作動音のレベル(35〜40db程度)
- 退去時の原状回復方法
- 設置による建物への影響の有無
特に重要なのは、原状回復に関する取り決めです。 スタンドアロン型で壁に固定金具を取り付ける場合、退去時に穴を補修する必要があるかどうかを事前に確認しましょう。 また、ベランダに設置する場合は、避難経路を塞がないことや、共用部分の使用ルールについても確認が必要です。
管理会社によっては、防災対策として蓄電池の設置を歓迎するケースもあります。 近年の災害増加を受けて、入居者の安全確保に理解を示すオーナーも増えているため、丁寧に説明すれば許可を得られる可能性は十分にあります。 ただし、書面での許可を得ておくことで、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。
分譲マンションと賃貸の違い
分譲マンションと賃貸住宅では、蓄電池設置に関するルールが大きく異なります。 分譲マンションの場合、各住戸は購入者の所有物となるため、専有部分については比較的自由に設備を導入できます。 一方、賃貸住宅は借り物であるため、さまざまな制約があることを理解しておく必要があります。
分譲マンションでの設置条件: ・専有部分(室内)は原則自由に設置可能 ・ベランダは共用部分のため管理組合の許可が必要 ・管理規約で禁止事項がないか確認 ・近隣への配慮は賃貸同様に必要 ・大規模な工事は理事会の承認が必要な場合も
賃貸住宅での設置条件: ・オーナーの許可が絶対条件 ・原状回復義務があるため工事内容に制限 ・設置場所の選択肢が限られる ・作動音などで他の入居者に迷惑をかけない配慮 ・契約書の特約事項を確認
分譲マンションでは、すでに太陽光発電システムと蓄電池が共用設備として設置されているケースも増えています。 このような物件では、各住戸に電力が割り当てられる仕組みになっていることもあり、個別に蓄電池を設置する必要がない場合もあります。 賃貸住宅でも、最近では防災対策として蓄電池を備えた物件が登場しており、そのような物件を選ぶことも一つの選択肢となるでしょう。
賃貸向けおすすめ蓄電池4選と選び方

賃貸住宅に適した蓄電池を選ぶには、各製品の特徴を理解し、自分の住環境に合ったものを選ぶことが重要です。 ここでは、賃貸での使用に適した代表的な4製品を詳しく紹介し、選定時のポイントについて解説します。 各製品の特徴を比較しながら、最適な蓄電池選びの参考にしてください。
各メーカーの特徴比較
賃貸住宅向けの蓄電池市場では、大手メーカーから特徴的な製品が発売されています。 それぞれに独自の強みがあり、使用環境や目的に応じて選択することが大切です。 以下、代表的な4製品について、その特徴を詳しく見ていきましょう。
主要4製品の比較表:
| メーカー | 容量 | サイズ(幅×高さ×奥行) | 重量 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック LJSF35 | 3.5kWh | 625×598×240mm | 60kg | 80〜100万円 |
| 住友電工 POWER DEPO Ⅴ | 3.3kWh | 550×760×275mm | 54kg | 90〜110万円 |
| エリーパワー POWER YIILE Ⅲ | 2.5kWh | 320×585×514mm | 52kg | 70〜90万円 |
| ニチコン ESS-P1S1 | 2.0kWh | 250×380×550mm | 38kg | 50〜70万円 |
パナソニック LJSF35
パナソニックのLJSF35は、家電メーカーならではの使いやすさと信頼性が特徴の蓄電池です。 容量3.5kWhと十分な電力を確保でき、4人家族でも安心して使用できるサイズとなっています。 最大の特徴は、電気料金が安い深夜に自動充電するタイマー機能を搭載している点です。
この製品の優れた点は、USB端子を4個も搭載していることです。 停電時にスマートフォンやタブレットなど、複数のデバイスを同時に充電できるため、家族全員の通信手段を確保できます。 また、震度6強レベルの地震でも転倒しない高い耐震性を実現しており、マンションの中層階でも安心して設置できる設計となっています。
操作性も優れており、大型ディスプレイで充電状況や使用可能時間が一目でわかります。 コンセントは2個装備されているため、照明と暖房器具など、複数の家電を同時に使用することも可能です。 パナソニック独自の安全基準をクリアした製品であり、長期間の使用でも安心感があります。
住友電工 POWER DEPO Ⅴ
住友電工のPOWER DEPO Ⅴは、賃貸住宅での使用を強く意識した画期的な製品です。 最大の特徴は、屋外設置が可能な防水・防塵設計を採用している点にあります。 室内のスペースが限られる賃貸住宅でも、ベランダに設置できるため、居住空間を圧迫しません。
この製品は本体にコンセントがない代わりに、分電盤に接続して使用するオフグリッドタイプです。 一見すると工事が大掛かりに思えますが、実際はエアコンの配管穴から配線を引き込むだけで設置可能です。 これにより、壁に新たな穴を開けることなく、単機能蓄電池のように家全体に電力を供給できます。
サイズはエアコン室外機の約3分の2とコンパクトで、ベランダでも邪魔になりません。 容量3.3kWhは、停電時でも冷蔵庫や照明、通信機器などを十分に稼働させることができます。 屋外設置のため作動音が室内に響きにくく、近隣への配慮も十分になされた設計となっています。
エリーパワー POWER YIILE Ⅲ
エリーパワーのPOWER YIILE Ⅲは、可搬性と実用性を両立させた蓄電池です。 業界最小・最軽量クラスのコンパクト設計でありながら、2.5kWhという実用的な容量を確保しています。 キャスター付きで移動が簡単なため、普段は部屋の隅に置いておき、必要な時にすぐ移動できる利便性があります。
この製品の大きな特徴は、12,000サイクルという圧倒的な長寿命を実現している点です。 毎日充放電を繰り返しても、約33年間使用できる計算となり、長期的なコストパフォーマンスに優れています。 また、スマートフォンアプリで操作できるため、本体のボタン操作が苦手な方でも直感的に使用できます。
太陽光パネルから直接DC充電も可能な設計となっており、将来的に太陽光発電を導入したい方にも適しています。 アプリでは充電状況の確認だけでなく、使用履歴の確認や充電スケジュールの設定も可能です。 コンパクトながら実用性の高い、バランスの取れた製品といえるでしょう。
ニチコン ESS-P1S1
ニチコンのESS-P1S1は、「ちょこ電」の愛称で親しまれている小型蓄電池です。 容量2.0kWhと今回紹介する中では最も小さいですが、UPS(無停電電源装置)機能を搭載している点が大きな特徴です。 停電時の切り替えがわずか10ms(0.01秒)で完了するため、パソコンなどの精密機器も安心して接続できます。
重量38kgと軽量で、女性でも移動させやすい設計となっています。 本体サイズも非常にコンパクトで、ワンルームマンションでも設置場所に困りません。 価格も50万円台からと比較的手頃で、初めて蓄電池を導入する方にも適しています。
日常使いでは、在宅ワーク中の停電対策として威力を発揮します。 パソコンやWi-Fiルーター、照明などを接続しておけば、停電が発生してもそのまま作業を続けることができます。 また、夏場の冷蔵庫対策としても有効で、数時間程度なら問題なく稼働を維持できる容量があります。
賃貸で重視すべき選定ポイント
賃貸住宅で蓄電池を選ぶ際は、戸建て住宅とは異なる視点での選定が必要です。 限られたスペースや原状回復の必要性、近隣への配慮など、賃貸特有の制約を考慮しながら最適な製品を選びましょう。 ここでは、特に重要な選定ポイントについて詳しく解説します。
容量・サイズ・作動音の確認
蓄電池選びで最初に検討すべきは、必要な容量の見極めです。 一般的な4人家族の1日の電力消費量は約10kWhといわれていますが、賃貸住宅では全ての電力を蓄電池でまかなう必要はありません。 停電時の最低限の生活維持と、日常的な電気代節約のバランスを考えて容量を選びましょう。
容量選定の目安: ・1〜2人暮らし:1.5〜2.5kWh ・3〜4人家族:2.5〜3.5kWh ・在宅ワーク中心:3.0kWh以上推奨
サイズについては、設置予定場所の寸法を正確に測定することが重要です。 特に搬入経路の確認は忘れがちですが、エレベーターや廊下、玄関ドアのサイズも事前にチェックしましょう。 階段での搬入が必要な場合は、重量も重要な要素となります。
作動音は35〜40db程度が一般的で、これは図書館内や静かな住宅街の昼間と同程度の音量です。 しかし、深夜の静かな時間帯では気になる可能性があるため、寝室から離れた場所に設置するなどの配慮が必要です。 メーカーによっては静音モードを搭載した製品もあるので、音に敏感な方はそのような機能も確認しましょう。
設置場所別の製品選び
賃貸住宅での蓄電池の設置場所は、主に「室内」「ベランダ」「共用廊下側」の3つに分けられます。 それぞれの設置場所に適した製品選びのポイントを理解しておきましょう。
室内設置の場合: ・コンパクトで軽量な製品を選ぶ ・インテリアに馴染むデザイン性も考慮 ・作動音が小さい製品を優先 ・キャスター付きなど移動しやすいタイプ ・推奨製品:エリーパワー、ニチコン
ベランダ設置の場合: ・防水・防塵性能が高い屋外対応製品 ・台風などの強風に耐える固定方法 ・避難経路を塞がないサイズ ・エアコン室外機との干渉を避ける配置 ・推奨製品:住友電工 POWER DEPO Ⅴ
共用廊下側設置の場合: ・管理規約で許可されているか要確認 ・通行の妨げにならない薄型タイプ ・防犯対策(盗難防止)も考慮 ・メンテナンスしやすい位置に配置
設置場所によって適した製品が異なるため、まずは設置可能な場所を確定させてから製品選びを進めることが重要です。 また、将来の引っ越しも考慮して、さまざまな環境で使いやすい汎用性の高い製品を選ぶことも賢明な選択といえるでしょう。
賃貸で蓄電池を導入するメリット・デメリット
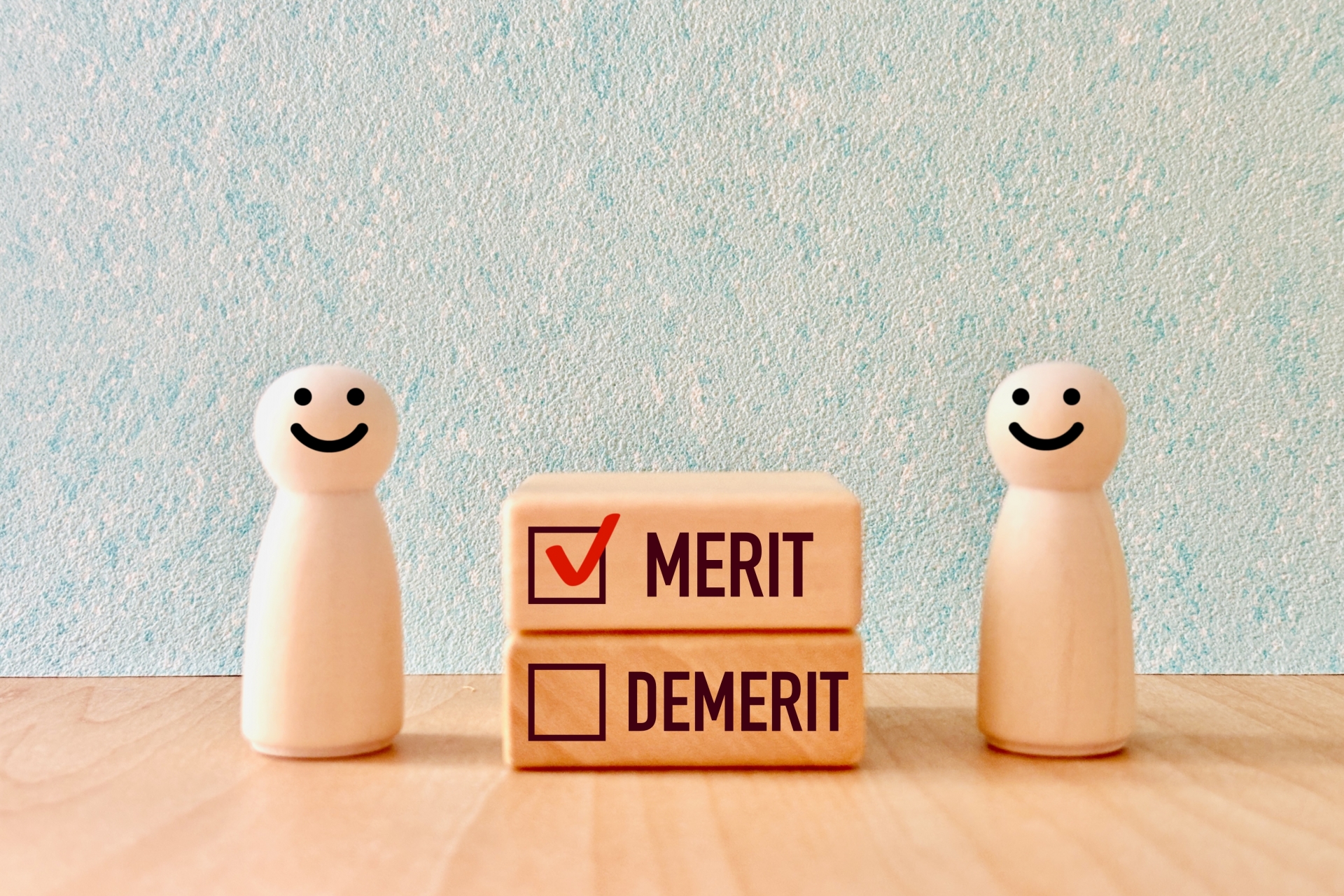
賃貸住宅での蓄電池導入には、戸建て住宅とは異なる特有のメリットとデメリットがあります。 導入を検討する際は、これらを十分に理解した上で、自分のライフスタイルに合った判断をすることが大切です。 ここでは、賃貸ならではの視点から、蓄電池導入の利点と注意点を詳しく解説します。
導入メリット
賃貸住宅で蓄電池を導入することには、想像以上に多くのメリットがあります。 単なる停電対策だけでなく、日常生活の質を向上させ、経済的な恩恵も受けられる可能性があります。 特に、賃貸特有の制約がある中でも実現できるメリットに注目してみましょう。
停電時の備えと電気代節約
蓄電池の最大のメリットは、なんといっても停電時の電力確保です。 近年、台風や地震などの自然災害が頻発し、都市部でも長時間の停電が発生するケースが増えています。 賃貸住宅では、建物全体の非常用電源がない場合が多く、個人での備えが特に重要になります。
停電時に確保できる主な機能: ・冷蔵庫の稼働維持(食品の保存) ・照明の確保(安全な移動と生活) ・通信機器の充電(情報収集と連絡手段) ・空調機器の使用(熱中症対策) ・医療機器の稼働(必要な方のみ)
また、電気代の節約効果も見逃せません。 多くの電力会社では、深夜の電気料金が昼間の半額以下に設定されているプランがあります。 タイマー機能付きの蓄電池なら、安い深夜電力で充電し、料金の高い昼間に蓄電池の電気を使うことで、月々の電気代を10〜30%程度削減できる可能性があります。
具体的な節約例として、月1万円の電気代がかかっている家庭の場合、年間で1万2,000円〜3万6,000円の節約が期待できます。 蓄電池の導入費用を考えると、短期的には元が取れないかもしれませんが、防災対策としての価値を含めて考えれば、十分に投資価値があるといえるでしょう。
引っ越し時も持ち運び可能
賃貸住宅ならではの大きなメリットが、引っ越し時に蓄電池を持っていける点です。 太陽光発電システムのような固定設備と異なり、ポータブル型やスタンドアロン型の蓄電池は移動が可能なため、転居先でも継続して使用できます。 これにより、一度購入すれば長期間にわたって活用でき、投資効率が高くなります。
引っ越しのしやすさを考慮した選び方: ・重量50kg以下の製品を選ぶ ・分解・組み立てが簡単な構造 ・汎用性の高い100Vコンセント充電タイプ ・梱包材を保管しておく ・搬出入経路を事前に確認
特に転勤が多い方や、将来的に住み替えを検討している方にとって、このメリットは非常に大きいといえます。 購入時は「今の住まいだけでなく、次の住まいでも使えるか」という視点で製品を選ぶことが重要です。 また、中古市場でも需要があるため、不要になった場合は売却することも可能です。
賃貸住宅では、設備投資が無駄になりがちですが、蓄電池なら資産として持ち続けることができます。 これは、賃貸生活者にとって大きな安心材料となるでしょう。
注意すべきデメリット
一方で、賃貸住宅での蓄電池導入には、いくつかのデメリットや注意点も存在します。 これらを事前に理解し、対策を講じることで、トラブルを避けながら快適に使用することができます。 デメリットを正しく認識することは、後悔のない導入判断につながります。
初期費用と設置スペース
蓄電池導入の最大のハードルは、やはり初期費用の高さです。 ポータブル型でも3万円以上、実用的なスタンドアロン型では50万円〜130万円という高額な投資が必要になります。 賃貸住宅の場合、長期居住が保証されていないため、投資回収の見通しが立てにくいという課題があります。
初期費用の内訳例(スタンドアロン型の場合): ・本体価格:70〜100万円 ・設置工事費:5〜10万円 ・搬入費用:1〜3万円 ・付属品・オプション:2〜5万円 ・合計:78〜118万円程度
また、設置スペースの確保も大きな課題です。 賃貸住宅は一般的に戸建てより狭く、収納スペースも限られています。 蓄電池は常時設置しておく必要があるため、貴重な居住空間を占有することになります。 特にワンルームや1DKなどの単身者向け物件では、設置場所の選定に苦労することが予想されます。
費用対効果を高めるためには、補助金制度の活用や、中古品の検討なども選択肢に入れるとよいでしょう。 また、レンタルサービスを提供している業者もあるため、初期費用を抑えたい場合は検討する価値があります。
近隣への配慮と原状回復
賃貸住宅特有の課題として、近隣住民への配慮があります。 蓄電池の作動音は35〜40db程度と決して大きくありませんが、深夜の静かな環境では気になる可能性があります。 特に壁が薄い物件や、隣室と接する壁際に設置する場合は、トラブルの原因となる可能性があります。
近隣トラブルを避けるための対策: ・設置前に隣室の住民に説明 ・防音マットや防振ゴムの使用 ・夜間は充電モードを静音設定に ・定期的なメンテナンスで異音を防ぐ ・苦情があった場合は速やかに対応
また、退去時の原状回復も重要な検討事項です。 スタンドアロン型で壁に固定具を取り付けた場合、穴の補修費用が発生します。 一般的な補修費用は1箇所あたり5,000円〜1万円程度ですが、複数箇所ある場合や、特殊な壁材の場合はさらに高額になる可能性があります。
原状回復を最小限に抑えるためには、できるだけ建物に手を加えない設置方法を選ぶことが重要です。 突っ張り棒型の固定具や、重量で安定させるタイプなど、壁に穴を開けない固定方法も検討しましょう。 事前にオーナーと相談し、どこまでの改変が許容されるか確認しておくことも大切です。
設置手順と活用方法
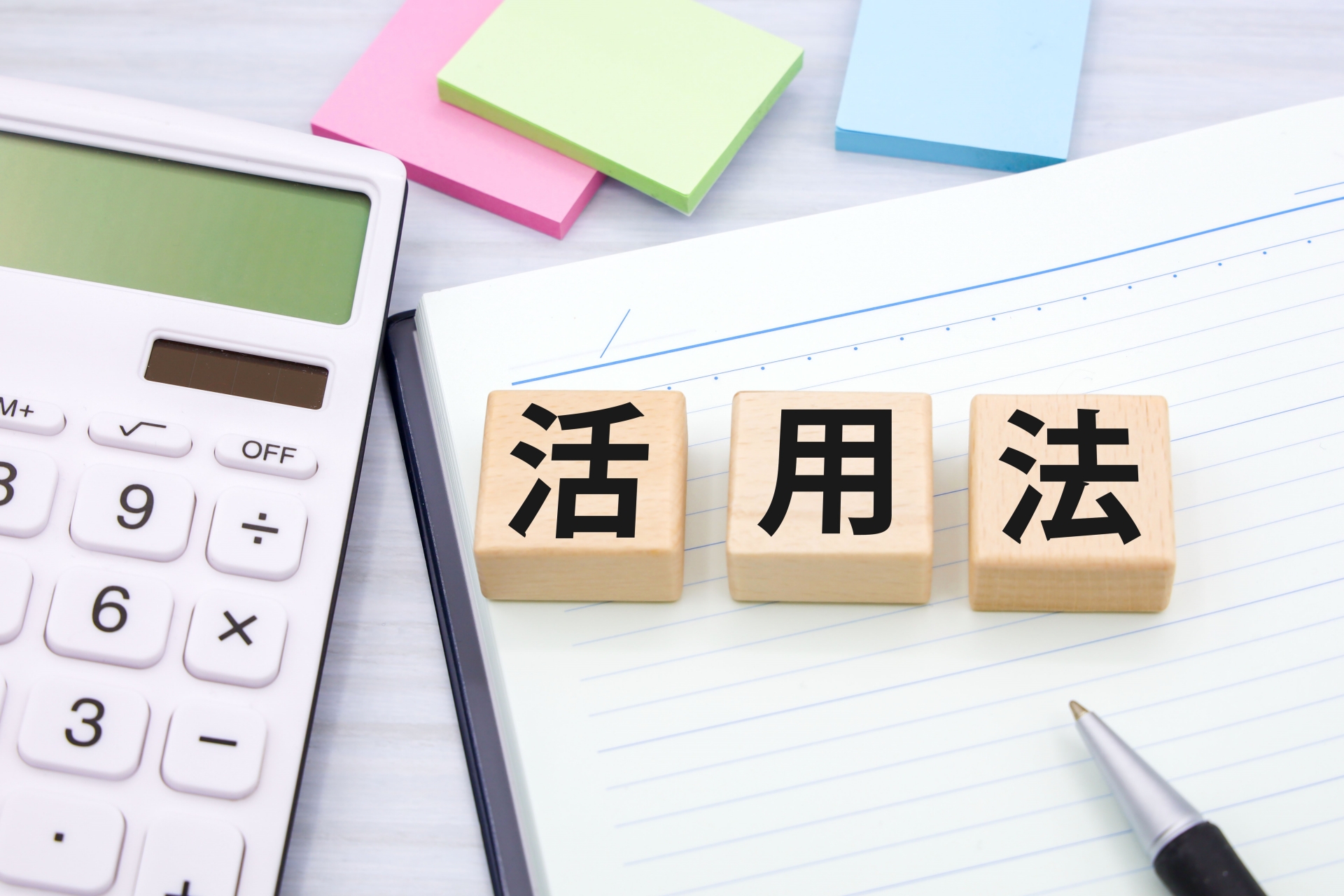
賃貸住宅での蓄電池導入を成功させるには、適切な手順を踏むことが重要です。 また、導入後の活用方法を理解しておくことで、投資効果を最大化できます。 ここでは、実際の設置プロセスから日常的な使い方、さらには利用可能な補助金制度まで、実践的な情報を詳しく解説します。
設置の流れと注意点
蓄電池の設置は、準備から実際の設置まで、段階的に進める必要があります。 賃貸住宅では特に、各ステップで確認すべき事項が多いため、チェックリストを作成して進めることをおすすめします。 以下、具体的な設置の流れを見ていきましょう。
設置までの基本的な流れ:
- 設置場所の選定と採寸
- オーナー・管理会社への相談と許可取得
- 製品の選定と見積もり取得
- 補助金申請の検討
- 購入と配送手配
- 設置工事(必要な場合)
- 動作確認と初期設定
まず、設置場所の選定では、コンセントからの距離、搬入経路、日常の動線を考慮します。 できれば複数の候補地を用意し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討しましょう。 採寸は、本体サイズだけでなく、メンテナンススペースも含めて行うことが重要です。
オーナーへの相談では、製品カタログや設置イメージ図を持参すると理解を得やすくなります。 特に、防災対策としての側面を強調し、建物の資産価値向上にもつながることを説明すると効果的です。 許可を得られたら、必ず書面で確認を取り、後日のトラブルを防ぎましょう。
設置工事が必要な場合は、施工業者の選定も重要です。 賃貸住宅での施工経験がある業者を選び、原状回復を考慮した施工方法を相談しましょう。 工事当日は立ち会いを行い、予定どおりの施工が行われているか確認することが大切です。
日常・非常時の活用シーン
蓄電池を導入したら、日常生活でも積極的に活用することで、投資効果を高めることができます。 また、非常時にスムーズに使用するためには、平常時からの準備と練習が欠かせません。 ここでは、具体的な活用シーンと準備方法を紹介します。
日常的な活用方法: ・深夜電力での充電と昼間の使用 ・在宅ワーク時のバックアップ電源 ・電力使用量のピークカット ・家電の待機電力カット ・電気料金プランの見直しと最適化
特に効果的なのは、電力需要が高まる夏の昼間のエアコン使用です。 蓄電池からの電力供給により、電力会社からの購入電力を抑えることで、基本料金の削減にもつながります。 また、在宅ワークが増えた現在、急な停電でも仕事を継続できる環境は大きな安心材料となります。
非常時の活用では、優先順位を決めた電力使用計画が重要です。 まず生命維持に必要な機器(医療機器など)、次に情報収集手段(スマホ、ラジオ)、そして生活維持機器(冷蔵庫、照明)の順で接続します。 定期的に停電を想定した訓練を行い、家族全員が操作方法を理解しておくことも大切です。
非常時に備えた準備リスト: ・延長コードと変換プラグの常備 ・使用する家電の消費電力リスト作成 ・充電ケーブル類の整理と保管 ・取扱説明書のわかりやすい場所への保管 ・緊急連絡先リストの作成
利用可能な補助金制度
蓄電池の導入費用を軽減する方法として、各種補助金制度の活用があります。 国や自治体では、防災対策や環境対策の一環として、家庭用蓄電池の導入を支援する制度を設けています。 賃貸住宅でも利用できる制度があるため、積極的に活用しましょう。
主な補助金制度の種類: ・国の補助金(経済産業省、環境省など) ・都道府県の補助金 ・市区町村の補助金 ・電力会社の補助制度 ・リース・レンタル事業者の優遇制度
たとえば、東京都では「家庭に対する蓄電池等補助事業」があり、集合住宅の居住者も対象となっています。 補助額は機器費の2分の1(上限あり)で、条件を満たせば数十万円の補助を受けられる可能性があります。 申請には、オーナーの同意書が必要な場合があるため、事前に確認しておきましょう。
補助金申請の注意点として、多くの制度が先着順や予算上限があることが挙げられます。 年度初めに募集が開始されることが多いため、前年度から情報収集を始めることが重要です。 また、工事前申請が必要な制度がほとんどなので、購入前に必ず申請手続きを確認してください。
申請に必要な主な書類: ・補助金交付申請書 ・見積書(指定様式の場合あり) ・賃貸借契約書の写し ・オーナーの同意書 ・設置場所の図面や写真
補助金情報は、各自治体のホームページや環境省のポータルサイトで確認できます。 また、販売店でも最新の補助金情報を把握していることが多いため、購入相談時に確認することをおすすめします。
まとめ

賃貸住宅でも、適切な製品選びと事前準備により、家庭用蓄電池の導入は十分に可能です。 ポータブル型やスタンドアロン型など、工事不要または簡易工事で設置できる製品を選べば、原状回復の心配も最小限に抑えられます。 停電対策としてはもちろん、日常的な電気代節約にも活用でき、引っ越しの際は持っていけるという賃貸ならではのメリットもあります。
導入にあたっては、オーナーや管理会社への事前相談が必須となりますが、防災意識の高まりから理解を得られるケースも増えています。 初期費用は決して安くありませんが、各種補助金制度を活用することで負担を軽減することも可能です。 製品選びでは、容量・サイズ・作動音のバランスを考慮し、自分の生活スタイルに合ったものを選ぶことが成功の鍵となります。
これからの時代、災害への備えと持続可能な生活の実現は、住まいの形態を問わず重要なテーマです。 賃貸住宅にお住まいの方も、ぜひ本記事を参考に、蓄電池導入を検討してみてはいかがでしょうか。 適切な準備と選択により、より安心で快適な生活を実現できることでしょう。
Contact
お問い合わせ
各自治体で補助金が使えるケースがございますので、
詳しくはお問い合わせください。






